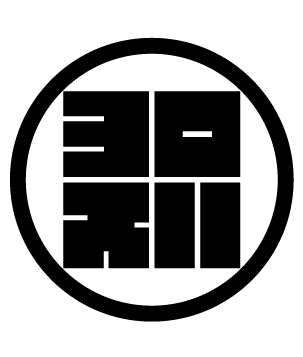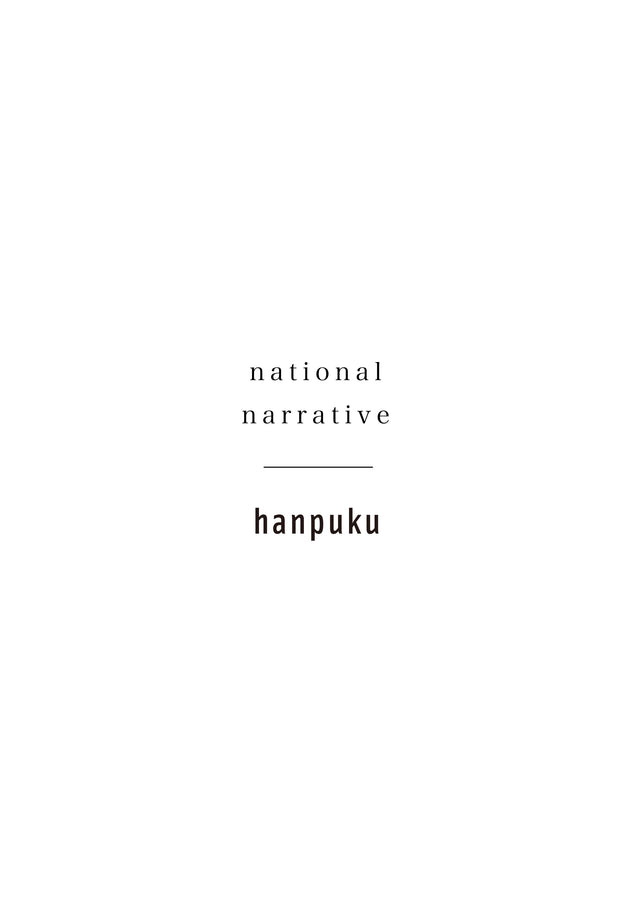
national narrative
中世期の土地を仲介とした君主-臣民関係である封建制度の崩壊/発展から主権国家というコンセプトがあらわれてくる。地方分権的な統治システムから中央集権的なモデルへの変化は絶対王政により準備され、市民革命によって国民主権が実現したことで、国民国家が成立する。このことは円環状の時間観念を基とした、固定化した身分制度がゆるやかに崩れていたことに由来する。この変化は階級なき社会を夢想させるに充分な出来事であったろうし、反対に不確定に変化する未来への不安も生み出しただろう。未来に向かう視線は直進する時間観念のイメージを人々に植え付けた。現代の人々がもつ近代的な史観はここで初めてあらわれる。
もちろん、国家は一国だけでは成立しない。複数の国家がお互いを対等な存在として承認することで初めて国家という概念が確立される。歴史的には三十年戦争後のウエストファリア条約が国家間の相互承認の契機であり、比較可能な外部の存在が規定されることで国境がより強く意味を持つようになった。
主権国家以前の世界でひとまとまりの機能としての国家を想像することは、限られたエリートのものだったが、資本主義の効率性の追求と、科学技術の進歩により、国家というビオトープのもつ輪郭があまねく人々にいきわたるようになる。このことは人々の認知する内/外の把握を大きく更新するものだった。
人々にいきわたるものとは情報である。情報の流通は言語的同一性、出版制度の成立、交通・輸送の発達という下地が支えた。逆にいえばこのような技術が揃わなければ、地域共同体の同胞の感覚を、未だ会ったことはないが、同じ国の人間である、という共通の国家意識を基とした同胞感覚まで拡張することはできなかったであろう。
国境や国家の重要性を理解しえた人々は、国という視点から自分の位置を理解できる人間、すなわち「国民」となった。現在における「国民」のイメージとはその国に国籍がある人程度のものでしかないように感じるかもしれないが、それは私たちが国という概念を既に内面化していることに依るだろう。
東アジアにおける国民国家の成立はそのほとんどが人為的なものであったと言われる。それは日本においても同様で、国家というコンセプトを持った外圧と対等に渡り合うため、それらと同様のコンセプトを持つことを意識的に選び取るに至った。近代をどのように理解するかによって、近代化の時期についてはいくつかの意見があるが、欧米で成立した”近代国家”について考えれば、日本がその体を成したのは明治期においてである。
市民革命とは農民でも貴族でもないブルジョワジーという新しい存在が、旧体制を打倒し、その身にそぐう環境を作り出すためにおこる、ある種の階級闘争であるが、日本においては藩主や武士といった旧体制に属する特権階級によって変革がおこなわれた。外圧によって近代国家としての制度を整えるということは、ボトムアップ型の国家の擁立にはなりえず、トップダウン型の権利付与式とならざるをえない。結果的に日本における近代国家は、天皇制を中心にヨーロッパ近代の制度を編成し直した、いわば絶対王政と疑似的国民主権のキメラのようなものとなった。
このような過程を経て成立した”日本のイメージ”は、王政=天皇のもつナラティブを強化することに力点がおかれていた。そのために万世一系の皇統神話が組み立てられ、神武天皇の即位日とされる日に基づいた建国記念日の制定や、神武天皇を祭神とした橿原神宮の創建などが続いた。
ナラティブの共有に基づいた民族的同一性は「ドイツ型ナショナリズム」と呼ばれる。ナポレオンの侵略によりドイツではナショナリズムが燃え上がり近代化への道を歩みはじめるわけだが、侵略という外圧から国家を防衛するために選択されたのが言語・歴史・民族の同一性を基礎としたナショナリズムだったということだ。
対となるのは「フランス型ナショナリズム」で、自由・平等・友愛といった普遍的理念に基づくナショナリズムである。市民革命から生まれた理念らしく、言語・歴史・民族に囚われない包括性の高い考えになっている。これに類するものが共産主義やアメリカの自由民主主義だ。
ただ、ナポレオンが普遍的理念を全ヨーロッパに広げると言う大義の下に征服戦争を行ったように、普遍的理念であれ、侵略や植民地支配のエクスキューズとして利用されてきたことは史実が伝えている。また冷戦期を鑑みればわかるように、普遍的理念が対立する場合もあり得る。語義矛盾的ではあるが、普遍的理念もまた、ある国家にとっての普遍であり、ナショナリズムの一形式であるということである。
「ドイツ型ナショナリズム」も全体主義に向かう下地となり、侵略戦争のエクスキューズとなった。ゲルマン民族の優越性を示すため、かつての領土を回復し、他民族他思想を殲滅せしめようとする意図から引き起こされたのが第2次世界大戦である。また、同時期に日本が行った植民地侵略においても、八紘一宇や大東亜共栄圏といった天皇を頂点に置くアジア支配の理念によって、皇民化教育や宮城遥拝などを含んだ同化政策が行われた。支配圏のすべての人民を同一民族化(日本人化)しようとするものだった。
しかし、いくら同一化教育をおこなおうと、言語・歴史・民族の同一性によって成立する「ドイツ型ナショナリズム」では、設定されたナラティブに対して実質的な共通性を持たない限り、形式以上のレベルのリアリティを発見することは困難だ。民族のナラティブを織り上げるためには整合性のためのフォーカスとフィクションの創造が往々にして起こるが、そこに求められるのはそれを人々が受け入れるための”もっともらしさ”である。そしてそのもっともらしさの土壌は、その共同体の慣習や残存する史料に由来する、曖昧な不文律に依っている。
明治期に作られたナラティブが大きく揺さぶられたのは太平洋戦争敗戦後である。52年にサンフランシスコ講和条約が発効されるまで、日本はGHQの実質的な占領状態となり、天皇と政府は統治権を失うこととなった。また、GHQ主導で作成された日本国憲法は新憲法は「国民主権・基本的人権の尊重・平和主義」のような理念を骨子とした内容で、帝国憲法にあった王権神受的な言説は省かれた。天皇においては人間宣言という奇妙かつ曖昧な宣言によって神の座から降り、象徴天皇制を受け入れたことにより主権の座からも降りることとなった。国家の屋台骨である憲法の作成に戦勝国の軍人が関わっていたことは、間接統治という手法も相まって戦後日本の主権の陰にアメリカの存在がちらつくトラウマを植え付けた。
ただ、戦前を支えた万世一系というナラティブの存在は薄まったといえど、国としてのひとまとまりの感覚が担保されていることは言を俟たないだろう。現在のショーケース的に県民を並べたテレビ番組を見て、それぞれの県ごとの違いや分からなさを安心して消費できるのは、どこかに共通する日本人という担保があることによる。江戸時代においてはクニと言われる対象が藩のスケールだったことを考えれば隔世の感だ。現在わたしたちは顔の見える隣人関係を超えた同国人への同胞感覚を、何によって担保しているのか。法によってか、制度によってか、理念によってか、他国からの承認によってか、または戦前のナラティブが生き延びたことによってか。いずれにせよ、日本のナラティブは、語り手が国家という主体から国民という主体に拡大したことで、絶対的な政策のレベルから相対的な文化領域のレベルへと変化したといえる。
生活や社会と関わるイメージは決して静的ではありえず、トップダウン型で作られたイメージは常に何かを取りこぼさざるを得ない。物語の主体が包摂可能な範囲が限られる以上、裂け目のないナラティブを現実空間に展開すれば破綻をきたすためだ。動態であるの文化の内実は、大きなナラティブに回収されえない生との緊張関係の裡に成り立っている。曖昧な同胞感覚というビオトープに働きかけるためわたし達ができることは、そこから取りこぼされるイメージや物語の断片を提示し、ボトムからそれに揺さぶりをかけつづけることである。
n.syukutani