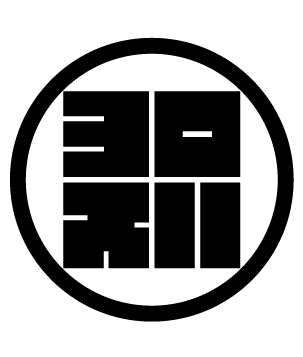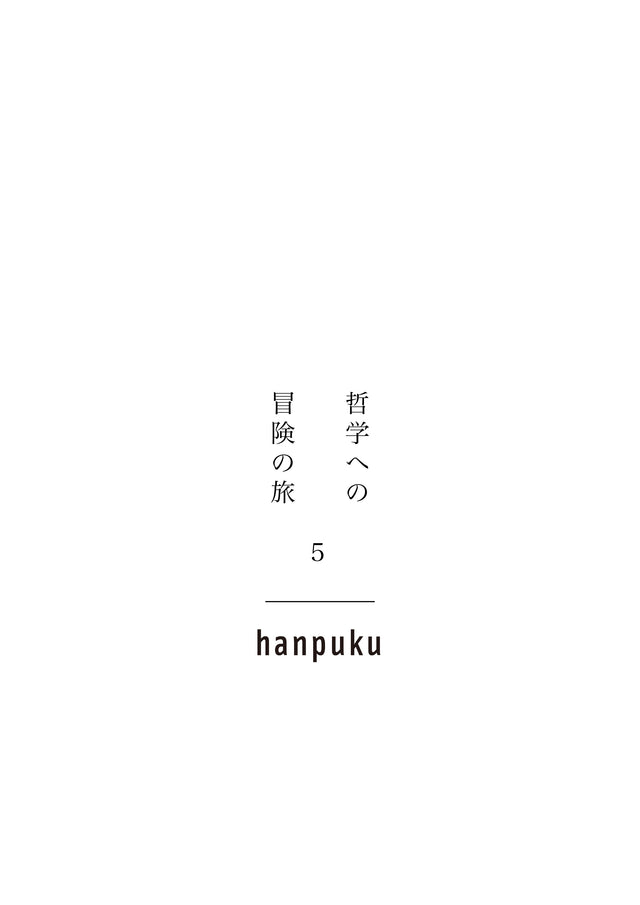
哲学への冒険の旅 5
哲学への冒険の旅 5
5 歴史の中の「時間的パラドクス」 その3 ヘーゲル
カント以降の二百数十年の西欧哲学では、主要な哲学者たちがこぞって時間的パラドクスをさまざまな形態で表現しています。問題形態はさまざまですが、時間的パラドクスに対する対処に関して言えば、共通している点があります。すなわち、時間的パラドクスの解決を断念した上で、広い意味での現象学的な哲学に向かっているという点です。「広い意味で」というのは、経験に基づいた探究、ということです。
前回述べたように、時間的パラドクスは、コペルニクス的転回と密接に繋がっています。コペルニクス的転換は、事実や現象から認識を得るのではなく、逆に事実や現象に対して認識を先行させるということでしたが、この転換を遂行しようとすれば、そもそもそうした認識をどこから、どのようにして得ることができるのか、という問題が持ち上がることは必定です。これこそ時間的パラドクスの問題です。ですが、この難問になんとかして解決を与えるのではなく、解決を断念したうえで哲学を続けようとすれば、これまた必然的に、事実や現象に従って認識を形成するという、転換前の在り方に戻らねばならないことになります。ですから、ヘーゲル、ニーチェ、フッサール、ハイデガーが、いずれも事実や現象に依拠した認識を産出しているのもうなずけます。外面的にみても、ヘーゲルの「精神現象学」、フッサールの「超越論的現象学」、ハイデガーの「現象学的存在論」と現象学のオンパレードです。ニーチェは現象学という用語を使いませんでしたが、初期ニーチェの断章には、次のような現象学を容易に連想させる言葉が記されています。「哲学者とは、自然の仕事場が自らを開示したものである。――哲学者や芸術家は、自然の手仕事の秘密について語るのである」。(1)
ただし、誤解のないように断っておきますが、転換は、一見、二者択一のように見えますが、それは原理に限定されていること、つまり、〈どこから始めるか?〉に限定してのことです。ア・プリオリな理性的認識から始められる体系のうちでは、現象学的な探究もまたそれに適した場が与えられます。ですが、現象学的な認識から始めた場合には、逆に、ア・プリオリな理性的な認識の場は欠落したままです。あたりまえですが、ア・プリオリな理性的認識を断念しているからです。しかし、それは、コペルニクス的転換を逆回転させることでもあります。つまり、前近代的な哲学の方に向き直ることを意味します。ヘーゲルはアリストテレスのうちに自分の思想を見いだし、フッサールは、ブレンターノが復活させた中世の「志向性」の概念を引き継いでいます。同様に、ハイデガーは古代ギリシャが提示した「存在」への問いを「反復」しています。ただ、ニーチェだけは、生命現象に依拠して「力への意志」を導き出しているためでしょうが、既存の哲学に依存することを断固拒否していました。そうしたことがよくないといっているのではありません。実際、そうしたことによって忘れられていたものが再生され新たな認識を生んでいることも事実ですから。ただ、そうした在り方はコペルニクス的転換においてみるなら、構造的な必然性をもっているということです。
以上を前置きにして、時間的パラドクスがどういう形態で現われているか、その解決を断念してどこに向かっているかを、ピンポイントで示してゆくことにします。さっそくヘーゲルから始めることにします(ニーチェについてはすでに触れたので省きます)。
ヘーゲルにおいて、時間的パラドクスが出現する箇所は、ずばり『精神現象学』C「理性」c「絶対的な現実性を獲得した個人」a「精神の動物王国とだまし――価値あるもの」においてです。この場所の意味については後で述べます。
ここでヘーゲルは、自分の素質をあらかじめ知って、それを成長させるという課題を提出しています。しかし、この課題はたちまち困難に陥ります。というのも、自分の素質を自分が知るためには、素質が発現されねばならないからです。つまり、自分の素質は、それがある程度発揮され、実現された後にしか知りえない、ということです。繰り返しですが、自分の素質をあらかじめ知るということは、それが発揮された後にはじめて知りうるものをあらかじめ知ることができるのでなければならない、ということですから、ここに時間的パラドクスが現われています。しかし、ヘーゲル自身は、ここに「時間的パラドクス」を見たわけではありません。彼がここに見たのは「悪循環」でした。
かくて行為におもむく意識は、一方が他方を前提するような悪循環に陥り、はじまりを見つけることができないことになる。目的となるべき根源的素質は、行為の結果からしか把握できないのに、行為を起こすには前もって目的を設定する必要がある、といった悪循環に。(2)
たしかにヘーゲルが直面しているのは、論理的に見れば、相互前提的です。結果を前提しなければ目的は設定できす、目的の設定を前提しなければ、行為はおこなえず結果は生まれないからです。これは理論的には解決不能です。ただ、ここで問われているのは意識的な「行為」です。ですから、「はじまりを見つけることができない」ということが行為することにとっての障害になるわけです。つまり、ヘーゲルはそこに理論的課題ではなく、行為するための障害を見ているのです。ですから、解決もまた「行為」によって行われることになります。
まさしくそれゆえに、意識はいきなりはじめなければならず、どのような状況のもとにあっても、はじまりがどうの、手段がどうの、終わりがどうの、と思いめぐらすことなく、動きださねばならない。(3)
要するに、意識の中でぐるぐる回っているのではなく、ともかく経験に飛び込めと、と言っているわけです。といっても、どんな経験なのかもわからずに闇雲に、経験に飛び込めと言っているわけではなく、ヘーゲルがこの先に言っていることは、「関心」の経験です。
はじまりとなる素質は行動の状況のうちに存在するので、個人がなにかに関心をいだくとき、すでにして、行為すべきかいなか、なにを行為すべきか、という問いに対する答えが与えられている。というのも、目の前の現実のありさまと見えるものは、もともと意識のうまれもっての素質であったものが存在というすがたをとってあらわれたものにすぎず、それも、行為が自他の分裂を前提するがゆえにそういうすがたをとったので、その素質のありようは意識のいだく関心のうちに表明されているからである。(4)
つまり、素質は、関心の対象としてはじめから現われているというわけです。ただ、それは行為においてであり、それが意識されるのは行為に対する反省によるのでなければならないでしょう。反省は、すでに行為ではないので、反省によって導き入れられるのは行為と行為についての思考との分裂です。そこで、この分裂を乗り越える道が探し求められることになります。どのようにすれば、行為と反省的思考との統一が図られるでしょうか。ヘーゲルの答えは、行為の次元では、初めに戻り、しかも同時に初めを反省的思考していることです。そこでは、過去の初め(過去の自己)に後からかかわりながら、現在の初め(現在の自己)を見ることになるからです。現在の自己を出て、過去の自己へと向かいつつ振り返り、そこに現在の自己を見ることができるようになるということです。それというのも、行為の次元――言い換えると、存在の次元――では、現在の自己は、過去の自己を形式的に反復しているからです。ヘーゲルはこれを「真理」と呼んでいます。
こうして再建される統一、いいかえれば、外に出ていきながら自分をふりかえるという動きこそが――最初にあった直接の統一とはちがう、この第二の統一こそが、真理なのだ。(5)
ヘーゲルの「弁証法」とは、「第一の統一」から「第二の統一」へと生成する運動の形式にほかなりません。「第一の統一」とはいわば自然的な関心のもつ統一で、それは反省との間で分裂しているわけですが、第二の統一は、最初の統一と反省との分裂を乗り越えた統一だということです。こうした生成の結果としての在り方にヘーゲルは「哲学のはじまり」を見ています。
絶対的に自分の外で出ていきながら純粋な自己を認識するという、このエーテル(活動の場)そのものが。学問のおおもとであり、知の一般型である。哲学のはじまりは、意識がこの場に身を置くことを前提条件とする。しかし、この場は、それが生成してくる運動を通じてはじめて、透明な場として完成する。(6)
ここが生成の到達点であり、かつ哲学がはじまる点であるわけです。しかし、そうした弁証法の運動の源にあるのは、先に見たように、「悪循環」であり、そのなかに時間的パラドクスもまた潜在しています。その解決を断念し、経験へと赴くことで、経験の中から弁証法は取り出されるわけです。つまり、弁証法は、現象学的に演繹されるのです。
現象学的に取り出された弁証法は、その後、人間の意識の運動から切り離されて、人間(意識)から独立した概念の運動形式として論理学において扱われます。運動するためには概念は主体でなければならないわけですが、このように主体化された概念が「神」とみなされます。論理学はこうして形而上学化されますが、それはともかく、ヘーゲルの哲学体系は、論理学から始められ、自然哲学と精神哲学を包括する『エンチュクロペディ』として形成されることになります。現象学は、結果から見るなら、学以前のいわば準備的な探究であったということになります。(7)
弁証法は初めから出て、初めに戻ってゆく円環運動の形式ですが、それが『エンチュクロペディ』では、体系全体を貫く方法として用いられます。
弁証法は、上に見たように、関心の運動から導きだされていますが、「関心」という概念に関しては、カントが『判断力批判』のなかで次のように定義しています。
関心とは、私たちがある対象の現存の表象と結合するところの適意のことである。(8)
「適意」とは意に適っていることですから、これは目の前の対象を快く思うことです。カントの場合は、この概念は理論と実践を結合する概念と考えられていました。というのも、カントの理論領域(『純粋理性批判』)は、対象にかかわることと自己にかかわることを分離していて、感性論はもっぱら対象にかかわるもの(感覚)だけを扱っていました。それに対して、実践領域(『実践理性批判』)では、もっぱら自己にかかわること(感情)に発すること(欲求能力)が取り上げられているからです。ですから、対象にかかわり、かつ自己にかかわるもの(関心)が、理論領域と実践領域を結合するものとみなされたのです。ですが、これは転倒していて、本来は関心が先にあって、それが理論と実践とに分離されたというべきものです。
ただ、歴史的に見るなら、理論と実践の分離は、近代哲学のはじまりとされるデカルトにおいて、すでに起こっていました。デカルトの哲学は、「懐疑」からはじめられますが、実はデカルトの懐疑は、理論領域に限定されていて、実践領域は除外されていたからです(9)。ということは、実践領域は、既存のものがそのまま受け継がれるということです(10)。この制限を外して、実践領域にまで拡大したのがニーチェでした。「神は死んだ」という言葉がこれを象徴しています。ここではじめて、理論的かつ実践的な概念としての関心という概念が主役になりうる地盤が整ったといえます。ヘーゲルは、上に見てきたように、関心という概念を用いていますが、『精神現象学』は、感覚からはじめて、自己意識、理性へと進んでいます。この点、認識論的ですが、精神では、共同体における個人が主題化されるので、そこからは実践的です。時間的パラドクスが現れるのは、理性段階の最後の部分で、それが精神へのつなぎとなっています。『精神現象学』は、そういう意味で、理論領域と実践領域を結合する一つの試みと捉えることができますが、全体が関心の概念で貫かれているわけではないので、なお外面的な結合を脱しえていない、というべきでしょう。
次回は、フッサールをとりあげます。
(注)
(1) 渡辺二郎訳「哲学者に関する著作のための準備草案」ニーチェ全集第三巻、理想社、p.193
(2) ヘーゲル『精神現象学』長谷川宏訳、作品社p.269
(3) 同上
(4) 同上
(5) 「まえがき」p.013
(6) 同上p.011
(7) 同上
こうした学問ないし知の生成過程を述べるのが「精神現象学」である。p.017
(8) カント『判断力批判』第一篇第一章第二節、原佑訳、理想社版カント全集第八巻p.71
(9) デカルト『省察』一
……私は、そうしたからといって〔懐疑したからといって〕別に何の危険も誤りも起こらないであろうことを知っているし、また、いま私が問題にしているのは、行動にかかわる事がらではなく、もっぱら認識にかかわる事がらだけであるから、どんなに不信をたくましくしても、すぎることはありえないことを、知っているからである。(野田又夫訳、中央公論社、世界の名著27、p.243
(10) デカルト『方法序説』第三部
第一の格率は、私の国の法律と習慣とに服従し、神の恩寵により幼時から教えこまれた宗教をしっかりともちつづけ、(云々)。(同上、p.180)