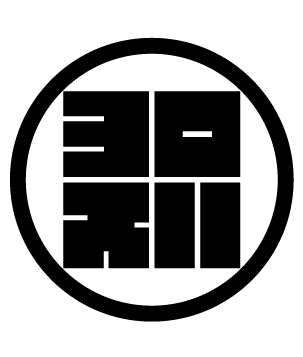国民性と個人
「読めば読むほどドイツ人でなければフィヒテの後期思想の要諦を掴むことができないと感じ、フィヒテの哲学を諦めざるをえなかった」
ずいぶん昔、思い出語りの中でこんなことを言っていた老教授がいた。
若かりし日の教授がどの地点で躓き、そのような結論に達したのか定かではないし、それを推量するほどの見識は持たないが、当時から浅学であった私は、哲学を人間の普遍性を検討する学問だと素朴に考えていたため、研究対象についてわかりえないと考えることが奇異に感じられたのだろう。わかりえないならば普遍性を抽出することはかなわないし、特定の人間にしかわかりえないものであるならば普遍ではない、と。つまり私は何らかのトレーニングを積めば普遍的なものを理解することができ、世界を読むための手掛かりが得られる実用的な学問として哲学をとらえていた。そんなこともあって10年以上経った今でもなんとなく印象として心に残り、時折思い出す。
後期のフィヒテは、当時流行したロマン主義者との交流などの影響もあり、民族的、宗教的傾向を深めていったとされる。前期の代表作『知識学』で根本に据えられた自我という立脚点も、神=絶対者へと移っていった。
この時期のフィヒテで最も有名な著作が『ドイツ国民に告ぐ』である。1806年からはじまるナポレオン軍の占拠下のプロイセンにおいて、首都ベルリンの学士院において行われた連続公演をまとめたものだ。そこで彼はドイツ国民の優秀さ、それをさらに向上するための祖国愛と道徳教育による教育制度の改革の必要性を説いた。
他国によって支配された国家は、イデオロギーのイニシアチブを明け渡さなくてはならなくなる。そうなれば被支配側になった元国家側の人間は、その国のイデオロギー勢力としてはマイノリティとして扱われるようになるだろう。マジョリティはアイデンティティを持たないと誰かが書いていた。国のアイデンティティは外圧によって顕わになると考えれば、フィヒテが行おうとしたことは侵略されつつあるドイツ国民とは何であり、いかにあるべきかを説くことで抑圧される側としてのマイノリティとしてのドイツ国民の立場を明確にし、占拠者が行う同化政策に抗えるよう、エンパワメントしようとしたということであろう。
『ドイツ国民に告ぐ』の文中には”精神性の自由による無限の形成を欲する者は、どこで生まれ、どんな国語を話そうとも、我々の種族であり、我々に属しており、我々に加わることでしょう。”というフランス人権宣言にも似た、広く開かれた国民性解釈の一説がある反面、フィヒテ自身はユダヤ人に対しては排斥的な言辞を厭わず、公民としての権利を与えることさえ拒むような言説をすら残している。
フィヒテのいう”ドイツ国民性”の中にこのような複雑さが入り込んでおり、それがフィヒテの思想を理解するための鍵となっているならば、その国民性を有していない者にとってうまく理解しきることができないという考えを、想像してみることはできる。それは、”それ”と”そうでないもの”を分ける作業であり、”そうでないもの”から”それ”を守るためのものとして機能し、”そうでないもの”に区分けされた人間からのアプローチを本質的に拒むようにできているためだ。
このような排他性は侵略される側において機能したことは想像に難くないが、”ドイツ国民”がマジョリティとしてドイツを治めるようになって以降も、単一の国民という考え方は為政者の意図と絡み合いながら度々首をもたげ、自らを守る武器が外側に反転することになっていった。国家概念の形成期におけるフィヒテの論と、全体主義を比較することはそれほど単純なことではないが、ナショナリズムのひとつの展開として記憶しておくことは必要だろう。フィヒテの考える”ドイツ国民”という概念には時代に対応するための動的な感性が多分に含まれている。そして動的なものとは、火事で煙の充満した部屋から逃れるために窓を破る金属バットのようなもので、平時に携え振り回すものではないのではなかろうか。
他国からの侵略というイシューにおいて、それに抵抗するためにフィヒテの理論に感化され、団結した人間がいたとすればそれは、これまでひとつのまとまりとして認識されたことのない、有象無象の一群であったであろう。ベネディクトアンダーソンの『想像の共同体』によれば、国民という概念もまた近代によって生み出されたものであり、自然にそこにあるのではなく、どんなに古そ うにみえる国民であっても、歴史的に人工的につくられたものであるとのことだ。しかし、国民という概念が生み出され、主権意識の高まりによって国家のあり様を考えることに人生を投じる=フィヒテの言う国家への個人の没入がすべからく起こったとは考え難い。国家の臣民と国民がイコールになるには、強力なインセンティブが必要になる。そしてそのような状況があったとしても、危機が去れば、国家と個人の距離は動いてゆく。国家を単一のナラティブでまとめようとしても、地域や人間が本質的に同一でありえないことから、どこかに綻びが生じざるを得ない。国家性のナラティブのイメージをぼんやりと把握しつつも、わたし達の感覚はマジョリティと、マイノリティの間を動いているため、そのすべてに同化し、真に受けつづけることには、実感としての困難を感じるだろう。
上手にひとつのナラティブで説明できなくなろうと、国という機能は働いており、あちこちに国の独自性を主張するようなファーが漂っている。そらが自身が国民であることを再帰的に理解することを促すわけだが、その一方で、国の文化政策によってつくられる文化イメージが余所行きのものとして感じられたりすることや、国民的行事が必ずしもそれが生活の最優先にならない場合に、その距離は現れてくる。
先日の国葬儀の日程は旅行中だったためほとんどそのことに触れる機会がなかっのだが、唯一旅先の土産物屋を物色している際に店にあるテレビから偶然流れているのを垣間見た。店主は暑さでぼんやりしていたのか見るともなく外を眺め、手持無沙汰を慰めるように新聞の端を捻っていた。放送の音はなんとなく耳にしながらも意識の中心は必ずもそこにないような感じの店主を眺め、個人的にこれが国と人との距離だなと感じたのだが、どうか。
国民という意識と個人という意識の間には直結する回路があるのではなく、緩やかに繋がりながらも、状況や関心といったインスタントな感覚にすら左右され、一貫性が揺らぐことがある。そうした矛盾や断片は、理路を抽出するときにはオミットされる。そう考えればフィヒテに限らずとも、人の抱えるそのような揺らぎの折り重なりを、まるごと理解しようとすることの途方も無さとはいかほどのものだろうかと呆然としてしまう。
n.shukutani