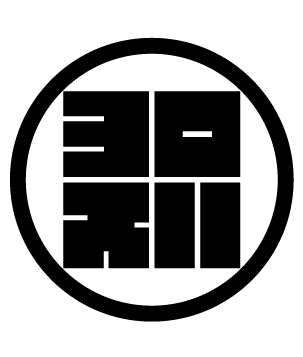哲学への冒険の旅 9
哲学への冒険の旅 9
9 歴史の中の「時間的パラドクス」五――ハイデガー3
理論化と隔生化
今回からは予告通り、ハイデガーが行った認識論から存在論への転換についてお話します。
この転換も、すでにお話ししたように、1919年の緊急講義のなかで行われています。その際、カギとなる概念は「隔生化Entlebung」です。この概念は前回も使いましたが、その時の使い方はハイデガー自身の使い方ではありません。その時は、ハイデガーの概念をハイデガー自身の存在論の起源を明らかにするために、私がブーメランさせたのでした。その際問題の焦点となっていたのは、体験と、体験につながる普遍的理論との関係にありました。体験のうちに理論的な問題を見てとるためには、「直接的な体験にしがみついていてはならないのであって、批判的な立脚点にまで自分を高め、自分の現状を越える自由な可能性を持たなくてはならない。つまり、高度な文化の理性を持たなくてはならないのである」(27)とハイデガーは言っていますが、これは、何であれ体験の理論化において必然的に求められることであります。ですから、体験から理論が形成されたのであれば、ハイデガーの存在論の形成においてもみられるはずです。
前回やったことは、まだ着手点にすぎませんでしたが、方法論的に見返してみれば、「隔生化」という概念をハイデガー存在論の起源の場面に適用させることであったわけで、その意味でハイデガー自身の使い方ではなかったのです。もしハイデガー自身がそういう使い方を行うとすれば、彼が形成した存在論は、自己言及性を方法として自覚的に用いる存在論でなければならなかったでしょう。
また、こうした使い方を可能にするのは、「理論的なもの」を、超領域的に、つまり認識論であれ、存在論であれ、それにかかわりなく、体験や経験から出発する「理論的なもの」一般と解する場合です。ですが、この時期のハイデガー自身にとっては、「理論的なもの」とは特定の理論、すなわち認識論を意味していました(28)。ハイデガーは、「理論的なものの優位」について批判的に論じていますが、その際の「理論的なもの」とは、認識理論的なものなのです。たとえば、認識論における所与性として「感覚データ」といったものについて、環世界的な体験を破壊するものだと言っている文章があります。少し長いですが引用します。
感覚契機としての「茶色の」というこのデータを、私は講壇と同じように体験しているのか。茶色そのもののうちに、しかもデータとしてとらえられたそれのうちに、世界が立ち現われるか。このように把握していることのうちでは、私の歴史的な自我が共鳴を行っているか。あきらかにそうではない。そして、直接的に与えられているとはなんのことか。確かに私は、感覚を外界の原因を解明するように後から解明する必要はない。感覚はそれ自体として現にある。しかしそれは、私が環世界的なものを破壊し、それをぬぐい去り、捨象し、私の歴史的な自我を遮断し、理論を立てることによってそうなのである。つまり、それが第一義的なのは、理論的な態度においてそうなのである。感覚のこの第一義的な性格が見られるのは、私がすでに理論を立てているから、すでに理論的な態度にあるからである。しかも理論的な態度それ自体は、その意味からして、環世界的体験を破壊することとしてのみ可能な態度なのだ。(29)
ここでは「茶色」と「講壇」が比較されていますが、「講壇」というのは、この講義が行われた教室にある「講壇」のことで、「茶色」というのは、その講壇の色のことです。「講壇」という言葉からは、それが置かれている教室、その教室にいる講義する人と講義を聴く人など、周りの世界が連想されます。それが環世界的体験です。私たちが日々生活している現実はそういうものです。ですが、認識論は、「茶色」を感覚データとして、そこから始めます。そのため、環世界的体験は壊され、抽象的な感覚的要素だけが取り出されるというわけです。
ここにはっきり現われているように、このときハイデガーにとって「理論的なもの」は認識理論なのです。実際、本来「理論的なもの」一般の本質特徴ともいえる論理的な対概念――関数と代入項――は、あたかも認識論にだけ使用されるかのようにさえ言っています。
感覚は単に、方程式の未知数Xなのであって、それが意味を獲得するのは理論的客観化においてであり、理論的客観化を通じてであるにすぎない。(30)
感覚データだけでなく、実在性の概念も、ハイデガーにとっては、認識論的な意味を与えられています。前回お話ししましたが、この稿では、「実在するもの」とは、何らかの類的な属性をもつものを指すとしていますが、ハイデガーの場合、実在性は世界から切り離された事物性を指しています。やはり長くなりますが、重要な個所なので引いておきます。
事物性は、環世界的な事柄から蒸留して取り出されたきわめて独自な領域である。「世界としてある」ということが、この領域にあってはすでに消し去られている。事物は、たんにまだそれとしてそこにある。すなわちそれは実在的であり、それは実在している。実在性はしたがって、環世界的な性格づけではない。むしろ事物性の本質に見られる、特殊理論的な性格づけである。意義付帯的なものが脱‐意義化されて、この「実在的である」という残骸になってしまっている。環世界を‐生きるということが、隔‐生されて、「実在的なものをそれとして認識する」という残骸になってしまっている。歴史的な自我が歴史をはぎ取られて、事物性の相関物としての特殊な自我‐性という残骸になってしまっている。(31)
要するに、ハイデガーが言っているのは、認識論における主観‐客観相関は、世界をもたな
い孤立した主観と世界を消し去られた事物としての客観から成り立っている、ということで
す。この批判には、相応の妥当性があります。たしかに認識論では、私たちが日々生きてい
る現実を体験に則して捉えることはできません。その意味で、生から隔たっています。です
が、前回見たように、ハイデガーが存在論を形成する態度にも隔生化が見られます。そして
彼の存在論には、論理的な操作も見られます。たとえば、『存在と時間』のなかで認識論を
批判している箇所(32)では、認識論における「無世界な主観」にたいして、「世界内存在」
が対置されています。「世界内存在」は一般概念であって、決して個別的な存在を表わすも
のではありません。そして、「私」や「君」の存在は、世界内存在という方程式の未知数Xを
充実化するものです。そこにも、一般的なもの(普遍的なもの)とそれによって意味づけさ
れる特定のものとの関係が存在しています。この論理的な関係自体は、認識論にだけ見られ
るものではなく、ハイデガーの存在論においてもみられるわけです。ただハイデガーは、こ
の論理的な区別を論理学的表現とは別の形で表わしています。たとえば「概念的なもの」は
その場合「形式的なもの」と呼ばれます。ですが、それは、名目的な論理的関係を拒否しな
がら、実質的な論理的関係を認めているということです。彼が論理学の表現を拒否するの
は、論理学が認識論と結び付けられて理解されているためですが、論理学における関数‐代
入項の対概念は、そもそも実質的な論理的関係に基づくものです。ですから、存在論におい
ても、それは用いられ得るものですが、ハイデガーは、それを頑なに拒否しています。
話が逸れたので、「隔生化」に戻りますが、先にも述べたように、体験や経験から出発する理論――広い意味で現象学的な理論――では、「隔生化」が問題となります。認識論だけではなく、環世界的体験から出発する理論においても、すでに見たように、隔生化があります。ハイデガー自身、そう言っています。
しかし理論化そのものが絶対化され、それが「生」に発することが理解されていなければ、究極的な問題がみいだされないままである。隔‐生の過程としての客観化の増大過程。そして最も困難な問題のひとつは、環世界体験から最初の客観化へ至る境界の乗り越えの問題である。なぜならば、この問題は、環世界体験とその奥に隠された問題を理解することによってのみ解決可能だからである。理論的なもの一般という問題もそのようにしてのみ解決される。(33)
ここで言われていること、とりわけ「環世界体験から最初の客観化へ至る境界の乗り越えの問題」――これこそ、前回取り上げた隔生化の問題でありました。それはそれとして、上の引用文の最初の文章に注目すべきことが言われています。「理論化そのものが絶対化されて」というのは認識論のことを指していますが、その後で理論化が「生に発することが理解されていなければ」と続いています。これが、次回に見るように、認識論からの転換をもたらす核となるものです。なお、この引用文は、転換の後で書かれているものなので、転換に先立つものではないのですが、転換の経緯を知る上では有効なものなので使わせてもらいました。
今回はまだ認識論から存在論への転換の核心には至っていないので、さらに次回に続けます。
(注)
(27) ID.§16,邦訳p.88
(28) 「理論的なもの一般」の視点がハイデガーにはなかったということではありません。この講義の終わりの方(第二部第三章§20,b「隔生の諸段階の性格づけ」)では、隔生化が理論化一般の問題として扱われています。(32)参照
(29) ID.§17,邦訳p.93
(30) ID.§17,邦訳p.94
(31) ID.§17,邦訳p.97
(32) SZ.第43節「現存在、世界性、実在性」
(33) ID.§17,邦訳p.98
・・・