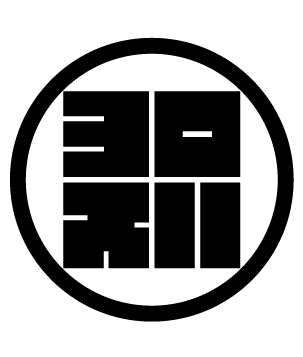哲学への冒険の旅 8
哲学への冒険の旅 8
8 歴史の中の「時間的パラドクス」五――ハイデガー2
1 存在と実在
前回は、事実的な存在の〈現〉を「絶望」と捉えました。しかし『存在と時間』は、その痕跡は見られても(10)、前景的には、絶望が主題になっているわけではなく、ましてや、たとえば、キルケゴールが、『死に至る病』で行っているように、絶望を主題化するだけでなく、かつそこからの脱出の途を(キリスト教的にではありましたが)説くというものでもありませんでした。それどころか、現存在は、投げ込まれた絶望の存在を引き受ける存在者として考えられているのです。それは、事実性のうちに可能性があらかじめぞくしている、という『存在と時間』のテーゼうちに現われています(11)。事実性のうちにあらかじめ可能性がぞくしているのだとすれば、可能性を引き受けることは、事実性を引き受けなければなしえないこととなります。この次第をハイデガーの体験のレベルに引き戻して考えてみるなら、絶望状態から脱出するのではなく、そこにとどまって、そこに含まれている可能性に自己を投ずるということになります。ですが、いったい絶望状態において現前する事実的な存在にそもそもどんな可能性がぞくしているのでしょうか。それがまず問題です。
それを解きあかすカギが『哲学の理念と世界観問題』§13「或ることがあるかという問いの体験)のb)「問うふるまい。『ある』の意味の多様性」のうちにあります。
数がある。三角形がある。レンブラントの絵画がある。U-ボートがある。私はたとえば、今日はまだ雨が残っている、明日は子牛のローストがあるという。さまざまな「ある」であり、そのつど異なった意味をもっている。しかしそれにもかかわらず、どの意味にもあてはまる同一の意味契機がある。完全に色を抜かれた、いわば特定の意味を抜きさった、たんなる「ある」にしても、まさしくそれが単純であるゆえに、多様な謎を秘めている。「ある」ということの意味にとっては有意味なモチーフはどこにあるか。(12)
要点は、「ある」はさまざまな意味でいわれるが、「どの意味にもあてはまる同一の意味契機」があり、それはなにかというと、「特定の色を抜かれた、いわば特定の意味を抜きさった、たんなる『ある』である」、という点にあります。「特定の意味を抜きさった、たんある『ある』」とは、なんでしょう。 ここで思い出されるのは、絶望状態において自己現前する自己の事実的な存在は、まさにそういう性格をもっていた、ということです。それは「即物的な無」という言葉が表わしていたものです。このつながりは何を意味するでしょうか。それは、絶望体験において見いだされる意味を抜かれた単なるあることのうちには、或る存在論的な意味の可能性が含まれている、ということのほかにはないでしょう。「どの意味にもあてはまる同一の意味契機」という句がそのことを表わしています。そして、さらにいうと、それが一つの謎として問いかけの対象になっているということです。つまり、それは、存在論的な探究の可能性が、それゆえまた、ハイデガー自身にとっては、存在論者としての存在可能性が、絶望状態において自己現前する自己の事実的な存在のうちに含まれているということです。この可能性は、もはや事実的な存在それ自体ではなく、何ものかへの途、すなわち或る意味をもった存在への途へと続くものではありますが、だからといって決して絶望状態を脱する途ではありません。それによって根源学のパラドクスが解決されたことにはならないからです。あくまでも絶望状態にあるなかでの存在論および存在論者の、存在可能性です。
事実的な存在が存在論の主題として問われることになると、ハイデガー自身の体験からは隔てられて(13)、体験からは独立した意味をもち始めます。「どの意味にもあてはまる同一の意味契機」とは、存在論的にはなにを意味することになるでしょうか。それは、あらゆるものに共通する規定としての「ある」ということであり、また、すべての存在するものを規定する普遍性をもつ、ということを意味します。この普遍性は、特定の類種に属するものに共通する普遍性とは異なります。ですから、普遍性には二つの普遍性があるわけです。ひとつは、類種的な普遍性、もう一つは類種的な区別を超えて、あらゆる領域にぞくするものに共通の普遍性です。
二つの普遍性については、『存在と時間』のなかにも記述があります。
哲学の根本問題である存在は、存在者がぞくするいかなる類でもないが、存在はそれでもなおそれぞれの存在者にかかわっている。存在の「一般性」は類よりも高いところにもとめられなければならない。存在と存在構造は、あらゆる存在者と、存在者にぞくする、存在するものと規定されたいっさいの可能なあり方を超えている。存在とは端的にtranscendens(超越概念)なのである。(14)
「超越概念」というと、なんか難しそうな感じですが、そう難しいものでもありません。あらゆるものは、何らかの領域に属し、何らかの属性をもっています。たとえば、猫、木、石、人、等々に属するものは、それぞれの属する領域に共通な属性をもっています。それが類(種)と呼ばれる普遍性です。「超越」というのは、ここではただ、あらゆる領域的属性を超える、という意味です。「存在」という概念は、或るものが「何であるか」、どの領域に属するのか、にいっさいかかわることなく、あらゆる「或るもの」に共通しており、しかもそれらを規定する概念です。ですから、猫という類に属する個的なものも、木という類に属する個的なものも「存在する」といえますし、それらは、この類を超えた共通の規定によって規定されえます。こうした類的な一般性(普遍性)とは異なる一般性(普遍性)、類的普遍性を超えた普遍性、それをハイデガーは「超越概念」と呼んでいるわけです。
「超越概念transcendens」という語は中世哲学の術語です。ハイデガーは、すでに1915年の教授資格請求論文として『ドゥンス・スコトゥスの範疇論と意義論』(15)を発表していることが示しているように、中世哲学の研究を行っていました。ですから、超越概念についての知識はもっていたわけで、それが絶望体験において現となる「事実性としての存在」と結び付いたと推察されます。ただ、ハイデガー自身はそのようには捉えておらず、あくまで理論以前的な体験が隔生化されたものとして捉えています。つまり、外からの情報は関与してせずに理論化されているという方向で捉えています。ですが、状況から見て、そこには知の記憶と体験された内実との出会いがあったのではないかとも考えられます。実際、そういうこと、つまり、言葉としては知っていて、事象として客観的に理解していても、自分のこととして、自分に結びつけては理解していないことが、関連する体験を経てはじめて、自分にかかわる内実をもつものとして、現実的に生き生きと理解されるということはよくあることです。これはいわば知識と体験との出会いです。この点については、なお詰めた研究が必要ですが、ここでは作業仮説として提示しておきます。
2 『存在と時間』における存在と実在
これまでは「存在」に焦点を当ててきましたが、反対に、類的な普遍性をもつものについてはどう考えられているでしょうか。ハイデガーは、こちらについては積極的には論じていないので、はじめに私自身の考えを述べますと、或るものがなんらかの領域に属し、類種的な属性をもつものであるかぎりで、これは「実在するもの」と呼ばれえます。すべて実在するものは、何であれ、何らかの類種にぞくするものだからです。「実在するもの」自身普遍概念ですが、この概念は、類的普遍性をもつものへの存在論的な名です。ですから、「実在するもの」という概念は、何らかの具体的な対象――それぞれの類に属する具体的な対象――をもちえます。
それに対して、「存在、存在するもの」という普遍概念(超越概念)には、そうした個的な対象はなく、それが関係するのは、「実在するもの」という類的な普遍性であり、実在するものを、「存在」という共通性において規定するものです。「存在」という概念には、それへと立ち帰る具体的な対象はないのです。たしかに、猫は存在する、木は存在するということはできますが、その場合でも、実質的に存在しているのは実在者であって、存在者なるものではありません(16)。
ですが、この区別はハイデガー存在論においては、明確になされていないばかりか、むしろ混同されています。たとえば、ハイデガー存在論の有名なテーゼのひとつである「存在と存在者の存在論的差異」というのがありますが、このテーゼには〈存在するもの〉と〈実在するもの〉の混同が含まれています。このことは、存在と存在者の区別が最初に議論されている講義『古代哲学の根本諸概念』(1926年夏学期)の序論第四節を見ればはっきりわかります。
「有」、この単語では、なにも表象されえない。有るものならよい。だが、有は? じっさい、普通の悟性や普通の経験が理解し探究するのは有るものだけである。けれども、有るものに有を見、有を把握し、有るものと有を区別するのは、区別を業とする学問、哲学の使命である。哲学のテーマは有である。有るものなどではない。
実証科学、それは有るものについての学問である。有るものとは、自然に係わる経験や見聞のために、前に置かれているものである。(17)
哲学は有(存在)についての学であり、実証科学は有るもの(存在者)についての学だといわれています。ですが、実証科学が主題化しうるものは、何らかの類種的な普遍性によって規定されているものであって、決してたんなる「存在するもの」ではありません。ですから、この場合、区別されるべきものは、存在と実在であり、また存在者と実在者なのです。この二つの間には、あきらかに概念の抽象度の差異とそれに基づく関係があります。カント的に言うなら、「実在、実在者」は経験対象に関係しうる「悟性」概念ですが、「存在、存在者」は悟性概念を規定する「理性」概念だということになります。
この視点から見るなら、ハイデガーが行っている認識論から存在論への転換についても別の見方ができます。つまり、この転換の基底には、類的普遍性の概念から超領域的な普遍性の概念への存在論体系の内部における推移が見られるのです。というのも、認識論が前提としているのは何らかの類種的普遍性に属しているものであって、類種的な規定が空虚化された「単なる存在するもの」ではないからです。この視点が大事なのは、これを把握していないと、認識論の批判によって、それが主題化している類種的普遍性に属しているもの(実在するもの)もまた、不当に貶められてしまうことになるからです。実際にそのことが『存在と時間』で見られます(18)。ここでいまくわしく分析する余裕はありませんが、その一端は上に見た「存在と存在者の存在論的差異」テーゼに示されているとおりです。ハイデガー存在論では、実在(者)と存在(者)とは混同されているというか、実在(者)は存在(者)のうちにのみ込まれてしまっているという状態になっているのです。ですから、逆に、「現存在」が「人間」として表現される箇所が『存在と時間』にはあります。
諸学は、人間の態度として、この存在者(人間)の存在のしかたをふくんでいる。この存在者を私たちは術語的に現存在ととらえるのである。(19)
あたかものみ込んだものを、今度は吐き出すかのようです。言うまでもありませんが、「人間」は、類的に普遍的な概念です。ですから、それは「実在するもの」に属しているわけで、実際、人間の実在性は身体にあります。他方、「現存在」は実在するものを指す概念ではないと、ハイデガーが明確に言っています。
この存在者をしるしづけるのに用いられる「現存在」という名称によって表現されているのは、机、家や木の場合のように、その存在者が〈なんであるか〉ではない、表現されているのは存在にほかならない。(20)
つまり、「現存在」は「存在するもの」であって、「実在するもの」ではないのです。ですから、「現存在」と呼ばれる存在者は身体をもちません。実際、『存在と時間』では、身体はいっさい論じられていません。つまり「現存在」はそもそも物的なものではないのです。それどころか、逆に、主観や自我といった概念の物化に抗して、物化されえないものの存在を問うことから「現存在」の概念は生まれています。たとえば、主観という概念は、歴史的には、アリストテレスの「基体」に由来するものですが、この概念は、『自然学』のなかの概念であり、つまりは「実在するもの」に関する概念です。ですから、物化されえないものについても、そのまま使われれば、「心的実体」や「意識の物化」を引き起こすことになります(21)。そうならないためには、物化されえないもの――「主観、こころ、意識、精神、人格といったもの」(22)――については、それとは異なる別の存在論的な問いが提示されねばならないわけです。そのため、『存在と時間』では、主観、意識、精神といった術語は用いられず、代わりに「現存在」という呼称が選ばれているわけです。
ですが、上の二つの引用文は、あきらかに矛盾しています。一方では、人間という「実在するもの」が「現存在」と呼ばれ、他方では、「現存在」は「存在するもの」であって、「実在するもの」ではない、と言われているからです。この矛盾は、内容的にみれば、次元の異なるものを混同していることから生まれてきたものだといえます。
そのことは、ハイデガーが自分の問題設定を、デカルトの有名な命題との関係で説明している箇所にも現われています。
デカルトには、近代の哲学的な問いが出発する基盤としてのcogito sum〔私は考える、私は存在する〕を――或る限界内で――たしかに探究していた。デカルトは、その反面、sum〔私は存在する〕を――それがcogito〔私は考える〕とおなじように根源的に着手点に置かれているのもかかわらず、――まったく究明しないままですませている。実存論的分析論は、sumの存在への存在論的な問いを設定する。この存在が規定されることではじめて、cogitationes〔諸思考作用〕が有する存在のしかたもつかまれるようになるのである。(23)
cogito sumのsumは、考える私の存在です。デカルトは、考える私、すなわち自我については究明しているが、その存在、すなわち考える私の存在、自我の存在については究明していないと、言っているわけです。「考える私」の存在、「cogitationesが有する存在の仕方」というのは、人間の存在、つまり存在論的には特定の「実在するもの」を指しています。とすれば、「sumの存在への存在論的な問い」とは「実在するもの」の存在、すなわち「実在」を意味するのでしょうか。それとも、「実在」を規定するもの、すなわち「存在」を意味するのでしょうか。その点があいまいです。「自我」の究明から「自我の存在」の究明への移行は、たしかに「認識」の理論から(実在を含めた)「存在」の理論への移行ですが、存在の理論の内部には、先ほど指摘したような、類的普遍性を探究する「実在するもの」の存在論と、超領域的な普遍性を探究する「存在するもの」の存在論との区別が含まれていますが、これが明確に規定されていません。ですから、単に、認識論から存在論へと移行するととらえるだけでは、この存在論の体系の内部における区別を見過ごさせることになります。
今回は、根源学の理念のもつ難問の解決を断念した後で、ハイデガーが存在論の可能性に向かったことを、彼の体験において見てきました。その経緯は、上述したような過程を経て立ちあがったハイデガー自身の在り方が、まさに「現存在」の原形となっているということを示しています。「現存在とは、自分の存在においてこの存在へと理解しつつかかわっている存在者」と定義されていますが(8)、この定義は、ハイデガー自身の体験、すなわち、絶望の底で開示される自分の事実的存在に存在論的に理解しつつかかわるという体験に基づいているといえます(25)。『現象学の根本諸問題」から前回引用した文章(1)が示しているように、存在論を可能にするものはどのような存在者なのか、という問いが、根源学の不可能性に挫折した哲学者が向かった先であったのですが、この問いは、『存在と時間』という存在論の著作を制作しているハイデガーという一個の現存在へと「跳ね返ってくる」問いでもあるわけです。しかし、この問いは、もはやすでに「おのれ自身を根拠づける学」の問いではありません。ですが、この問いが後に『存在と時間』において、「基礎的存在論」と呼ばれることになるものです(26)。この呼称については後に述べますが、根源学の理念そのものを変容させるものであります。
話が『存在と時間』の時期にまで及んでしまったので離れてしまいましたが、この稿では、1919年の戦時緊急講義の段階が基本的には主題化されていました。その段階では認識論から存在論への転換が行われる以前の段階であったのですから、それがどのようにして行われたのか、という問題が残されています。次回から、この問題を扱います。(2025.4.26)
(注)
(10) たとえば、SZ.第32節には次のような句があります。
――たとえ根拠が没意味性の深淵であろうと――(2-p.227f)
(11) SZ.第31節
現存在の事実性には、存在可能が本質からしてぞくしている……。(2-p.200f)
ハイデガーは、このような、事実性に属している可能性を、これを「被投的な可能性」と呼んでいます。(2-p.192)
(12) ID.p.74
(13) 「隔生Entleben」という概念をハイデガーは使っています。この概念は、両義的で、認識論に対しては批判的に用いられますが、理論化においては必然的な過程であるので、存在論を形成するという場合にも起こります。(ID.§20,b参照)
(14) SZ第7節,1-213f
(15) 邦訳全集第1巻「初期論文集」所収
(16) 中世のイスラム哲学の照明学派と呼ばれる一派の創始者であるスフラワルディーが、同じようなことを言っていたことを、井筒俊彦が『イスラム哲学の原像』(岩波新書1980年)で報告しています。
スフラワルディーはこう申します。多くの哲学者たちは存在、存在と、あたかも存在なるものわれわれの意識の外に客観的に実在するかのごとく語っているが、実は「存在」という言葉によって指示される特定のものないしことが意識の外にあるわけではない。概念としての存在はたしかにわれわれの頭の中に実在する。論理的思惟にとっては、それはきわめて有効な道具である。だが、われわれの頭の外、いわゆる外界にはそれに対応するものはない。外界に実在するのは「本質」だけである。(p.149)
(17) 邦訳全集第22巻 p.9f
(18) SZ.第43節「現存在、世界性、および実在性」参照
(19) SZ.第4節 1-p.111
(20) SZ.第9節 1-p.225
(21) SZ.第83節 4-p.461
古代の存在論は「事物概念」によって仕事をしており、そこには「意識を物化する」危険がある。
(22) SZ.第10節 1-p.241
(23) SZ.第10節 1-p.240f
(24) SZ.第83節 4-p.461
(25) ID.§20,c.p.125
さてここで、規定性が一切の理論的記述に先立ってあるという、謎めいた事態の解明が行われる。理論的には、私自身が体験から来ている。
(26) SZ第4節,1-p.118
かくて基礎的存在論は、現存在の実存論的分析論のうちにもとめられなければならない。他のすべての存在論は、その基礎的存在論からはじめて発出しうるのだ。名称こそ変わっていますが、実質的には、基礎的存在論が諸学の根源と言われています。