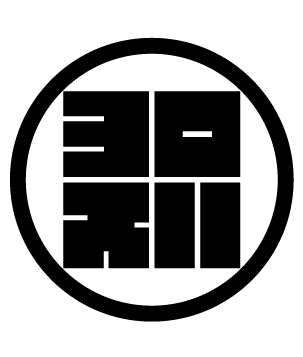哲学への冒険の旅 6
哲学への冒険の旅 6
6 歴史の中の「時間的パラドクス」その4 フッサール
ヘーゲルにおける「時間的パラドクス」は、人間の意識にかかわっていましたが、フッサールでは学問論の在り方にかかわるものになります。この変化は存在論的に重要な意味をもっています。というのは、学問論は、人間の知的活動の産物ではありますが、しかし制作されれば、人間からは独立したものとして実在することになるからです。フッサールも、「学問は著述という形でのみ独自に現存している」(1)と言っています。人間とその知的制作物との関係という問題は、存在論の問題圏域にあるものですが、時間的パラドクスをこの関係に絡ませてみると、哲学史の流れに関して興味深いことがわかります。
ヘーゲルは、前回見たように、時間的パラドクスを人の素質の先行的な把握、という課題に見ていましたが、論理学ではみていませんでした。論理学は、人間の知的活動から独立した概念の運動を記述するものでした。ですから、大きくいって、ヘーゲルには、現象学から論理学へという流れが見られます。これに対して、フッサールは、これから見てゆくところですが、時間的パラドクスを論理学において見いだし、その解決を回避して、現象学へと向かっているのです。つまり、ヘーゲルとは反対に、論理学から現象学へと流れてゆくのです。
この場面に限定すれば、現象学は人間の知的活動を扱い、論理学は、その制作物でありながら、人間からは独立した存在者を扱います。その視点でいうなら、現象学→論理学は、存在論的には、人間→人間の外のもの(人間を超えたもの)、という流れです。これに対して、論理学→現象学は、人間の外のもの→人間、という流れです。後に見ますが、ハイデガーの『存在と時間』は、この流れをフッサールと共有しています。そして、これは先走ってしまいますが、「哲学の冒険への旅」は、現象学→論理学の流れです。その意味では、ヘーゲルにおける哲学の流れを再生させるものとなっていますが、時間的パラドクスは、人間においても、人間の外のものにおいても見いだされ、解決に向かうものとなるので、この点では、ヘーゲル、フッサール、ハイデガーのいずれとも異なっています。ですから、ヘーゲルを再生するといっても、ヘーゲルにもどるわけではないのです。以上を前置きにして、早速フッサールに向かいましょう。
フッサールは、『論理学研究』の第一巻「純粋論理学序説」で、学問論としての論理学の可能性を問うています(2)。そもそも論ですが、学問論とはどういうものかといえば、学問の学問、いいかえれば個別諸科学を超えて、諸学を基礎(根拠)づける学問です。古代では、アリストテレス『形而上学』で言われる第一哲学(存在論)が担ってきたものです。フッサールは、これを論理学として形成することを企てています。内容を度外視すれば、そうした企ては、フィヒテ『全知識学の基礎』やヘーゲル『論理学』があり、そこに近代哲学に固有の課題があったと考えられます。
次に、フッサールは学問論としての論理学を、規範学から捉えています(3)。規範というのは、それだけで存立するものではなく、それを規範とする他のものとの関係の内でのみ存立しうるものです。そして、さらに、規範学が提示する根本規範を目指して特定領域の学問を形成するということになれば、規範学から「学問の技術学」が生まれます――たとえば、ヘーゲル論理学は「弁証法」を方法として技術的に作られているといえます。しかし、論理学が他の学問にとって規範学となり、また技術学となるためには、それが他の学問にとって根本規範となりうる理念を扱う「理論学」が必要になります(4)。フッサールは、そうした理論は、理性に基づく独立したア・プリオリな学であるべきだとしています(5)。それが「純粋論理学」です。 それに対して、規範学・技術学の理論的な土台は、独立しているのではなく、すでに存在する諸学問に編入されるとする「反対派」――たとえば心理学主義派――と対立することになります。
われわれが一方の側に立って、技術学と解されるすべての論理学の基礎にはひとつの固有の理論学が、すなわち《純粋》論理学があると主張するのに対し、反対派は論理学的技術学の中で確認される一切の理論的諸学説はその他の周知の理論的諸学〔たとえば心理学や論理学〕へ編入できると信じている。(6)
まずこの対立の構図を頭に入れておいてください。重要な点は、心理学主義と対立しているという点です。論理学→現象学の流れでいえば、知的活動の制作物から人間の知的活動へとたちもどるという流れですから、心理学の方向へと向かってもいいわけですが、心理学と対立するということは、心理学とは異なる仕方で人間の知的活動に立ち戻るということを示唆しています。
さて、心理学主義派の主張はどういうものかといえば、「学問論の本質的土台を供給する」のはいかなる理論学かという問いに対して、それは心理学にある、と答えます(7)。というのも、論理学が扱う概念、判断、推論、認識、証明などは、すべて「心的な働きや産物」だからである、と。
ところで心理学主義派への反対派にも、純粋論理学を唱える立場とは異なる「通常の反対派」――仮に論理学派としておきます――があります。となると、関係はおおっざぱに言うと、三角関係となり、純粋論理学は、一方で心理学主義派と対立しつつ、他方で論理学派とも関係することになります。もっとも論理学派に対しては、ともに反心理学主義派である点で共通しているので、やや親和的です。
論理学派の主張は、「心理学は思考作用をありのままに(das Denken,wie es ist)考察し、論理学はそれがいかにあるべきか(wie es sein soll)を考察する」(8)というものです。
ここには重要な論点が含まれています。一言でいえば、ここでは存在と価値とが分離されている、という点です。これに対してフッサールは、たとえば「AはBであるべし」といった規範的命題は、「価値評価の関心を度外視すれば」、「BであるAのみがCという諸性質を有する」(9)という理論的命題を含んでいる、と述べています。これは価値評価に転ずる前に、理論的命題のうちに、価値評価へと「方向転換」しうる要素がすでに含まれている、ということを示唆するものです。それが何か? についてはフッサールは何も語っていません。この問題を解決するためには、伝統的な主語+述語の論理学から、実は同時代に勃興していた関数と値の論理学(記号論理学)への転換がなされねばならないのですが、フッサールが依拠していた論理学は、アリストテレス以来の伝統的な論理学であったことが影を落としていると考えられます。
アリストテレスの第二実体は述語であり、第一実体は主語ですが、記号論理学では、第一実体と第二実体は値と関数に置き換えられます。値(value)という表記から見ても明らかなように、論理学の内部に価値評価に転化しうる要素が入っています。フッサールが示唆しているのは、まさに関数/値関係における値のことだと考えられます。値とは、関数に適合する――関数が与える条件を充たす――代入項のことだからです。歴史的なことを付言するなら、フッサールとフレーゲとの間には交わりがあったようです。
話を戻しますと、論理学派の主張は、思考作用をあるがままに考察する理論学(思考の自然学)が、規範学としての論理学の理論的土台である、という心理学主義派の主張に対して、それでは論理学の諸規則は偶然的なものにしか到達しえず、必然的なものにはならない。論理学は、どのように思考するのかというのではなく、いかに正しく思考しうるかに関する諸規則を提示しなければならないと、思考の倫理学を説きます。(10)。
それに対して心理学主義者は答えます。「因果関連の問題を無視できようか。自然的諸関連の研究を抜きにして論理学がいったいどのようにしてイデア的関連を探求できるのであろうか?」(11)と。
ここで「因果的連関の問題」が出てきていることも、やはり存在論的にみて重要です。因果性は、カントにおいても言われていますが、存在者と存在者の関係の仕方を規定する原理ですから、本来存在論的な問題圏域にある問題です。しかも、この原理はカントにおいても存在論的には解決しえない問題であったものです。にもかかわらず、それを使用することが有効であるがゆえに、因果性は、存在者の存在を構成する原理ではないが、存在者と存在者の関係に規則を与える原理(統制的な原理)として容認されていました。思考の自然学には、存在論的な問題に接するところがあるということが、ここに示されています。
それはさておき、「因果関連の問題」は無視できないという心理学主義者に対して、論理学派は、いや因果関連を無視などしていない。むしろ、論理学が目指すこと、すなわち、正しい判断が、どのような知的活動(原因)から生まれる(結果するか)を明らかにすることには、因果関連が明瞭に含まれている、と(12)。
ここで攻守が入れ替わって、論理学派が心理学主義派に攻めこみます。そして、「循環」の問題が現われます。これまで心理学主義派と論理学派と純粋論理学との三つ巴の論争を見てきましたが、ここではじめて「時間的パラドクス」につながる問題が出現します。論理学派から次のような「循環」が持ち出されます。
論理学は心理学にもその他のいかなる学にも依拠できない。なぜならどの学問も論理学の諸規則と調和することによってのみ学問なのであり、これら諸規則の妥当性を既に前提しているからである。したがって論理学をまず第一に心理学を基礎にして建設しようとするのは循環であろう。(13)
論理学を学問論として捉えれば、いかなる学問も学問論としての論理学の諸規則に従ったものでなければならないわけです。その意味で、心理学も、論理学に依拠すべきものです。その視点から見るなら、心理学が論理学の基礎だというのは転倒しています。基礎づけられるべきものが逆に基礎づけるものになるわけですから。しかし、基礎づけられるべきものが、また基礎づけるものになるということは、結局、自分自身を基礎づけるものになる、ということです。そこに「循環」が生まれます。
ここで一言挟みますが、基礎づけられるべきものが基礎づけるものになるということは、「自分自身を基礎づける」という在り方における本来の在り方ではありません。本来のそれは、基礎づけるべきものが基礎づけられるものにもなるという在り方です。ここでこの区別について言及したのは、後で主題化することになるハイデガーの『存在と時間』で起こっていることがまさにこれだからです。
で、攻められた心理学主義派はどうするか? 相手が使った武器を逆手にとって、論理学派に切り返します。そしてそこに出現する循環は、まさに後者――基礎づけるべきものが基礎づけられるものになる――でありました。
反対派〔心理学主義派〕はこう答えるであろう。そのような論証が正当でありえぬことは、そこから論理学一般の不可能性が帰結するであろうことからも既にあきらかである。論理学が学たる以上それ自身も論理学的に処理せざるをえないのであるから、したがって論理学も同じような循環に陥るであろう。つまり論理学が前提している諸規則の的中性を論理学は同時に基礎づけねばならないであろう。(14)
論理学自身も学である以上、論理学は自分自身を論理学的に〔学問論的に〕基礎づけねばならないことになるであろう、というわけですが、この「循環」は、先の循環とは異なって、基礎づけるべきもの(論理学)が自分自身によって基礎づけられるものになる、ということです。これが本来の「自分自身を基礎づけることであります。この企てが「時間的パラドクス」を出現させます。というのも、基礎づけられるべきものが基礎づけるものになるという場合、基礎づけられるべき学は基礎づけるべき学がなくても存在することができます。たとえば、諸科学は、それらを基礎づける存在論がなくても存在できるし、存在しています。探究すべき諸現象が与えられているからです。反対に、基礎づけるべき学は、自分自身を基礎づけるということになれば、基礎づけるものであり、かつ基礎づけられるものでとなりますが、仮に、基礎づけられるものから始めようとしても、それはできません。なぜなら、それはこれから作られるものであって、事実として与えられてはいないからです。ですから、基礎づけるものから始めなければならないことになりますが、そうだとすると、それは基礎づけられるものをあらかじめ知っていなければならないことになります。なぜなら、基礎づけられるものはいまだ存在しないからです。しかも、その知が客観性をもつためには、あらかじめ創出されたものが、のちに現実的な現象として生起するものでなければなりません。つまり、基礎づける学から始める場合には、あとで得られる事実としての基礎づけられるものをあらかじめ創出していなければならないということになります。これが、プラトンのメノンのパラドクスや、カントの「ア・プリオリな総合的判断」や、ヘーゲルの素質のあらかじめの把握におけるパラドクスに潜んでいたパラドクスと同じ形式のパラドクスです。
論理学派は、これで追い詰められたと想像されます。論理学派が時間的パラドクスを解決したという話は聞いたことがありませんから。ある意味、フッサールも追い詰められたと思われます。でなければ、どうみてもこれに対処する方策としか考えられないものが、次に提示されるからです。その方策とは、なんと「従ってnach」と「からaus」の区別という一見簡単なものなのです。
しかしわれわれは、いったいどこに循環があるといわれるのか、その点を更に詳しく考察してみよう。心理学が論理法則を妥当なものとして前提している点に〔循環があるのであろうか〕? だが、前提(Voraussetzung)という概念の多義性に注意されたい。ある学問がなんらかの諸規則の妥当性を前提しているということは、それら諸規則がその学問を基礎づけるための前提(Prämissen)であるという意味でもありうるし、あるいはまた、それらは学問がそもそも学問であるためには是非とも依拠せねばならない諸規則であるという意味でもありうる。〔先の心理学主義者の〕論証はこの二つのことを混同している。すなわち論理法則に従って(nach)推論することと論理法則から(aus)推論することがその論証にとっては同じこととされているのである。なぜなら、それらの諸規則から推論されるとした場合にのみ、循環が成立するからである。しかし多くの芸術家が、美学のことを少しも知らなくても、美しい作品を創作するように、研究者も一度も論理学を引き合いに出さなくても種々の証明をなしうるのである。したがって論理法則がそれら証明の前提であったわけではない。(15)
諸規則「から」という場合は、諸規則をあらかじめ前提していなければならないということですが、言い換えれば、これは諸規則の形成が、現象の探究に先行しなければならないということです。ですから、その場合は、時間的パラドクスが発生します。
これに対して、諸規則に「従って」という場合には、諸規則を前提する必要がなく、逆に、諸規則は経験の後から反省によって――いいかえれば、現象学的に――得られるものとなるわけです。そして、フッサールは、この二つの道のうち後者を取っているわけです。前者をとることは「時間的パラドクス」に陥ることですから、後者をとるということは、「時間的パラドクス」を回避するということを意味することになります。決してその解決ではありませんから。
実はこの道をとることは、序説を書く際には、すでに決定されていました。というのも第一章の冒頭ですでに同じようなことが語られているからです(16)。「従って」という場合、それは何に従ってなのであろうかという疑問に対しては、フッサールはそこで「内的躍動」といっています。内的躍動に従って思考したことを後から反省的に捉えるのが現象学ですから、「従って」の道は現象学の道です。フッサールが、「時間的パラドクス」を回避して行きついた道は、ヘーゲル同様に現象学の道であったわけです。ただ、ヘーゲルと異なるのは、冒頭に述べたように、ヘーゲルでは、「時間的パラドクス」が人間の意識にかかわっていたのに対して、フッサールでは、自己自身を根拠づける学という学の在り方にかかわるものになっているという点です。そして、このことが、ハイデガーに引き継がれます。
(注)
(1) フッサール『論理学研究』第一巻「純粋論理学序説」第六節
学問は文献のうちにのみ客観的に存立するものであり、たとえ学問の現存 が人間とその知的活動に大いに関係があるとはいえ、やはり学問は著述という形でのみ独自に現存しているのである。このような形で学問は数千年来受け継がれ、個人や世代や民族を超えて存続しているのである。このように学問は外的便法の集計であり、そして後者は、かつてそれが多数の個人の知的作用から生まれたように、再び無数の個人の知的作用の中へ移行しうるのである。しかし、このようなことは容易に納得される反面、この移行の仕方を精密に記述することは決して簡単ではない。(立松弘考訳『論理学研究Ⅰ』 みすず書房1968年p.32
(2) 第一章第六節「学問論としての論理学の可能性と資格」同上 p.31
(3) 第一章第十一節「規範学および技術学としての論理学または学問論」、p.46
(4) 同上第二章「規範学の土台としての理論学」第十六節p.59
すべての規範学および実用学は、それら諸学の諸規則が規範化(当為)の思想と区別され理論的内実を所有せねばならない以上、その理論的内実の学問的究明をまさに自己の任務とするひとつのまたは若干の理論学に依拠している。
(5) 同上第二章第十六節「規範学の土台としての理論学」
……どの規範学も、それゆえになおのことどの実用学も一ないし若干の理論学を土台として前提しているのある。すなわち〈規範学や実用学は一切の規範化から切り離すことのできる理論的内実を所有していなければならず、しかもこの理論的内実それ自身は、既に限定された理論学であれ、あるいはまだこれから構成されるべき理論学であれ、とにかくなんらかの理論的諸学のうちにそれ自身の本来の位置を有している〉という意味においてそうなのである。(p.66)
(6) 同上第二章第十三節p.52
(7) 同上第三章「心理学主義、その論証と通常の反対論に対するその立場」第十七節「規範的論理学の本質的な理論的土台が心理学に存するかどうかの論争問題」
……〔論理学の〕本質的理論的土台は心理学のうちにあり、論理学にその性格的特徴を与える諸命題はそれらの理論的内実からみて心理学の領域に属する、……。p.70
(8) 同上第十九節「反対派の通常の論証とその心理学主義的解決」p.72
(9) 同上第二章第十六節、p.67
(10) 同上第三章第十九節
諸原理を心理学から、すなわちわれわれの悟性についての考察から採択するとすれば、われわれは単に、思考作用がどのように進行するか、さまざまな主観的障害や制約のもとでそれがどうなっているか、を見るにすぎず、そしてこれは単に偶然的な法則の認識に到達するに過ぎまい。しかし論理学においては偶然的な諸規則ではなく、必然的な諸規則が問題であり、――われわれがどう考えるかではなく、われわれはどう考えるべきかが問題である。したがって、論理学の諸規則は偶然的な理性使用からではなく、心理学を一切排除した際に見出される必然的な理性使用から取り出されたものでなければならない。(p.72f)
(11) 第三章第十九節「反対派の通常の論証と心理学主義的解決」p76
(12) 同上p.76
(13) 同上、p.77
(14) 同上、p.77
(15) 同上、p.77f
(16) 第一章第四節
日常経験されることであるが、芸術家が自由自在に素材を処理する際のその卓越した技量や、彼が専門とする芸術部門の作品を評価する際の断固とした、しかもしばしば確実な判断が〈実践的作業の進展に方向と順序を指示し、しかもそれと同時に完成した作品が完璧であるかどうかを判定する評価の基準をも規定する諸法則〉の理論的認識に依拠している場合は極めて例外的である。創作する芸術家というものは通例自分の芸術の諸原理を理路整然と解説できるものではない。彼は諸原理に則って〔から〕創造するのでもなく、諸原理に則って〔から〕評価するのでもない。彼は彼自身のあい調和して形成された諸力の内的躍動に従って創作し、繊細に完成された芸術家的敏感さと感情に従って判断するのである。(p.29)