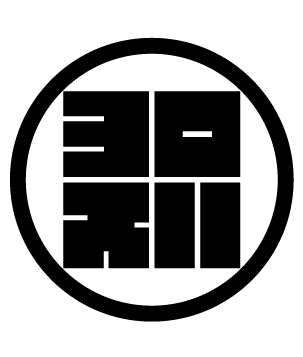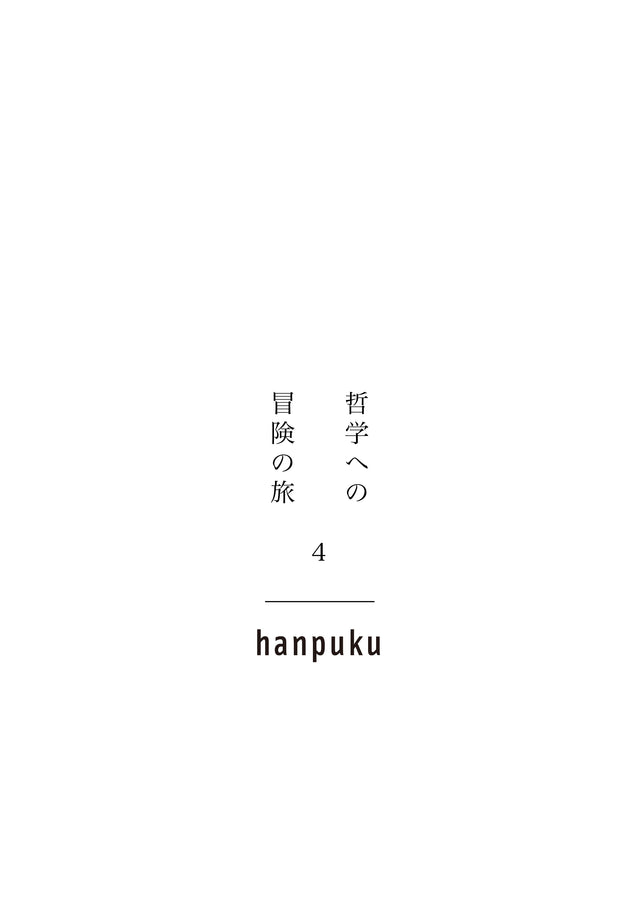
哲学への冒険の旅 4
哲学への冒険の旅 4
4 歴史の中の「時間的パラドクス」 その2 カント
今回は、カントの著作のどこに「時間的パラドクス」が見いだせるのか、お話しします。カントの場合も、やはり一目でわかるほど明らかに示されているわけではなく、見いだすためには若干の分析が必要です。結論から言うなら、カントの主著『純粋理性批判』(以下『純理』)の課題のうちに、それは隠れつつ現われています。『純理』の課題は、「ア・プリオリな総合的判断はいかにして可能か?」という問いとして提示されていますが(1)、このうちに時間的パラドクスが眠っているのです。それを見いだすためには、「ア・プリオリな総合的判断」とはどういうものなのかをまず知る必要があります。第二版序論に従って、簡単に説明します。
語義的にみれば、「ア・プリオリ」とは先行的という意味です。カントでは、それは同時に、経験に由来しない、経験に依存しないことをも意味します。次に「総合的判断」についてちょっと説明すると、判断は、主語と述語で構成されているものですが、そのうえでカントは、判断を分析的判断と総合的判断とに分けています。分析的判断というのは、述語が主語にあらかじめすでに含まれているもので、主語を分析することで述語が導き出される判断のことです。たとえば、「教師とは、何かを教える者である」といったような判断です。こうした判断は経験を必要としないので、ア・プリオリです。それに対して、総合的判断は、述語が主語の外にあって、主語には含まれていない判断で、通常、述語を主語の外から経験を介して得てくるものです。たとえば、「この机は赤い」といったような判断で、「机」という主語には、「赤い」ということは含まれておらず、分析したところで導き出せません。ですから、この判断が成立するためには、その机を見るという経験が必要になります。言い換えると、経験の後でしか成立しない判断です。ですから、「ア・プリオリな総合的判断」とは、経験に従って事後的に成立する判断(総合的判断)を経験によらずにあらかじめ把握している判断ということになります。こう見れば、この課題には時間的に逆行するというパラドクスが含まれている、ということがわかります。
この問いに答えようとする探究を、カントは、「先験的(超越論的)transzendental」と名づけています。「先験的」というのは、戦前のカント翻訳で使われた訳語ですが、ここではこの方が分かりやすいので、今日使われている「超越論的」ではなく、「先験的」という訳語をあえて使用します。「先験的なもの」の探究とは、「経験に先立ち、経験を可能にする」ものの探究を意味します。単に経験に先立つだけでなく、経験を可能にするものでなければなりません。というのも、たとえば、想像的なものは、経験に先立つとしても、かならずしも経験には結びつかず、対象の認識にはならないからです。経験を可能にするものであれば、経験に必然的に結びつきます。これが「先験的(超越論的)認識」と呼ばれるものです。ですから、この術語のうちにも、時間的パラドクスを見いだすことが可能です。経験の後を追って、経験に従うのではなく、経験に先立って、後の経験を可能にするものをあらかじめ捉えるということだからです。繰り返しますが、過去・現在・未来という時間の順序に逆らって、後なるものをあらかじめ、というように逆行しているわけです。
プラトンの場合は、前回見たとおり、時間的パラドクスという問いは、「学ぶことはいかにして可能か?」というそれ自体が隠れていた問いの中にありました。カントの場合は課題が明示されていますが、時間的パラドクスを直接表わすのではなく、特定の内容をもった形でいわば潜在的に表わされています。後で見るように、こうしたことはヘーゲル、フッサール、ハイデガーにも見られます。問題の提出の姿形はさまざまでありながら、それらに共通にみられるひとつの問いがあるわけです。そこで共通のもの(時間的パラドクス)が表明されるさまざまな姿形を「問題形態」と呼ぶことにし、さまざまな問題形態のなかで繰り返されている共通のものを「問題本質」と呼ぶことにします。要するに、現われ方はさまざまですが、その中で変わらない本質的形式が繰り返されている、ということですが、こうした区別は、古い形而上学(存在論)では「実体と付随性」と言われていたものです。カントもこの術語を使用しています。
こうした解釈の仕方は、「問題に準拠する」という点で、ルーマンの「機能的分析」と似ています。
……機能的分析は、究極的には問題に準拠し、その問題の複数の解決法を発見しようとする。(2)
「問題に準拠する」という場合の「問題」を問題本質――ここでは時間的パラドクス―と捉えるなら、同じだといえますが、また相違する点もあります。ルーマンの場合、区別線は、問題と多様な解決法の間に引かれています。ですが、異なる解決は、問題が、異なった形態において提起されることと関連しています。つまり、そもそも「問題」の段階で、繰り返されるもの(問題本質)と多様な現われの区別(問題諸形態)の区別があるわけです。上の術語上の区別――「問題形態」と「問題本質」――が示しているのはまさにそれです。実際のところ、時間的パラドクスに直接挑んでも答えは出てきません。ですから、その時点で使用可能な手段にもとづいて、どういう問題形態でそれ(問題本質)を提出することができるかということが、まずは解決されねばならないことです。時間的パラドクスを、どのように構成するか、それが第一の関門であり、それがクリアーされることで、それに応じた解決の道が拓かれます。
こうした観点から言えば、カントは「ア・プリオリな総合的判断はいかにして可能か?」という問題形態において、時間的パラドクスという問題本質を提示し、それを解決しようとした、ということができます。では、なぜこのような問題形態をとることになったのでしょうか。いくつかの要素はありますが、時間的パラドクスとの関係でもっとも関係深いものは二つあります。ひとつは、十七世紀に勃興してきた近代自然科学で、もうひとつはヒュームによる形而上学批判です。
まず、近代自然科学の勃興と「ア・プリリな総合的判断」の可能性への問いとはどんな関係にあるか、からみましょう。近代自然科学の特徴は、それまでの自然研究が自然の観察に携わり、その経験の中から規則的なことを取り出すものであったのに対して、理論的にあらかじめ構成したものを、実験で確めたり、観察で発見したりすることにありました。もうこれだけでお分かりだと思いますが、近代自然科学は、経験に先立って、経験を可能にするア・プリオリな知によって成り立っているわけです。この事実には、このような知がいかにして可能かを解明せよ、という哲学への要請が暗に含まれています。『純理』は、この暗黙の要請を受け取って、近代科学の知の可能性を解明し、それを根拠づけようとしたものとして受け取ることができます。しかしまた他方で、カントは、近代科学におけるこの考え方の転換を見ただけでなく、これに倣って、形而上学(存在論)においてそれを遂行しようとしました。
これまで人は、すべて私たちの認識は対象に従わなければならないと想定した。しかし、私たちの認識がそれによって拡張されるような何ものかを、対象に関してア・プリオリに概念をつうじて見つけるすべての試みは、こうした前提のもとでは失敗した。だから、はたして私たちは形而上学の諸課題において、対象が私たちの認識に従わなければならないと私たちが想定することで、もっとうまくゆかないかどうかを、いちどこころみてみたらどうであろう。(3)カントは、この考え方の転換を、太陽が地球の周りをまわるのではなくて、地球が太陽の周りをまわるとしたコペルニクスの仕事になぞらえました。そこから、この考え方の転換は「コペルニクス的転換」と呼ばれるようになりました。この転換は時間的パラドクスの問題と緊密に結びついています。というのも、この転換が可能であるためには、経験に従う認識ではなく、経験に先立って経験を可能にするア・プリオリな認識が必要不可欠だからです。カント以降、ヘーゲル、ニーチェ、フッサール、ハイデガーと、これまで二千年以上問題にされなかったのに、たった二百年余のうちに、時間的パラドクスという問題本質が繰り返された現象の根底には、この結びつきがあったということができます。
カントは、形而上学(存在論)においてこの転換を遂行したらどうか、と言っていましたが、実際のところ、存在論においてこの転換を行ったわけではありませんでした。『純理』でなされたのは、「ア・プリオリな総合的判断」がいかにして可能であるのかの解明、すなわち人間の認識能力の解明にすぎませんでした。つまり、近代自然科学の知の可能性を明らかにして、それを根拠づけることでありました。それも『純理』という表題が示しているように、経験に基づかない純粋理性の働きを批判しつつ、それを遂行しようとしたのでした。批判の内容は、端的に言って、「ア・プリオリな総合的判断」のもとになるア・プリオリな概念を純粋理性は産出することはできず、ただ想像的なものしか産み出せない、というものでした。
しかし、ア・プリオリな理性概念が産出しえないとすると、「ア・プリオリな総合的判断」は成立しないことになり、近代自然科学の知を根拠づけることもできなくなります。そこで、純粋理性からは離れて、経験にかかわる悟性認識にア・プリオリ性を与えようとします。そして、経験に諸規則を与える悟性――つまり、経験にかかわる知性としての悟性――に生得的な概念を与え、これを「カテゴリー(純粋悟性概念)」と呼びました。悟性は、経験にかかわる概念を産出する能力のことです。その悟性に、ア・プリオリな概念が生まれつき与えられているというのです。生まれつき与えられているのであれば、その限りで、あらゆる経験に先立つことになります。そのため、「先験的」というカントの概念は「先天的」という意味を帯びることになりました。結局、カントは、人間に生来備わっている認識能力の解明に逃げ込んだのです。しかし、この概念の生得説は、後にピアジェの実験心理学によって打ち破られます。
純粋理性への批判はヒュームの影響によるところが大きかったといえます。カント自身、ヒュームの警告によって、「独断〔古い形而上学〕のまどろみ」から目覚めさせられたといっています(4)。ヒュームは、古来から形而上学が因果関係の概念を根拠づけてきたとしていたことに疑念を提示し、因果性の原理は想像力と習慣の産物だとしました(5)。純粋理性がア・プリオリな概念を産出できず、想像的なものしか産み出せない、とした背景には、こうしたヒュームの形而上学批判があったわけです。
重要な点は、ヒュームの形而上学批判が、因果性の原理に向けられていた、ということにあります。因果性の原理とは、存在するものと存在するものとの関係が、原因‐結果の関係であるとするもので、これがギリシャ哲学以来の西欧形而上学が自明な前提となっていました。この因果性の原理に疑いが向けられ、決して客観的なものではなく、主観的なものでしかないとすると、形而上学としての存在論そのものが疑わしいものとなります。ヒュームの批判は、因果性の原理を習慣に基づく主観的なものとしたのですが、だとしたら、存在者と存在者の客観的に必然的な結合関係は、どうなのか? 因果性のほかにあるのか、という問題が生まれます。そうだとすれば、因果性に代わる存在者と存在者の客観的に必然的な結合関係を見いだし、根拠づけるという新たな課題が存在論に課せられることになります。
しかしカントは、上に見たように、この問題には手を付けることなく、人間の認識能力の解明に向かっているのです。つまり、カントの理論は、認識論にとどまり、存在論には至らなかったということです。時間的パラドクスという問題本質が、「ア・プリオリな総合的判断はいかにして可能か」という問題形態をとっていることの意味はそこにあります。この問題形態は、ある特別な認識の可能性への問い、つまり認識論の問いであって、存在論の問いにはなっていないのです。認識論から存在論への転換は後に、ハイデガーによって行われますが、時間的パラドクスの壁に阻まれて正面突破できず、方向転換してしまいます。ですから、コペルニクス的転換を存在論において遂行することは、依然として課題として残されているのです。
カント以降の哲学――ヘーゲル、ニーチェ、フッサール、ハイデガー――は、前にも言ったように、いずれも時間的パラドクスに解決を与えるものではありませんでした。哲学は、模索のなかにあったのです。ニーチェはすでに述べていますので、次回、ヘーゲルから見てゆくことにします。
注
(1) カント『純粋理性批判』第二版序論Ⅵ「純粋理性の普遍的課題」原佑訳、理想社版カント全集第四巻p.96
(2) ルーマン『信頼』大庭健、正村俊之訳、勁草書房1990年p.3
(3) カント『純粋理性批判』第二版序文 同上p.40f
(4) カント『学問として現われうるであろうすべての将来の形而上学へのプロレゴーメナ』序言 土岐邦夫・観山雪陽訳 世界の名著39「カント」中央公論社 所収p.94
(5) 同上p.92
実際は、想像力が経験によってはらまされて、或る表象を連合の法則にもとにもたらして、そこから生じる主観的必然性、すなわち習慣を、洞察から生じる客観的必然性とすりかえたのだ……。