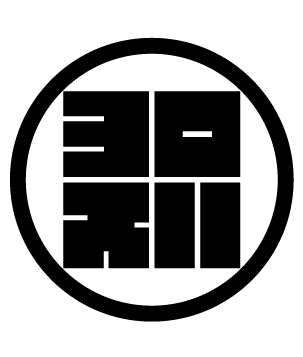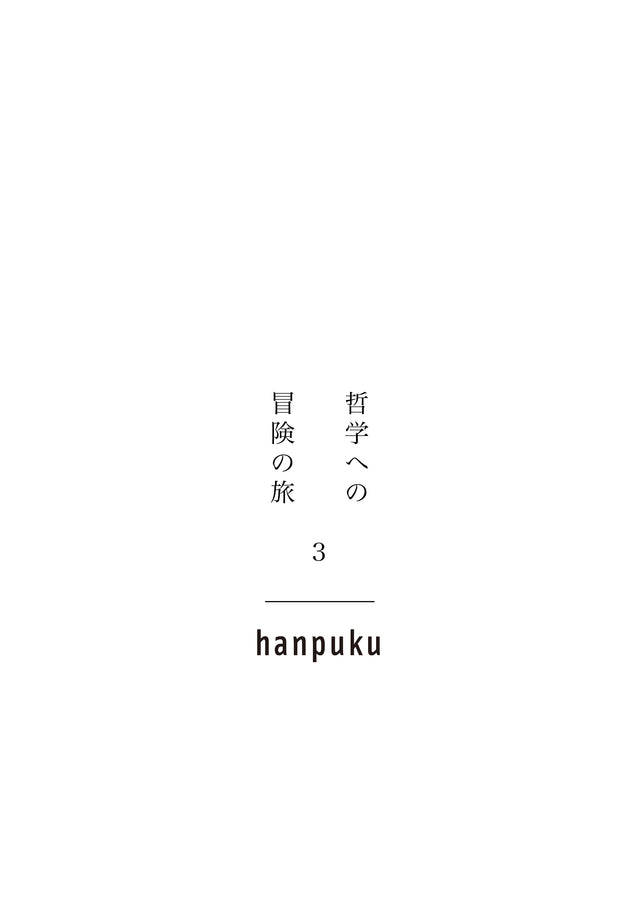
哲学への冒険の旅 3
哲学への冒険の旅 3
3 歴史の中の「時間的パラドクス」 その1 プラトン
前回は、認識者の先行的な自己認識という企てそのものに解決不可能に思われる難問が含まれており、それを第二の墓と呼び、最後に、今回その墓の正体を明らかにすると約束しました。それを果たします。
常識的には、これから哲学的探究を行うもの、つまりこれから哲学者になろうとするものが、まず哲学者を自己認識するということなどできるはずがありません。それはまさにベンヤミンのいうところの、探究の「冒頭に置かれた場合には解き明かしえぬもの」(1)であります。
そういう問いもたしかに哲学にはあります。たとえば、「哲学とは何か」という問いが哲学的探究の端緒に置かれた場合には、やはり解き明かしえないものとなります。ただし、それはこれから自分が作り出す哲学をあらかじめ認識するという場合のことで、哲学をはじめて学ぶ人が「哲学とは何か」と問う場合はそうではありません。その場合は、なにも自分で哲学を作り出そうとしているわけではなく、これまで行われてきた哲学はどうようなものであったかを知りたいということです。それはつまり、哲学の歴史のなかで哲学の本質を学ぼうとすることで、事後的な認識ですから、先行的な認識の不可能性に陥ることはありません。哲学者になるに先立って哲学者を自己認識しようという場合は、後で存在するはずのものをあらかじめ認識しようとすることですから、これは過去から未来へという時間の順行的な流れを逆転させるようなパラドクスだといえます――そこで私はこれを「時間的パラドクス」と呼びました(2)。誤解しないようにお断りしておきますが、「時間のパラドクス」ではありません。その場合は、時間そのものがパラドクシカルだという意味です。そうではなくて、パラドクスが時間的な姿をとっているということです。そして、これが第二の墓の正体です。
私は、探究のまさに始まりの時点で、このパラドクスに捉えられて、もはや一歩も進めなくなりました。さしあたり解決不可能と思われた問いを抱えて身動きできず、立ちんぼうになってしまったのです。それでも解決を断念したわけではありません。そのうち解決できる日が来るだろう、くらいにのんきに構えていました。のちになって、この不可能性は、単に〈さしあたり〉ではなく、存在の問いの本質にもとづく必然的なものであることが明らかになるのですが、この時点では知る由もなく、あくまで探究を続けていれば、そのうち解決されるだろうと思っていました。そこで、解決が可能になるまで、とりあえずは、そこへ向かう自分の探究を事後的に把握しよう考えたのです。こうして、目的地ははっきりしているが、どこをどのように行けばいいのかルートの見えない暗闇のなかで、行き当たりばったりの、曲がりくねった哲学探究の迷い路に入り込むことになりました。
結局、ニーチェがダメだといった、事後的な自己探究をすることになったわけです。そういう方針――いわば広い意味での現象学的な方針――で、哲学的探究を続けていると、そのうち次のような経過を繰り返していることに気づくようになりました(3)。まず時間的パラドクスに挑戦する、しかしそれは不可能に終わる。次に解決不可能な問いを抱えたまま、哲学の歴史に入り込み、時間的パラドクスに相当する問いがないか探す。そして、次に、哲学以外のテキストのうちに同様のパラドクスの表明がないか探す。やがて、はじめにもどってまた時間的パラドクスに挑戦する、といった運動を繰り返し行っていたのです。
そういう繰り返しの中で、哲学の歴史のなかに、時間的パラドクスとその解決形態としての哲学理論、とみられるものがあることがわかってきました。私がみつけたのは、まずプラトンとカントです。この二人は、時間的パラドクスに挑戦し、それにひとつの解決を与え、それにもとづいて、それぞれ独自の理論として提示していました。さらにヘーゲル、ニーチェ(既述)、フッサール、ハイデガーですが、彼らは、時間的パラドクスの前で屈して、別の道へと逸れています。このパラドクスの形式と内容を捉えるうえで資すると思われるので、以下、これらの哲学者たちを取り上げて、どの著作のどこで、どういう問題形態で時間的パラドクスが提示されているかをピンポイントで指摘し、プラトンとカントの場合は、それにどのような解決形態を与えているのか、ヘーゲル、フッサール、ハイデガーの場合は、どのような道に逸れているのかをみておくことします。まずプラトンからはじめます。
『メノン』のなかでソクラテスは、ひとつのパラドクスに直面します。それは、「論争家ごのみの議論」として提示されているもので、次のようなものです。あらかじめ断っておきますが、それ自体は時間的パラドクスではありません。
いわく、「人間は、自分が知っているものも知らないものも、これを探求することはできない。というのは、まず、知っているものを探求するということはありえないだろう。なぜなら、知っているのだし、ひいてはその人には探求の必要がまったくないわけだから。また、知らないものを探求するということもありえないだろう。なぜならその場合は、何を探求すべきかということも知らないはずだから」(4)
敷衍するまでもないですが、自分が知っていることを探求することはないし、知らないことは何を探求すべきかをも知らないのだから探求できない。結局、人は探求したり、学んだりすることはできない、ということになります。これに対して、ソクラテスは、探求したり学んだりすることは想起することだと答えます。一見してこの答えは、問いと直接つながっていないのではないかと思われます。唐突感があるのです。そこで、この答えは、かの難問とどうつながっているのかを考えてみることにしました。そして次のように考えました。以下は論理的に考えるならこうだろうというものです。
難問に従うなら、人は探求することも学ぶこともできないという結論になります。ですが、実際には、人は探求することも学ぶこともできます。それが事実です。この事実を踏まえるなら、ではどうすれば人は探求することや学ぶことできるのでしょうか、という問いが生まれます。そう考えると、難問の第一のテーゼ、人は知っていることは探求しない、ということはそのとおりというほかないのですが、第二テーゼ、人は知らないことをも探求できない、に関してはどうでしょうか。実際には人は学ぶという事実があるのですから、そこでは、なぜ人は学ぶことができるのか、という問いが発生してきます。そして、それについてはつぎのように考えることができます。すなわち、先の第二テーゼを踏まえて言うなら、人が探求することや学ぶことができるためには、〈人は知らないことをあらかじめなんらかの意味で知っているのでなければならない〉ということになります。これは私が時間的パラドクスと呼んだものにほかなりません。
しかし、どのようにして? でしょうか。これに対する答えが想起説だ、と考えることができます。想起説がこのパラドクスへの答えであることは、その内容を調べてみれば明らかです。そこでソクラテスは、「神職にある」人々の話として、オルペウス教の教えを紹介しつつ言います。
彼らの言うところによれば、人間の魂は不死なるものであって、ときには生涯を終えたり――これが普通「死」と呼ばれている――ときにはふたたび生まれてきたりするけれども、しかし滅びてしまうことはけっしてない。……
こうして、魂は不死なるものであり、すでにいくたびとなく生まれかわってきたものであるから、そして、この世のものたるとハデスの国〔死の国〕のものたるを問わず、いっさいのありとあらゆるものを見てきているのであるから、魂がすでに学んでしまっていないようなものは、何ひとつとしてないのである。だから、徳についても、その他のいろいろな事柄についても、いやしくも以前にも知っていたところのものである以上、魂がそれらのものを想い起すことができるのは、なにも不思議なことではない。(5)
要するに、魂は不死で、あらゆるものを学んできてしまっているので、何でも知っているから、それを想起するのだ、というのです。これは、人はあらかじめすでに知っているということの根拠を宗教的な物語で示しているといえます。ですが、すでに知っているのであれば、それを探求することもないわけですから、すでに知っているが知らないという状態にあるのでなければなりません。そこで、すでに知っているのだが忘れているという状態が考えられねばなりません。この点は『メノン』では語られていませんが、後の『パイドン』では以下のように語られています。
ただ『パイドン』からの引用を読むためには、そこで前提されているある区別を知っておかねばなりません。それは何かというと、たとえば、「さまざまな「〔美〕しいもの」と、「美しさそのもの」との区別です。この区別は、アリストテレスの「第一実体」と「第二実体」と重なる要素を持っています(6)。一般的には個別例と本質の区別といわれるものですが、記号論理学の言い方では、「値」と「関数」という区別に相当します。私自身は、記号論理学の区別法を使っています(後述)。
生まれる前に手に入れながら、生まれるさいに失い、後になって感覚を用いてそれについて〔美しさそのものについて〕、かつて以前にわれわれが持っていたかの知識を再び手に入れるとしたら、われわれが学ぶと呼んでいることは、じつは、自分の所有だった知識を再び手に入れることではないだろうか。そして、このことが、とにかく、想起することなのだと言ったら、その言い方はただしくないだろうか。(7)
ここには、『メノン』では明確に区別されていなかった感覚的なものと感覚を超えたもの――等しさそのものとか、美しさそのものといったもの――の区別が行われており、魂が生まれる以前に知っているものとは、そうした感覚を超えたものであるとされています。この区別は、時間的パラドクスの中では理論的には必然的です。というのも、未来のものを感覚することはできないわけですから、感覚的には知らないものについてあらかじめ知っているものは感覚的なものではなく、感覚を超えたもの(超感覚的なもの)、すなわち頭で考えることのできるもの、でなければならないからです。さらに『パイドン』は、感覚的なものがきっかけになって、あらかじめ知っている超感覚的なものが想起されるといっています。これは一般的に言えば、経験から本質に向かうという道で、後述するカントの「コペルニクス的転回」において考えるなら、転回以前のあり方を示すものと言えます。
ということで、想起説には、時間的な逆転だけでなく、感覚的なものとそれを超えたものとの区別が必然的に含まれることになります。そしてそうしたものをとらえることのできるのは、プラトンにおいては、不滅の魂であるということになります。
この宗教的な物語では、第一に時間的パラドクスは隠れていて、その姿を現わしていません。与えられている難問そのものは、時間的パラドクスを表わしておらず、それを露現させるためには、難問に直接反応して応えるのではなく、事実に基づいて、探究が可能であるためにはどうでなければならないか、と一歩踏み込んで問うといった考察が必要です。
プラトンの答えは歴史的なものです。ですが、問いの方――時間的パラドクス――は形をかえて繰り返されます。実際、プラトンの時代から2100年ほど後の18世紀にカントが別の形でこの問いを問うています。
(注)
(1) ベンヤミン「言語一般および人間の言語について」『ベンヤミン・コレクションⅠ』ちくま学芸文庫p.011
(2) ハイデガーは1955年の講演『哲学とは何か』(ハイデガー選集7原佑訳p.14)で同じパラドクスに直面していますが、それを「循環」と呼んでいます。彼は、初期の『哲学の理念と世界観問題』(1919年)でも、根源学の理念に含まれているパラドクス――それは私の考えでは時間的パラドクスなのですが――、をやはり「循環性」と呼んでいます。後で見ますが、ヘーゲルもフッサールも同じ形式のパラドクスを「循環」と呼んでいます。
(3) フッサールでいえば、これは現象学的探究の第一段階に相
当します。
まず第一に……超越論的な自己経験の広大な領土が遍歴されなければならない。しかも、さしあたり、調和的な流れに内在する明証にただ身を任せて。明証が及ぶ範囲を決めるにあたって、疑いのない原理にに対して考えられる、究極的な批判的吟味という問いは留保しておく、それゆえ、十分な意味ではまだ哲学的ではないこの段階では、自然科学者が自然な経験の明証に身を委ねているのと同じように振る舞うことになる。(『デカルト的省察』第二篇第一三節、浜渦訳、岩波文庫p.63)
(4) プラトン『メノン』80e 藤沢令夫訳 岩波文庫p.5f
(5) 同上81bc.p.47f
(6) アリストテレスは「カテゴリー論」の第五章で、第一実
体の例として「ある特定の人間、ある特定の馬」を挙げ、第
二実体の例としては「人間や動物」といった類種的な概念を
挙げています。
(7) プラトン『パイドン』75e 村治能就訳 全集1 角川書房p.163