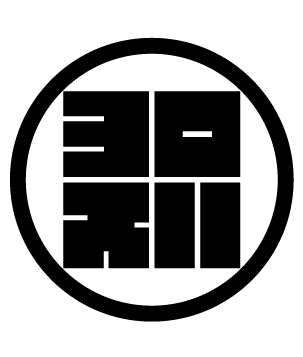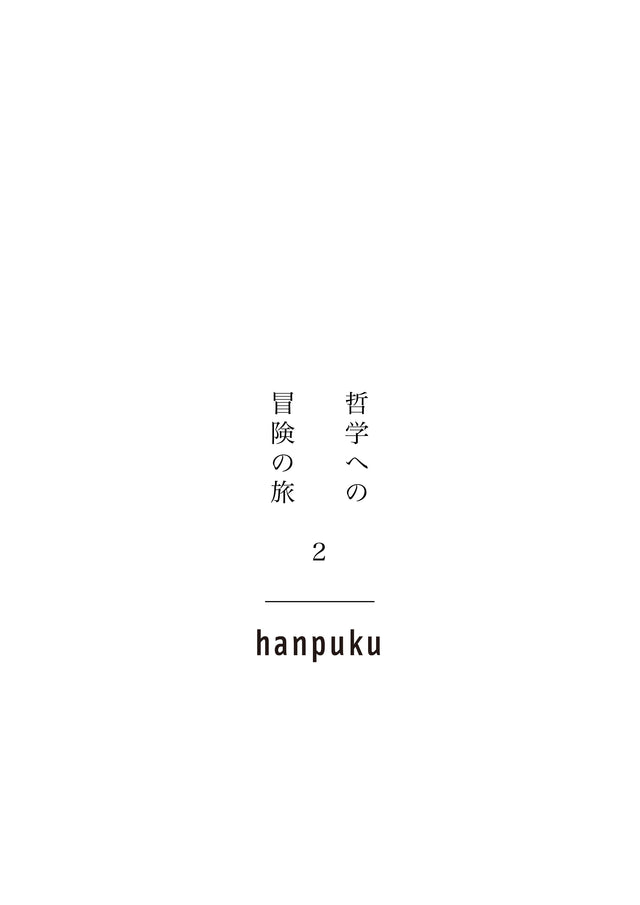
哲学への冒険の旅 2
哲学への冒険の旅
塚原誠司
2 二つの思い その2――ニーチェ
今回は、先送りしたもう一つの思い――認識者の自己認識という思い――に移ります。はじめに述べたように、これは、まず自分自身を知らねばならないという内的な衝動が、自分で哲学を作ろうと思ったときに、哲学を作る自分を認識しなければならない、という形になったものです。そのため、私の場合、自己認識は、ある性格を持つことになりました。それは何かというと、先行性という性格です。これから哲学を作ろうとするのですから、むろん、哲学の制作者としての自分も、いまだ存在していないわけで、それを認識する――想像したり、予言したりするのではなく――ことは、当然、事実や現象に先立つという性格をもつことになります。
認識者の自己認識については、すでにニーチェが『道徳の系譜』序言で、これまで追及されたことがない、と指摘していました。
われわれはわれわれに知られていない。われわれ認識者が、すなわちわれわれ自身がわれわれ自身に知られていない。それはそのはずである。われわれは決してわれわれを探し求めたことがないのだ。――われわれがいつかはわれわれを見出すであろうなどと、そんなことがどうして起こるというのか。(1)
一口に認識者の自己認識といっても、それには二つの対立する方向があります。ひとつは、すでに哲学者である者が自分自身を反省的に認識するというものと、いまだ哲学者でないものがいまだ存在しない自分を認識するという場合です。上に述べたように、私は後者の道を辿ろうとしていました。では、ニーチェは、どちらの道のことを言っているのか? 序言の続きを読むと、外的対象の認識と認識する者が自分の体験をあとからふり返ることに関して言われています。ですから、そこでは事後的な自己認識について言われていることになりますが、重要なのは、そうした自己認識がかならず誤るといわれている点です。少し長いですが引用しておきます。
……いわゆる〈体験〉に関することなど、――われわれの誰がこれを顧みる真面目さだけでももっていようか? いな、その時間だけでももっていようか? そうしたことについては、おそらくわれわれは、本当に〈事に専念した〉ためしさえなかったようだ。まことわれわれの心はそこにはない、――われわれの耳すらもそこにはない! むしろ、神々しき放心の境にある者や自己沈潜の裡にある者の耳に、折しも時鍾が力をこめて烈しく正午の十二の音を打ち告げるとき、その者が不意に目覚めて、「はてあれは何時を打ったのか?」とわれと自らに問うように、われわれもまた時折あとになって耳をこすりつつ、すっかり驚き狼狽えながら、「われわれは一体いま何を体験したのか?」と訊ねるばかりか、さらには「われわれは一体何者であるか?」とさえ訊ね、そして今言ったように、あとになってから、われわれの体験・われわれの生・われわれの存在の震える十二の時鐘の音を、のこらず数えなおす、――ああ! しかもその際に数えそこなう……。われわれはわれわれにとって必然的にどこまでも見知らぬ者なのだ、われわれはおのれを理解しない、われわれはおのれを取り違えざるをえない。われわれには、「各人はそれぞれおのれ自身にもっとも遠い者である」という命題が、永遠に妥当する。――われわれにたいしては、われわれはけっして〈認識者〉ではない……。(2)
つまり、ニーチェは、事後的な自己認識の道に対して墓標を立てているわけです。ですが、事後的な自己認識だけが自己認識ではありません。はじめに「探し求めたことのない」と言われているのですから、事後的ではない他の自己認識の道があるのでなければなりません。先行的な自己認識を行おうとしている私からみれば、ニーチェが暗に示している道は、事前的、先行的な道だとただちに察せられます。そうでなくても、自己認識の道が、事後的か、事前的か、の二つの道しかないとすれば、ニーチェが「探し求めたことがない」と言っている道は、当然、事前的・先行的な自己認識の道のことだということになります。しかし、ニーチェには、このことを直接、明示的に表明している文章はありません。ただそれを推察させる傍証といえる断章は残されています。
根本思想。すなわち、私たちは未来を私たちの価値評価すべてにとっての標準とみなさなければならず、――私たちの背後に私たちの行為の法則を探しもとめてはならない! (3)
繰り返しますが、ここにはっきり打ち出されている哲学姿勢は、いまだ存在しないものに価値評価の標準を求めるのであって、すでにあるものには求めはしない、ということです。ニーチェの思想はときに反近代的だと言われたりしますが、この姿勢はまことに近代的です。というのも、この姿勢は、形式的に見れば、カントがコペルニクス的転回と呼んだものと同じだからです。後で詳しく述べますが、カントが哲学において行おうとしたのは、認識が事実に従うことから、事実が認識に従うことへの転回でありました。ニーチェが言っていることも、これと同じことです。
すでに存在するものに価値の基準を求めることは、時間的に言えば、過去に、つまり「背後に」求めることであり、いまだないものに標準を求めることは、未来にそれを求めることです。そして、前者から後者へと転回するとニーチェは明言しているのです。
さらに突っ込んで言うと、こうなります。
事実の状態はそれ自身では存在しない。それどころか、事実が存在する以前に、まず意味をそこに導入しなければならないのだ。(4)
この基本的姿勢からすれば、認識者の自己認識もまた、先行的なものでなければならないはずです。しかし、それについてはただ沈黙しかないということはどういうことでしょうか。その可能性には絶望していたということでしょうか。実際、先の引用文では、「われわれがいつかはわれわれを見出すであろうなどと、そんなことがどうして起こるというのか」と言われています。これが先行的な自己認識の可能性を断念していることを表しているものだとするなら、もう一つの思想の墓がここに現われている、ということになります。第一の墓は、事後的な自己認識の墓で、その墓の下に事前的な自己認識の可能性という課題が見出されるのですが、その新たな課題そのものが不可能性を秘めた思想の墓だということになります。
しかし、ニーチェが先行的な自己認識の道を完全に断念していたともいえません。というのも、たとえば、ある断片には、「おのれ自身をみずから産み出す芸術作品としての世界」(5)という言葉が記されています。探究の端緒ではなく現在到達した地点に立っていうなら、私が実際に産みだしたテキストも、「おのれ自身をみずから産み出す哲学作品」といえるものです。違いは、芸術作品であるか、哲学作品であるかにあります。ですが、そうした作品は、事前的な自己認識という理念が抱えているパラドクス(後述)にある解決を与えることによって産み出されたものです。このことから。ニーチェの言葉は、やはりパラドクスへの解決を見ていたことを表しているように思えます。ただ、それを哲学においては行えないと考えていたので、芸術に期待し、託したのではないかと解釈されます。だとすれば、当の難問を完全に断念したわけではなかったということではありますが、しかし哲学にとっては、依然としてそこには思想の墓標が立てられていたということです。
墓標は、上に見たように、ある理論的企てが挫折したまさにその場所を示すものですが、それはまた、私にとっては、「ここに解決されるべき課題がある」と、取り組むべき課題を告げる指標でもありました。私が哲学的探究をはじめるときに抱いた、「二つの思い」も、墓標の下から見いだされた二つの課題でありました。もういちど繰り返すなら、ひとつは、認識者の先行的な自己認識という課題であり、もうひとつは、交換の可能性という課題です。
後者の課題については、ハイデガーの現存在の存在論では欠落していると第一回で述べましたが、前者についても、『存在と時間』では欠落しています。「存在の意味を問うものの存在を問う」と言いながら、ハイデガーが主題化しているのは、日常的な現存在でした。日常的な現存在は、存在了解はもちますが、存在認識はもちません。存在認識は、存在論を形成する者(学的な存在論者)がもちうるものです。ですから、「現存在」の存在論は、存在了解の存在論であって、存在認識の存在論ではありません。後者であるためには、存在論者自身の存在が問われねばなりません。それが問われないまま欠落しているのです。
つまり、『存在と時間』では、この二つのものが欠落しているのに対して、私の企てでは二つともを取り上げるということになってるわけです。これは意図したことではありません。この稿を書いて気づいたことですが、両者は、まるで陰と陽のような関係にあることになります。そうだとするなら、この二つのものには、何らかの関係があるのではないか、とさえ思えます。
しかし、探究の端緒においては、認識者の先行的な自己認識という課題と、交換可能性の課題とは、たがいにかけ離れていて、とうてい結ばれようがない、と思われました。考えあぐねたすえに、こう考えるようになりました。すなわち、人間の存在を、交換を可能にする存在として規定することができれば、経済的交換にとどまらず、さまざまな交換現象を、人間存在の存在可能性として根拠づけることができるのではないかと一方で思い、他方で、人間存在の存在を解明するために、認識者自身の存在を先行的に自己認識することを方法として採用することができるのではないか、と。こうすれば、「二つの課題」は、課題と方法として整理され、すくなくとも形の上では、一つの計画のなかに結ばれることになります。
ところが、この計画を実践に移す段になった途端、たちまちこの計画をうち砕くようなとてつもない困難に直面させられることになりました。そもそも方法としての認識者の先行的な自己認識が抱えている不可能性が、そこで露わになり、解決を迫るのです。
この第二の墓の下からなにか別の課題を見いだすことは不可能です。というのも、この課題は、解決するか、そうでなければ、退いて別の道を歩むか、のどちらかしか選択肢のないもので、まさに〈究極の課題〉とでも言うべきものだからです。一体、この第二の墓の正体は何か? 次回はその話から始めます。
注──
(1) 『道徳の系譜』序言、信太正三訳、ニーチェ全集第十巻、理想社1967 p.323
(2) 同上p.323f
(3) 『権力への意志』(1000、原佑訳、理想社版全集12-p.417)
(4) ロラン・バルト『テクストの出口』(沢崎浩平訳、みすず書房1987,p.95)からの孫引き
(5) 『権力への意志』( 796,同上12-p.266)
塚原誠司(つかはらせいじ)
1944年東京生まれ。1967年、早稲田大学文学部西洋哲学科卒業。労働運動系広報誌の編集者、塾講師、警備員などを経て、現在、自らの哲学を「自己言及的存在論」として展開している。
ポッドキャスト「自己言及的存在論講義」pod.link/1456031219