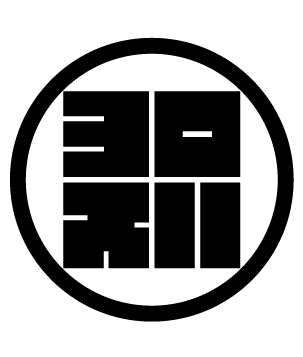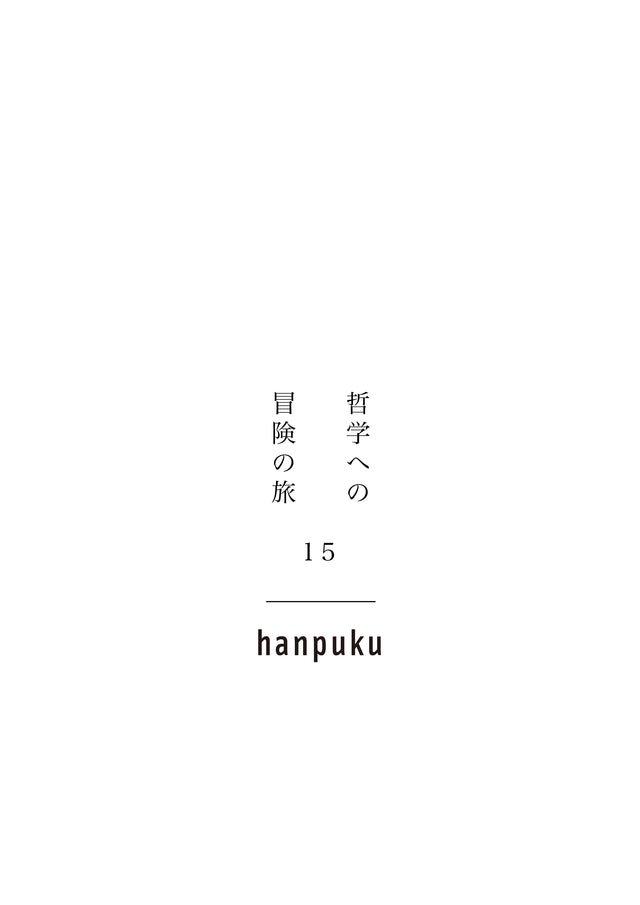
哲学への冒険の旅 15
哲学への冒険の旅15
諸手段の獲得
1
これまで見てきたように、ハイデガーは、おのれ自身を根拠づける学(根源学)の可能性を断念しましたが、その理由として彼が挙げているのは、「突破する手段が何一つない」ということでありました。他方、私たちは、ハイデガーが方法としては持たなかったいくつかの手段をすでに持っています。それらを用いて、おれ自身を根拠づける学(根源学)を形成することができるかどうか。それが問題です。
それら諸手段には、むろん、ハイデガーが切り開いた理論の枠組みである存在論も含まれますが、すでに見たように、それもただそのまま受け継いだものではありません。形式的にいえば、批(・)判(・)的(・)に(・)受け継いでいるわけですが、これから挙げるものもすべてそのまま受け継いだものではなく、批判しつつ受け継いだものです。それら諸手段としてここで挙げるのは、自己言及性、シニフィアンとシニフィエの区別、記号論理学における概念の関数表記です。この三つは、それぞれ別々に獲得されたものではあるのですが、絡まりあって存在論のひとつの方法となっています。中心となっているのは、自己言及性で、シニフィアンとシニフィエの区別や概念の関数表記が、これと絡み合っています。前回申しましたように、自己言及的存在論と名付けたのは、存在論に自己言及性を導入しているからですが、この場合の自己言及性は、そうした三つの要素が絡み合ったものを指しています。
自己言及性というとなにか仰々しいもののように思えますが、その実、簡単なものです。まず、存在論は、あらゆるものの存在を開明するものと仮に規定します。ところで、存在論もまた存在するものです。厳密にいうと、存在論自体は表現される意味で、存在するのは存在論を表現するテキストです。逆にいうなら、存在論は何ららかのテキストにおいて表現されたものです。この時点ですでに、ソシュールによって区別された「意味するもの(シニフィアン)と意味されるもの(シニフィエ)」が取り入れられています。この区別なしに〈存在論はそれ自身存在する〉といった場合、存在するのが「意味されるもの」(シニフィエ)なのか、意味するもの「シニフィアン」なのか判然としないということになります。意味(シニフィエ)は、それ自体で存在するものではなく、シニフィアンにおいて「意味されるもの」を指すものです。それを「概念」ということもできます。概念は、中世哲学の実在論ではいざ知らず、今日ではそれ自体存在するものとはみなされていません。存在するのは、シニフィアンです。ですから、存在論に自己言及性を導入するということは、存在論が示す「あらゆる存在するものの存在」に関する諸概念や諸命題が、それらを表現するテキストの存在に言及され、それらの存在の解明に用いられるということを意味することになります。
ですから、この関係は同時にまた論理学的な関係を含んでいます。その関係とは、存在論が呈示する諸概念や諸命題が、それらを表現するテキストを指示対象としてもつことを想定しているということです。概念と指示対象との関係を扱うのは意味論と呼ばれる分野なので、この自己言及性は意味論的な自己言及性だということになります。
2
以上を具体的な例で見てみることにしましょう。たとえば、ハイデガーの存在論に接することができるのは、『存在と時間』という名の著作を、翻訳本としてであれ、読むことができるからです。このテキストはいうまでもなく存在するものです。存在論は、あらゆるものの存在の開明を目指すものですが、『存在と時間』も「存在一般」の意味の開明を目指しています。であれば、『存在と時間』は、それ自身の存在をも解明しうる「存在一般」の概念を呈示しえなければならないはずです。でなければ、「存在一般」を目指すものたりえないからです。実際、「あらゆるものの存在を開明する」と称しながら、それを表現するものの存在を開明できないのであれば、看板に偽りあり、となってしまいます。その点からみると、『存在と時間』は、完全に失敗作です。なぜなら、そもそも「存在一般」の意味の解明には到達できず、それに先立つ探究としての現存在の存在の意味の究明にとどまっているからです。
ただ、自己言及性に関しては評価は微妙になります。たしかに、『存在と時間』は、「存在一般」を探究する方法として自己言及性を明示的には取り入れいません。しかし、自己言及的な関係が作動していないとはいえないからです。というのも、『存在と時間』が問うているのは、存在一般を問う者の存在でありますが、ここには自己言及性が事態として作動されているからです。というのも、そこでの存在一般には、それを問う者の存在があらかじめ含まれていなけれがならないです。だからこそ、まず第一に問う者(現存在)の存在が問われることになるからです――もっともこれはSROの視点からの分析で、『存在と時間』のなかでそういわれているというわけではありません。ですが、存在一般が、それを問うものの存在をも開明しうるものとして問われていることは明らかです。なぜなら、実際には成功しませんでしたが、計画では、存在一般が開明された暁には、現存在の存在が、「存在一般」の視点からあらためて規定されることになっていたからです。ですから、前にもお話ししたように、『存在と時間』においても自己言及性は潜在的に作動しているわけです。しかし、方法として自覚的に用いられてはいなかったわけです。
私たちが目指している自己言及的存在論は、この自己言及性を、存在論に内在する論理として、顕在化するものです。これは存在論そのものが内抱している論理で、外から持ち込まれるようなものではありません。自己言及性を導入すると言うと、外から持ち込まれると誤解されるかもしれませんが、そうではなく、もともと存在論が内に潜在的に抱えているものを顕在化させるにすぎないのです。また、顕在化といっても、『存在と時間』の問い――存在を問う者の存在を問うという問い――をそのまま受け継ぐわけではありません。自己言及的存在論は、すでに見たように、存在論を表現するテキストの存在を開明しうる存在概念を求めているわけです。ですから、まず初めに問われるのは、存在論のテキストの存在です。すると、逆にこう言われるかもしれません。まず存在論を表現するテキストの存在から始めるというのであれば、それを問う者の存在を問わないということになるのではないか、と。ですが、それは違います。人間が先が、テキストが先か、といった問題ではないのです。存在論を表現するテキストの存在から始めることは、根源学から始めるということです。根源学とは、これまでも見てきたように、おのれ自身を根拠づける学のことです。学はテキストにおいて表現されるものです。「学問は著述という形で独自に現存している」(71)とフッサールも言っていました。〈おのれ自身を根拠づける〉ということは、それによってあらゆるものの根拠が与えられるということです。であれば、〈おのれ自身を根拠づける学〉は、当然、根拠を表現するテキストを根拠づけることができなければならないはすです。でないと、「あらゆるもの」に根拠を与えることにはならないからです。ということは、「あらゆるものの根拠」は、それ自身を表現するものの根拠をも含んでいなければならないということ、いいかえれば、根拠は、それ自身を表現するものへと自己言及しうるものでなければならないということです。そしてまた、根源についての学は、それ自身、学の根源です。ですから、そこから他のすべての存在論が発現しうる存在論でもあります。ということは、根源学から始めるならば、存在の問いを問うものの存在を開明する存在論へと展開しうるということになります。実際、ハイデガー自身が認めているように、『存在と時間』の存在論は、根源学のもつパラドクスを解決できないために「さし戻された」存在論であったわけで、それが意味していることは、現存在の存在論は、本来ならば根源学の後で産出されるべき存在論であったということであります。ですから、根源学から始めるということは、『存在と時間』では不在であった根源学が顕在化されるというだけのことで、それに続いて人間的現存在の存在論に進みうるということでもあります。
3
このように自己言及性は、存在論にも、根源学にも、ましてや根源学としての存在論(根源的存在論)にも内在する論理ですから、それを顕在化し方法として用いることは、根源的存在論にとって、決定的に重要であることは推察されうることです。しかし、それは後から分かったことで、根源学や存在論の理念から自己言及性を導き出した、というわけではありません。そもそも、私の探究は、認識者の存在を先行的に認識することはいかにしてできるのか、という問いから出発していました。その問いに答えるためには、いまだ存在していない自分の存在をあらかじめ把握することができなければなりません。これが時間的パラドクスであったわけですが、この問いと自己言及性とはすくなくとも直接には関係してないように見えます。実際、当初は認識者の存在の先行的な自己認識の探究を、私は超越論的探究の一種と見ていました。フッサールが、認識者の自己認識を「超越論的」と呼んでいたからです(72)。ただし、フッサールとの違いは、フッサールが後からの認識(反省)であったのに対して、あらかじめの認識を求めている点でした。もっとも時間的パラドクスに直面し、この壁を乗り越えられず、不承不承、自分の存在を後から把握する、広い意味での現象学的な探究を行っていたわけですが、そうした探究の途上で、自己言及性に出会うわけです。ですから、私の体験としては、自分の課題を「超越論的課題」とおもっていたところ、或るとき自己言及性に出会った、ということになるわけです。
具体的にいうと、80年代前半に柄谷行人が、批評テキストで、当時アメリカで話題になっていた自己言及性を論じはじめたのです。その際呈示されていた自己言及性は、「噓つきのパラドクス」と呼ばれるもので、たとえば、ひとりのクレタ島人が、「クレタ島人は嘘つきだ」と言う、といったもので、これは悪循環を引き起こすものでした。なぜなら、そうだとすると、「ひとりのクレタ島人」の言った内容も「嘘」ということになり、「クレタ島人は嘘つきではない」ということになってしまい、またそうだとすると、今度はひとりのクレタ人が言ったことは「嘘でない」ということになってしまい、結局、「嘘」と「嘘でない」の悪循環に陥り、意味が決定できないことになるからです。ですが、この悪循環は、否定的な内容が自己言及されるからおこることです。仮に、ひとりのクレタ島人が、「クレタ島人は正直だ」と言う、というのであれば、悪循環は起こりません。この内容が「ひとりのクレタ島人」に自己言及されても、内容は変わらないからです。ただし、この場合には、言明の内容が、現実から乖離しているということになります。ですから、その場合は、現実と合致しうる内容をいかにしてあらかじめ言明することができるのか、という問題が起こります。形式的には悪循環をおこさないとしても、現実との合致しうる先行的言明の可能性が課題となるわけです。このシリーズで、「時間的パラドクス」といってきた難問が抱えている課題がそれです。
柄谷行人は、悪循環をもたらす自己言及性をもっぱら追及していました。ですが、私は、悪循環をもたらさない自己言及性の方に引き付けられていました。それが認識者の先行的な自己認識という課題と形式的に見て親近的であったからです。というのも、自己言及性は、あらかじめ認識が呈示され、それが認識者自身へと言及されるという形になっているからです――前回言っていた「あらかじめ」の自己言及です。そこで、自分が求めている先行的な自己認識の形式はこの「あらかじめ」の自己言及性の形式として表現できるのではないか、と思うようになったのです。
4
ですが、ここで障害が現われます。自己言及性は論理学的に禁止されていたのです。ホワイトヘッド・ラッセルの『プリンキピア・マテマティカ』では、それが別の意味で悪循環を引き起こすものとされ、「悪循環原理」で禁止されていたのです。その原理というのは、「或る集まりのすべて〔の成員〕を含むものは、何であれ、その集まりの一員であってはならない」(73)というものです。この原理は、形而上学に対しては破壊的でありました。というのも、この原理に従うなら、神はすべてのものの創造者として、すべてのものを含んだものでありますが、それ自身は、そこには含まれるのか、含まれないのかという問題が起こります。含まれない、とすると、神は「すべてのもの」の創造者ではありえないことになります。なぜなら、「すべてのもの」であるなら、神もまたそこに含まれていなければならないはずだからです。ですが、含まれるということになると――それが自己言及ですが――、神は、それ自身被造物の集合の外にありながら、その内にもあるということになってしまいます。「悪循環原理」は、これを禁じているわけです。つまり、「悪循環原理」は集合における自己言及を禁じているわけです。ですから、意味論的自己言及には当てはまらないわけですが、『プリンキピア』はさらに、悪循環原理を命題関数にまで及ぼしているのです。
命題関数については後でも触れますが、簡単にいいますと、たとえば、「ソクラテスは人間である」という命題を、主語+述語の文章形式ではなく、人間(x)で、x=ソクラテス、と数学的に表現するものです。人間(x)が命題関数(以下「関数」)で、ソクラテスは代入項で、人間(ソクラテス)が値となります。これは、人間(x)という命題とソクラテスという個的な対象との論理的関係の形式を表わすもので、先にお話ししたように、意味論と呼ばれる領域のものです。ですから本来、集合にかかわる自己言及ではないのですが、『プリンキピア』では、これも集合論的なパラドクスと捉えていたのです。それは関数を値の集合ととらえているためです。その場合、関数がそれ自身を値として含むということが、関数が値の集合の一部になるということを意味することになり、集合論的自己言及となるので、悪循環原理によって禁じられることになるわけです。そして結局、関数自身がその値に含まれないということは、「悪循環原理のもっとも基本的な例」(74)とされてしまいます。しかし、その後、論理学の内部では、関数とその指示対象との関係を、集合論ではなく、意味論として扱うとする動きが起こります。この間の事情については、柄谷行人が1983年の『隠喩としての建築』でこう説明していました。
ラッセルはパラドックスをさけるために、ロジカル・タ
イプ(論理的階梯)を設定した。それは、集合あるいはク
ラスとそのメンバーが非連続的であること、クラスはそれ
自身メンバーにはなれないし、メンバーはクラスになれな
いということである。クラスにおいて用いられる項は、メ
ンバーにおいて用いられる項とは、ちがった抽象レベル、
すなわちロジカル・タイプにある。それが混同されるとパ
ラドックスに陥るほかないので、ラッセルはその混同を“禁
止〟したのである。なおラムゼイは、ラッセルのあげたパ
ラドックスに二種類あることを指摘し、「自己自身を含む集
合」のパラドックスは、ロジカル・タイピングで解決でき
るが、「エピメニデスの(うそつきの)パラドックス」は言
葉のつかい方にかんするものだから、タイピングで解決す
べきではないし、論理体系内部で解決できないと批判した。
(75)
ということで、自己言及性は、集合論的と意味論的の二つに分けられることになったのですが、柄谷行人は、このことを知ったうえで、意味論的自己言及を集合論的自己言及へと吸収してしまいます。例えば、次にように言われています。
われわれは話を簡単にするために、自己言及的な形
式体系に生じるパラドックスを回避しようとするさま
ざまな企てを、ロジカル・タイピングと呼ぶことにす
る。(76)
これは事実上、意味論的自己言及は無視するということです。なぜなら、ラムゼイが言っていたのは、「嘘つきのパラドクス」はロジカル・タイピングでは解決できないということだったからです。この後、柄谷行人は、自己言及性を禁じている体系に、集合論的な自己言及性を導入することによって、内部から解体するという批評活動を展開します。
ですが、私は、意味論的自己言及性に可能性を見ていました.
といっても、論理学の側からは、私が求めているような、意味論的自己言及が提供されることはありませんでした。
たとえば、タルスキはその論文「真理の意味論的観点と意味論の基礎(1944年)で、嘘つきのパラドクスを扱っていますが、その際例文として挙げたのは次の文章です。
この論文の六四頁のうしろから三行目の文が真でない。
(77)
この文章は、主語部分をなす文――「この論文の六四頁のうしろから三行目」について、それが「真である」と言っている文で、この論文の中でタルスキが「メタ言語」と呼んだものです。主語部分を成すのは、それに対して「対象言語」と呼ばれることになります。つまり、この文章で問題にされているのは、「対象言語」と「メタ言語」の関係であって、自己言及性ではありません。仮に、自己言及性をこの文で問題にするならば、この文章自体が、文の中で指定されている場所の置かれているのでなければならないでしょう。そうであれば、文の内容は、文の存在に言及しうるものとなるからです。ですか、タルスキは、そのようには設定していません。実際のタルスキの議論を説明するのは煩瑣になるので止めますが、一つ指摘しておくことがあります。「対象言語」と「メタ言語」の区別は、それ自体重要ですが、タルスキでは、この先にあるのは「言語のヒエラルキー」なのです。
「対象言語」および「メタ言語」という語句は、単に相
対的な意味しかもっていないことに注意されたい。たとえ
ば、もともとの対象言語ではなく、そのメタ言語の文に当
てはまるような真理の観念が問題となる場合には、自動的
に、このメタ言語がその際の議論の対象言語となる。そし
て、この言語に対して真理を定義するためには、あたらし
いメタ言語、いわばより高次のメタ言語に訴えなければな
らない。このようにして、言語のヒエラルキーが形作られ
る。(78)
或る命題の真理を判断するためには、その命題とその命題の指示対象の現実の事態とをともに把握できる立場になければならないのですが。タルスキは、その立場をより「高次」に求めているわけです。そのため、原理的には、対象言語、メタ言語、メタ言語のメタ言語……というように、原理的に無限に進行してしまいます。ですが、命題とその指示対象とをともに把握できるのはなにもより高次のものである必要はありません。命題と指示対象の関係の外にいる者にとってならだれでも可能性としては捉えられうるからです。極端な場合、より低次であっても可能です。
すでにお話したように、タルスキの議論は、自己言及性とは直接関係ありませんでしたが、そもそも意味論的自己言及性は、少なくとも従来の論理学の内部では議論しえない性質のものです。というのも、論理学が扱う領域はそもそも概念の領域でありますが、概念の領域で自己言及性を唱えることは、結局、概念の階層的な体系やヒエラルキーや無限進行に陥るだけで、最終的に問われるのは、「第一のもの」とならざるをえないからです。ある概念がその概念自身を値としうるということは『プリンキピア』も言っていたように、おこりえないことで、自己言及性が論理学の内部で認められるには、おそらく、論理学は、概念の領域を存立させているもの、すなわち言語学で言うシニフィアンの領域を含みこまなければならないからです。ヴィトゲンシュタインの『論理‐哲学論』の冒頭部分は、そのための第一歩であったようにも思えます。なぜなら「〔論理〕絵も一つの事実である」(79)と言われているからです。そうであれば、言語学は、テキストの理論へと展開せざるをえないということになりますが、ともかく、概念だけを扱う論理学においては、自己言及性の論理は扱えないことは明らかです。その意味では、自己言及性という問題は、論理学の拡張を促す圧力を持っているということもできます。
5
ということで、意味論的自己言及を方法として獲得する経緯は、、批評テキストや言語学や論理学などとの戦いであったわけですが、とりわけ重要なのは、記号論理学における概念の関数表記です。
自己言及的存在論では、主語‐述語の文章構造から離脱して、
主語を代入項、述語を関数fx、主語+述語を値と表記します。これはただ言い方を替えたということにとどまりません。述語はfxのxは、数学的には「変数」と呼ばれますが、これを存在論的に解釈しなおします。変数とは不特定の代入項を意味しており、特定されていないなんらかの代入項を表わしていますが、これを、何らかの代入項がそこに挿入される場所と捉えなおすのです。或る記号論理学の入門書で、f( )という表記を見た覚えがありますが、これこそまさに存在論に見合った表記です。つまり、変数は、存在論的には、何らかの代入項が一時的に占有するために開かれた空域とみなされるわけです。すると、概念(関数)は、何らかの代入項が一時的に占有する場をあらかじめ拓いているものだということができます。つまり、概念(関数)とはいわば代入項が容れられる容れ物であるということになります。となると、「容器が持ち運べうる場所であるように、場所は動かしえない容器である」(80)というアリストテレスの言葉が想起されます。それとともに、逆に、場所とは関数であるという命題も引き出されえます。場所とは、何らかの物・者がそこに一時的に占有しうるという意味で関数である、と。たとえば、私が家にいるということは、私が家という場所=関数の代入項として存在しているということであり、私が散歩していることは、散歩道という関数=場所の代入項として存在していることだということができるわけです。総じて、私の存在は、関数の代入項として存在すること、すなわち値であるということになります。さらにいえば、世界内存在とは、現存在が世界という場所の代入項として存在することであり、その存在は値であるということになり、同時に世界は関数だということになるわけで、ハイデガーの主観的な世界概念――有意義性――を超えることができます。たとえば、私にとって、この道が親近的であろうとなかろうと、私の存在がこの道の代入項として存在する値であることには変わりないということになるからです。こうなれば、論理は言語領域からも解放され、事物の領域までをも含みこみ、存在の論理(「存在=論理」)となることになり、存在論は、存在=論理学となることになりえるのではないでしょうか。
現象学的探究からの転換
上に述べたような諸手段の獲得は、私自身の存在を反省的にとらえる、広い意味での現象学的な探究の途上でなされたことです。それがこうした現象学的探究からの転換を促したことは間違いありませんが、転換自体を可能にしたものではありません。転換自体を可能にしたのは、自分が背負っていた時間的パラドクスを、テキストに背負わせるという、いわばパラドクスの対象化でありました。「対象化」というと、フォイエルバッハの疎外としての対象化を想起させますが、疎外は、自己否定的な対象化でありました。つまり、対象化されたものが自己を否定する呈の対象化です。たとえば、「理想化」がその一例です。理想化は、なりたい自己を他者に対象化することですが、それによって、自己は理想ではないもの、それよりは劣るものとして把握されることになります。フォイエルバッハはこのメカニズムをキリスト教の神に適用し、それをさらにマルクスが、世俗化し、国家や貨幣を疎外と捉えるようになったとされています。
ですが、パラドクスの対象化は、そうした自己否定的な、自己を貶めるようなものではなく、むしろ逆に、自己自身を照らし返すような対象化です。というのも、テキストに対象化されたパラドクスは、もともと自分が背負ているパラドクスであり、対象化したからといって、自分がパラドクスから逃れえるわけではなく、逆に、自分が背負っているパラドクスと同じ形のパラドクスを、テキストのパラドクスとして目の前に見ることができるようになるからです。これは、他を媒介として自己を理解するという、間接的な自己言及性の形をとることですが、これを「自己言及的対象化」と呼んでいます。これによって、時間的パラドクスとの距離が生まれ、時間的パラドクスの解決の途が拓られます。
そもそも自分自身がパラドクスを背負っているかぎり、パラドクスは解きえないものでした。というのも、あらかじめ自分の存在を認識するという課題がパラドクスを形成するものであったのですが、それを課題として問う時点で、自分はすでに存在してしまっているので、あらかじめ自分の存在をとらえることはそもそも論理的にも不可能なのです。存在を問うときには、すでに問う自分は存在してしまっていて、存在に先立つことはできないからです。ハイデガーは、死は「追い越しえない」といいましたが、「追い越しえない」のはこの場合、存在です。ハイデガーは、不安においては無に立つことができるかのようなことを言っていますが(81)、それはあくまで気分的にであって、実際に客観的に無には立つことはできません。しかし、テキストならば、無に立つことはできます。テキストは、書かれて初めて存在することになるのですから、書かれる前には、当たり前ですが、存在していないのです。テキストを書くということは、そのつどテキストの無の前に立つことです。テキストの制作者は、その都度、テキストの存在に先だっているわけです。ですから、ここでは、あらかじめテキストの存在を捉えることがすくなくとも状況的には可能なわけです。むろん、あらかじめ捉えることができるのは、方向だけであり、それもぼんやりとしたものでしかないのですが、それでも、ひょっとしたらパラドクスの解決につながりうるものであるかもしれず、そうでないかもしれないですが、すくなくとも解決に向けて着手することはできるわけです。実際、後から見れば、この自己言及的対象化によって、パラドクスの解決の途が開かれたことは、間違いないと言うことができます。
ここまで言った以上、実際に解決を示すほかありませんが、それは自己言及的存在論の本論となるので、ここで序論的なお話は終わりにさせていただきます。次回からは本論に入る予定です。(2025.9.23)
(注)
(71) フッサール『論理学研究』第一巻第一章第六節(立松弘孝訳、みすず書房、1975年、p.32
(72) フッサール『ヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学』第 26
節(細谷恒夫・木田元訳、中央公論社 1974
(73) ホワイトヘッド・ラッセル『プリンキピア・マテマティカ序
論』岡本・戸田山・加地訳、哲学書房 1988年 p.130
(74) 同上、p.135
(75) 柄谷行人『隠喩としての建築』1983年、講談社、p.66
(76) 同上、p.67
(77) 坂本百大編『現代哲学基本論文集Ⅱ』勁草書房,1992年p.64
(78) 同上、p.68f
(79) 『論理哲学論』2.141(世界の名著70 中央公論社 1980年
p.336
(80) 『自然学』212a15(アリストテレス全集3 岩波書店1987年
P.138
(81) ハイデガー「形而上学とは何であるか」(1929年)邦訳ハイ
デッガー全集第9巻『道標』(1994年)
無の内へとそれ自身を投げ込んで保ちつつ、現有はそ
の都度既に、全体としての有るものを越えている。(p.138)