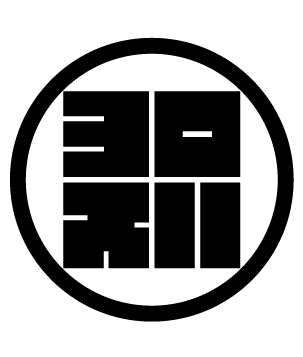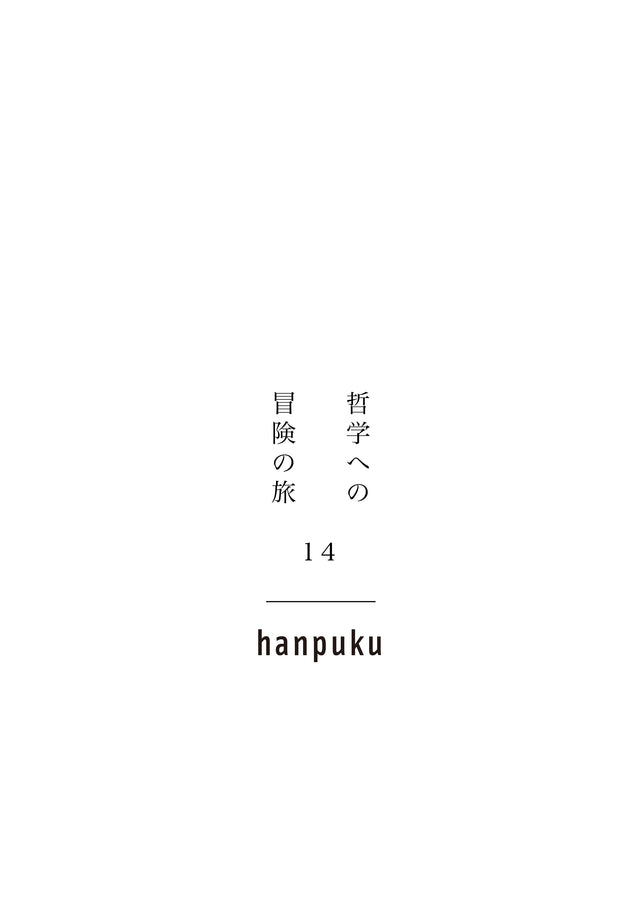
哲学への冒険の旅 14
哲学への冒険の旅14
14 歴史の中の時間的パラドクス五――ハイデガー8
「形式的なほのめかし」と「根源への還帰」
前回に続けて今回は段落2を読みます。
語義はすべてまだまったく形式的で、何の予断を与え
ともなく、ある方向を――これを固定することなく――
ほのめかすにすぎない。ひょっとしたら、この方向はその
途上で生のもっとも根源的な動機に還帰することにのみ
役立つのかもしれない。生の動機はたしかに理論的‐学問
的ではないが。根源学の真正な方法の問いはいずれも、根
源学自身の中にある「事象的」な問題であって、真正に追
跡すると、必然的に「根源」の中に通じている。(63)
「ひょっとしたら」という言葉は、解釈の冒険的な性格を垣間見せています。これは「言葉が偶然降りかかる」といわれていたことともつながっていて、哲学的関心を「根源的な動機」に向かわせるのに役立つものではあっても、かならずしも根源的な動機に通ずるものではないかもしれない、ということを含意しています。方法的に捉えるなら、これは自己言及性の一つのあり方です。自己言及性については「諸手段の獲得」について述べる回で説明しますが、ここで簡単に触れておきます。SZには、自己言及性という術語は使われていませんが、実質的に触れている箇所があります。
「証明における循環」は、存在の意味への問いにはふく
まれていない。とはいえたしかに、問われているもの(存
在)が、或る存在者の存在様態である問うことに「さかの
ぼって、あるいはあらかじめ関係づけられていること」は
注目にあたいする。問うことが、問われているものに本質
からしてかかわることは、存在の問いのもっとも固有な意
味にぞくするのである。(64)
問われていること(存在)が、問うこと、すなわち問うもののあり方に関係すること、これが自己言及的関係です。ここではその仕方が二つ挙げられています。ひとつは、「さかのぼって」の関係であり、他は「あらかじめ」の関係です。「さかのぼって」の関係は、後からの関係ですから、すでに関係づけられるもの――ここでは問うこと――が与えられている場合です。それに対して、「あらかじめ」の関係は、関係づけられるものがいまだ与えられていない場合で、関係づけられるものは、後から現実化されることになるわけです。その場合、問われていることがあらかじめ示され、それが何らかの対象において現実化されるという仕儀になります。この点からいえば、前回見た予描と現実化は、それ自体は自己言及性ではないにしても、「あらかじめの」自己言及性の動性と類似した動きだといえます。であれば、ハイデガー存在論では、自己言及性が潜在的に作動していて、それに導かれていたと考えることはできます。
それだけではありません。SZでは、相反するふたつの自己言及性がともに作動していることが次のような考察で明らかになります。
まず、「あらかじめ」の自己言及性の潜在的作動ですが、前回、現象学の即かつ対自的なあり方が、現象学の対象――人間的生――に「降りそそぐ」と言われていました。その際、現象学のあり方は、即かつ対自的なあり方を形式としてあらかじめ示すものとして使われています。つまり、対象――人間的生――をどう捉えるかを示す形式が現象学のあり方においてあらかじめ示されるという形になっています。ですから、その時点では、当然、人間的生は即かつ対自的なあり方としてはまだ規定されていないはずです。果たして人間的生が、即かつ対自的に存在するものとしてみずからを示すかどうかは、その時点では、わからないはずなのです。ですが、SZは、他方で、人間的生が即かつ対自的に存在することは、「一箇の事実」だといわれています。
平均的でばくぜんとしたこの存在了解は、一箇の事実で
ある。(65)
これは日常的現存在のことを言っているのですが、存在了解を有する存在者とは、存在しつつおのれが存在することがわかっている存在者のことです。SZでは、こうした存在者は「現存在」、その存在は「実存」と術語化されています。つまり、現存在と実存とは、ヘーゲル的にいえば「即かつ対自」的に存在するものおよびその存在のことです。ですから、一方では、人間的生が「即かつ対自」的に存在するものであることはいまだわからない状態なのに、他方では、それがすでに事実として与えられているものでもあることになるわけです。つまり、これから規定されるべきものが、すでに事実として与えられているということになります。重要な点なので繰り返しますが、これから解明されるべき人間的生の規定性(即かつ対自的存在)が、事実としてすでに与えられており、議論の前提にされてしまっているということです。当然、こうした議論は循環構造をなすことになります。
先の引用文の冒頭に、「証明における循環」などないという言葉がありましたが、それは現象学的存在論は、論証的な理論ではないということを言っているにすぎません。つまり、循環はあっても、それは「証明における循環」――いわゆる循環論法――ではなく、〈解釈における循環〉――「解釈学的循環」――だというわけです。そして、この循環は「抜けでる」べきものではなく、むしろ「入りこむ」べきものだとされています(66)。
循環構造が導入されたのは、1919年の『哲学の理念』においてです。以前、認識論から存在論への転換について見たときに触れた個所です。そこではまずこう言われていました。
まず措定されるべきはずのまさしくそのことが、前提と
されており、前提とされなければならない。(67)
措定されるべきものが前提されているということは、論証でいえば循環論証です。論証的理論においては固く禁じされているものです。そこで、ハイデガーは、以前見たように、理論的な領域以前の領域、環世界的な体験の領域に立ちかえり、その領域――人間的生の領域――で源学を設立しようとしました。それは、その領域においてなら、措定されるべきものが前提されているという循環が成り立つということです。ここに解釈学的循環の始まりがあります。すなわち、人間的生の領域は、循環が成り立つ領域としてあらかじめ見られているのです。この転換は同時に認識論から存在論への転換であったわけですから、ハイデガーは、そもそも存在論を循環構造が成立しうる理論として見ていたということになります。
このようにして導入された循環構造においては、あらかじめ根源について示された形式は、根源に「必然的に」通ずる、ということになります。解釈の循環構造を前提とすれば、「解釈学的状況」においてあらかじめ経験から獲得された概念(形式)が生の根源に行き着いてもおかしくはないどころか、「必然的」であるからです。
ですから、ハイデガーは、一方で、解釈は「ひょっとしたら」根源に行き着くかもしれないといいながら、他方では、必然的に行き着くんだ、と反対のことを言っていることになります。どちらかではなく、両方だというのです。これは論理的には矛盾でありますが、こうした矛盾を生まれるのはなぜでしょうか。
学問論的に見れば、解釈の循環構造は、すでに見たように、根拠づけられる学がみずから根拠づける学たらんとすることに由来することです。それに対して、「偶然的に降りかかる」という形態で形式を先立てることは、いかにも突飛な思いつきでしかないように見えます。なぜそんなものが必要なのでしょうか。推察するに、経験的に得られた概念を根拠づけうるものとして、循環構造の外から与えられる根拠が求められたからではないでしょうか。というのも、解釈の循環構造だけでは理論は成り立ちえないからです。仮に循環構造だけで理論を形成するとすれば、比喩的にいえば、発掘された土器をあらかじめ埋め戻したうえで発掘するようなものになってしまうからです。
こう考えてくると、先の学問論的な分析は充分ではなかったことに気づきます。先の分析では、循環構造が導き出されたにすぎないし、それだけなら、特定科学における関数の形成においてもいえることで、根拠づけられる学がまた根拠づける学になるということにまで及んでいないからです。後者を可能にするためには、経験的に形成される関数を根拠づける何か、つまり循環構造を越えて経験的な関数を根拠づける根拠がなければならないわけです。
であれば、現象学の即かつ対自的なあり方が、現象学の対象に「降りかかる」という不合理的な構造も、この必要を充足させるものとして、納得はできないにしても、理解はできます。現象学は、現象学の主題対象である人間的生に対しては外的であるからです。
この外部性は、自己自身を理解する現象学がテキストとして存在すると仮定すればすぐわかることで、その場合それは、人間的生を対象とする現象学とは異なるテキストとして実在することになるはずだからです。というのも、その場合、現象学の対象はそれ自身であることになるからです。そう考えると、「自己自身の中に降りかかって還帰する」というのも、そうしたそれ自身独立した学としての現象学のことを言っているのかもしれません。その場合は、「源逆説性」にぶつかって、結局、根拠づける学から始めるという途は放棄されることになるわけですから、解釈としてはこの方が妥当性をもつと思われます。だからといって、先の解釈が間違っていたというわけではありません。先の解釈は「源学」の視点に立ったものだからです。それに対して今回の解釈は「根源学」の視点に立ったものです。しかも先に見たように、循環構造(源学)は、1919年1月~4月に行われた『哲学の理念』講義の中で呈示されていたもので、「根源学」は1919~20年の冬学期での講義で、後から提示されたものです。こうした経緯も、「偶然言葉が降りかかる」は、循環構造に付加されたものだと考えさせる状況証拠になります。
しかし、それだけではまだ十分ではありません。なぜ「即かつ対自」という単なる存在形式が「降りかかるのか」? その理由は、根源学の試みは「源逆説性」に直面し挫折するという点にあります。その場合、根源学としての現象学は存在することはなく、したがって、理念を根拠づける関数を提供することもないわけです。ですが、他方で、解釈の循環構造において用いられる理念が外から根拠づけられる必要は依然としてありつづけます。このせめぎあいの中で、不在の根源学の名において、解釈の循環構造において用いられる理念を根拠づける関数が見いだされることになったと考えることができます。その場合、その関数は、権利上、循環構造に先立っているので、根源に行き着くかどうかはわからないので、「ひょっとしたら」行き着くからもしれない、ということになります。しかし、同時に、その関数は、循環構造の側の要請に応えるものとならざるを得ません。そうであれば、その関数は循環構造とは独立した根拠づけをもたないということになります。独立した根拠づけは、「源逆説性」(時間的パラドクス)を解決することによってでしか与えられないからです。実際、『存在と時間』には次のような記述があります。
「根拠」は意味としてのみ接近可能となる――たとえ根
拠そのものが没意味性の深淵であろうと――…。(68)
根拠が「没意味性の深淵」であるとはどういうことでしょうか。循環構造の中では根拠として機能するが、それ自体で見れば、「没意味性」であるということです。具体的にいうなら、1919/20年の時点では、それは「即かつ対自的存在」のことを指しますが、この理念は、おのれ自身を理解する現象学の理念ですが、しかし、理念として語られているだけで、そういう現象学は実際には形成されません。「源逆説性」を乗り越えることができないからです。それはこの理念を根拠づけることができないということを意味します。しかし、ハイデガーは、この理念を、根拠づけられないまま、形式として人間的生の探究の方向づけとして機能させるわけです。それは、無‐根拠な理念を根拠として用いるということです。しかもその理念は、先に見たように、すでに事実として現象学が前提としていたものでもあるのです。つまり、その理念は、現象学の対象である人間的生のあり方の側からの要請に応えているものでもあったわけです。
これが、根拠づけられる学がそれ自身根拠づける学になるということにおいて行われていることです。すなわち、不在の根拠づける学の存在形式が根拠づけられる学のうちに引き込まれて先行する理念として機能させられているということ、これが、現存在の存在論を基礎的存在論とする、ということの実際の姿です。ここで冒険の旅7の冒頭に引用した言葉が想起されます。
オントロギーは、基礎的部門として現存在の分析論をも
つ。このことには同時に、オントロギーはそれ自身純粋に
オントローギッシュには基礎づけられえない、ということ
が含まれる。オントロギー自身を可能にすることは、或る
一つの有るものすなわちオンティッシュなものへ、つまり
現存在へと差し戻されるのである。(69)
ここではまず現存在の分析論が「基礎的部門」――SZでは、「基礎的存在論」と言われているもの――だといわれます。続いて、それは、おのれ自身を根拠づける存在論は不可能であるというだけでなく、それを「含んでいる」とされています。これは二つの意味を持っています。ひとつは、おのれ自身を根拠づける存在論――つまり根源学としての存在論――は不可能とされていることで、これは「源逆説性」――時間的パラドクス――を解決することができない、とすることです。それが不可能であることが、現存在の分析論への移行の理由となっています。そして、その移行の形は「差し戻し」と表現されています。つまり、本来なら根源学から始めるべきところを、それが不可能だから、根拠づけられる学へと「差し戻される」ということです。ですが、それだけでは「含まれている」といわれる意味がわかりません。「含まれる」ということは、現存在の分析論の外ではなく、〈内にある〉ということです。つまり、不在の根源学が不可能性のゆえに差し戻された現存在の分析論の内にあるということです。それはおのれ自身を根拠づけるという根源学の理念が、形式として現存在の解釈を方向づけるものとして機能させている、ということです。さらにいえば、それは現存在そのものを〈おのれ自身を根拠づけるもの〉とすることを意味します。つまり、現存在そのもののうちに「根源」があるということになります。SZの中では「良心の呼び声」においてそれが現実化されています。良心の呼び声は、「私のうちから私を超えて到来し、私に向けて発せられている」ものだとされています(70)。
根源はいまや現存在のうちに見いだされ、それを主題化する分析論が根源的な学(基礎存在論)となるわけです。
以上のように、はじめに形式的にいわれたことを、具体的な形で見直すことができたので、長くなったハイデガー論もここで終わりにします。むろん、ハイデガー論としてはほんの入口にすぎませんが、根源学を断念したあとで、どういう途に向かったかという当初の目的は或る程度果たせたと思います。同時に、「歴史の中のパラドクス」のシリーズも終わりにします。というのは、この議論の過程で、ハイデガーのテキストには、自己言及性が潜在的に作動しているということが見えたからです。このことは、すでに自己言及性を方法としてもつものとして見ているからいえることです。私が作っている存在論では、存在論に自己言及性を導入するということから議論が始められます。それを「自己言及的存在論」(略称SRO)と呼んでいます。ですから、そこでは自己言及性は顕わになっています。このことは、ハイデガーのテキストとの関係で歴史的にみれば、ハイデガーのテキストにおいては潜在化されていた自己言及性が、私自身のテキストにおいては顕在化されている、と自己理解されることになります。私のテキストの歴史的な位置づけが得られたわけで、この後は自己言及的存在論にかかわる話になります。
自己言及性という概念は戦略的な概念で、これが根源学を可能にするもっとも重要な概念のひとつであります。ハイデガーは、「突破する手段が何一つない」として根源学を断念していますが、自己言及性をはじめとして私に入手しえた諸手段とその経緯について、次回に話します。ということで、「歴史の中の時間的パラドクス」のシリーズはこれまでとし、次回は諸手段の獲得についてお話しする予定です。(2025.8.18)
(注)
(63) GP.第1節,p.5
(64) SZ.第2節,1-p.99,d.22
(65) SZ.第2節,1-p.86,d.14
(66) SZ.第32節,2-p.231,d.431
(67) ID.§18,p.103
(68) SZ.第32節,2-p.227f,d.429
(69) 「冒険の旅7」(1)参照
(70) SZ.第57節,3-243,d.823