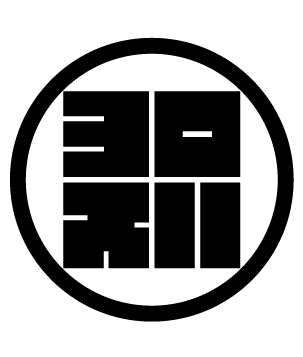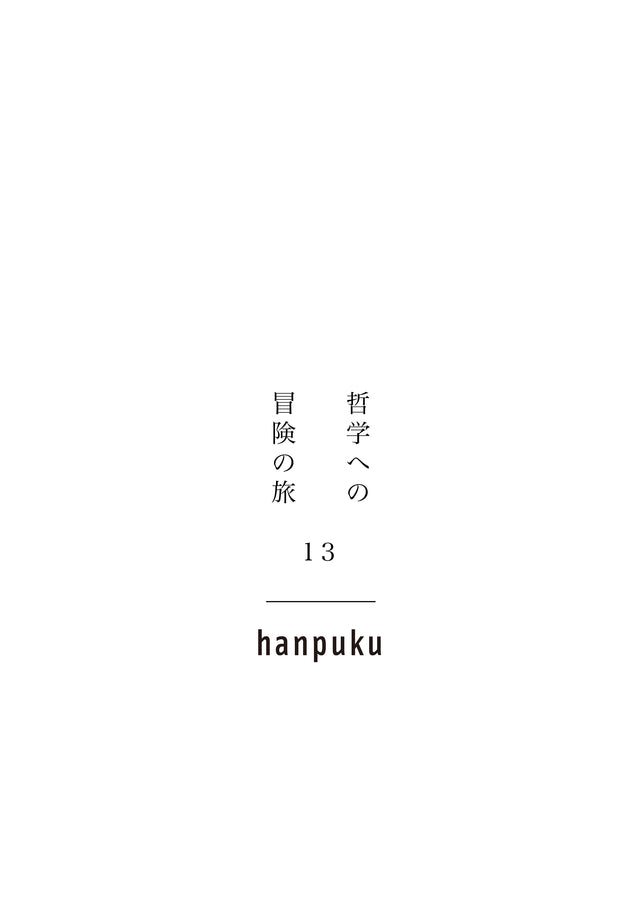
哲学への冒険の旅 13
哲学への冒険の旅 13 vers.2
13 歴史の中の時間的パラドクス五――ハイデガー7
一 現実化の予描と循環構造
前回に続いて今回は「根源学の理念Ⅱ」を読むことにします。「Ⅰ」では、根拠づける学から根拠づけられる学への移動を見ました。ですが、そもそもの問題は、現存在の存在論を基礎的存在論とする、ということを明らかにすることにありました。ですから、まだ当初の目標には達していないわけです。「Ⅱ」において見られるのはこのことですが、まずはこの問題を学問論的に分析しておきます。
現存在の存在論を基礎的存在論とするということは、学問論的には、根拠づけられる学が、自ら根拠づける学になるということですが、それは具体的にはどういうことでしょうか? それを知るためには、根拠づける学が根拠づけられる学に何を提供するのかを見なければなりません。むろん、その答えは明らかで、根拠を提供するわけです。では、根拠とは何かといえば、それは理念的な関数です。ですから、根拠づける学が不在であれば、根拠づけられる学は、根拠となる関数が与えられないということです。ではどうするか? 途は大きく分けると二つあります。一つは、根拠をもたないまま根拠づけられる学を形成することで、その場合には、主題対象の研究は、一定の方向性を持たずに、対象に引きずられたものとなるでしょう。もう一つの途は、根拠づけられる学がみずから根拠を形成するという場合です。この場合は、根拠づけられる学が、何らかの仕方でみずから理念となる関数を形成することになりますが、そこでまた二つの途に分かれます。ひとつは、根拠づけられる学は何らか特定の領域に属するものを対象とする学ですが、そうした特定科学のままで、たとえば理念型のようなものを立てる場合です。もうひとつは、根拠づけられる学が、みずから理念的関数を形成して、それ自身根拠づける学でもあらんとすることで、ハイデガーの場合はこれです。ですが、その場合、形成される関数は、前回でも見たように、理性的に関数が形成されるわけではなく、主題対象の経験にもとづいて関数が形成されます。するとどういうことになるかといえば、主題対象の経験にもとづいて形成された関数にもとづいて対象が解釈されるということになるわけです。全体としてみれば、この場合、解釈は循環構造をもつことになります。つまり、根拠づけられる学がそれ自身また根拠づける学になろうとするならば、論理必然的に解釈は循環構造になる、ということです。このことを念頭に置いたうえで「根源学の理念Ⅱ」を読むことにします。
「根源学の理念Ⅱ」は三つの段落で成り立っていますが、ここで取り上げるのは、段落1,2です。3にはベルクソンへの言及が見られます。いずれベルクソン哲学との対決もなされねばならないと考えてはいますが、そこに踏み込むことはここでは避けます。ということで、まず段落1から見てゆきます。
根源学(Ⅱ)の理念は、根源学が具体的に生き生きと現
実化する仕方を自ら予描する。つまり、現実化の仕方は
「学」の理念の中に取り入れられているのである。認識―
―根源学において――そして根源学において根源的に―
―問題といったようなもの――方法がある。これがどうい
うことかを、根源学自身が源学として理解にもたらす必要
がある。そのような源学としての根源学は、その源学的問
題性や方法性を外から、根源学とは異質なものから、特殊
学から押しつけられることを許してはならないのであっ
て、根源自身に、根源から、根源的な産出やたえず更新す
べき実証や明証的な傾向充実において、生ずるのでなけれ
ばならない。このことはさらに、学の理念――認識――認
識の表現――明証――証明や根拠づけ様式そのものにま
で及ぶ。いわば理念型としての特別の個別学ではないにせ
よ、形式化された普遍化ないしその他の普遍化が学の理念
の根底に置かれる、というわけではないのである。(54)
ここでは二つのことが言われています。(1)現実化の仕方を予描するということ、(2)根源学は他に依存するものではないので、理念や問題や方法などについては自分自身で理解するのでなければならない、ということです。ここではとくに(1)について考察します。
根源学がじぶんを現実化する仕方をあらかじめ描きだすということですが、これがどういうことかは実際に見ればすぐわかることです。というのも、驚くべきことに、ここであらかじめ言われていることが、7年後の『存在と時間』で現実化されているのです。その証拠として第一部第一篇「現存在の予備的な基礎的分析」の冒頭節の一部を引いておきます。
存在の意味への問いにおいて第一次的に問いかけられ
ているものは、現存在という性格を有する存在者である。
現存在の予備的な実存論的分析論は、それ自身、その特
性におうじて、呈示をあらかじめ素描しておくことが必要
であり、一見したところその分析論と並行しているかにみ
えるいくつかの探究から〔分析論を〕境界づけておくが必
要である(第一章)。探究のために確定された着手点を堅
持しながら、現存在について一箇の基礎的構造が発掘され
ねばならない。それが世界‐内‐存在である(第二章)。
(以下省略)(55)
「予備的基礎分析」は、第一章から第六章までありますが、上に見たように、そこで扱われる内容があらかじめ素描されて紹介されるわけです。これはここだけではなく第二篇の冒頭節(第45節)でも見られます。しかもそこでは、あらかじめ素描すること自体が、「解釈学的状況」(56)として解明されています。この点についてはあとでのべます。
さらに章のレベルでも、第一篇第三章以下各章、第二篇第一章以下各章で、現実化の予描が記されています。つまり、予描は、SZの論述のスタイルになっているわけです。しかも、このスタイルは、7年前に予描されたことの現実化であったのです。ということは、1919/20の『現象学の根本問題』から1927年の『存在と時間』までを一つの大きな著作と考えるなら、あらかじめの予描とその現実化という構造それ自体が、予描され現実化されるという二重構造になっているということです。
ですが、そもそも予描と現実化という構造自体が循環構造をあらわしています。というのも、予描というのは、後で詳しく叙述される内容の形式的な概略をあらかじめ描くということで、すでに知られていることをあらかじめ示すものでしかないからです。先送りした「解釈学的状況」もまたこれにかかわっています。
現実化の仕方をあらかじめ描き出すことができるためには、何らかの方法で、形式的なものがまず把握されねばならないわけですが、「解釈学的状況」はその方法を示すものです。具体的には、根本経験のなかで「あらかじめ持ち」「あらかじめ見」「あらかじめ掴む」によってあらかじめ対象の存在構造を概念的に構成することです。この方法で、あらかじめ概念が形成されるのであれば、解釈の全体は、主題対象に関する経験からあらかじめ把握される概念によって主題対象を解釈するということになります。いいかえれば、これから解釈されるべきものがあらかじめ前提されているという構造、すなわち循環構造になるわけです。実際、SZにおける探究の仕方が循環構造をもつことは、次の言葉が証示しています。
探しもとめることとして、問うことは、探しもとめられ
ているものの側から先だってみちびかれている必要があ
る。(57)
ふんわりした言い回しですが、存在の意味は探しもとめられるものでありますが、それがあらかじめ把握されている必要があるということです。ただどのようにしてあらかじめ把握できるのかについては上では言われていませんが、すでに見たように、それは「解釈学的状況」として経験からあらかじめ把握されたものであるわけです。つまり、SZにおける探究は、循環構造をもつということを表明しているわけです。
解釈のこのような循環構造は、根拠づけられる学がそれ自身根拠づける学となる場合に必然的に生ずるものであることはすでに分析的に示したところですが、上に見たように、ハイデガーのテキスト自身が或る形態の姿をとって、それを自ら示しているわけです。その意味でこれは学問論的な解釈の妥当性を証しているものと受け取れますが、それだけでなくまた、解釈の循環構造は、SZの学問論的な位置づけによって根拠づけられることをも示すものです。これが重要な点であることは、他方でハイデガーが、解釈における循環構造をそもそも現存在の存在構造に根ざしているとしているからです。
理解における「循環」は、意味の構造にぞくしている。
そして、意味というこの現象は、現存在の実存論的体制の
うちに、つまり解釈しつつ理解することのうちに根ざして
いる。或る存在者――その存在者にとっては、世界内存在
として、じぶんの存在そのものが問題である――は存在論
的に循環構造を有しているのである。(58)
学問論的に見れば、これは大きな間違いで、循環構造は、根拠づけられる学が根拠づける学であろうとすること――SZに即していえば、現存在の分析論を基礎的存在論とすること――に由来することです。ですから、この構造は現存在の存在規定とは関係ないのです。であるなら、現存在の存在本質の規定は、解釈学的循環からは切り離して別になされねばならないということになります。いいかえれば、現存在の存在本質の規定は、やり直さねばならないということになります。そう考えると、『存在と時間」の生成史の中に、現存在の存在の意味を時間性と規定する以前の段階に、別の見方が示されていたことに思い至ります。
時間という概念が現存在の存在を規定する概念として呈示されるのは1924年の講演「時間」で、1925年の「カッセル講演」では、「現存在であるということは時間である〔時間を存在すること〕である」(59)と言われ、この視点に立って古代ギリシャ哲学における「ウーシア」が時間論的に解釈されます。
驚くべきことに、ギリシャ人は存在するということを時
間から解釈しました。つまり、ウーシアは現前性、現在を
意味しています。(60)
ですが、それ以前の『アリストテレスの現象学的解釈』(通称「ナトルプ報告」(1923年)では、
アリストテレスにとってそもそも存在とは何の謂いなの
か。それはいかにして近づいてゆくことができ、捉えられ、
規定されうるのか。根源的な存在意味が汲まれている対象
領域は、関わり合いにおいて使用される製作された対象の
領域である。すなわち、理論的な観察において客観的事物
として捉えられた対象様態たる物の存在領域ではなく、製
作したり用務を果たしたり使用したりする関わり合いにお
いて出会われる世界が、根源的な存在経験の目指し向かう
先である(61)。
と言われていました。繰り返しますが、物を作ったり使用したりするあり方とそこで出会われる世界をこそ目指すべきものだとされているわけです。ここに解釈学的循環につながれた存在解釈とは異なる解釈の可能性があったということが言えます。むろん、ハイデガー自身は、ここから時間論的解釈の方へと向かってしまいます。作ったり使用したりする世界とは仕事の世界で、仕事の世界は、形式に関していえば繰り返しの世界ですから、ここから解釈が反復する時間性に向かうのもまったく理解できないこととは言えません。ですが、そうした解釈の方向へと向かわせているのは、解釈学的循環へのあらかじめの方向づけによるものであろうと思われます。それはともかく、すくなくとも生成の途上では、解釈学的循環とは切り離された形での現存在の存在解釈の可能性がハイデガーのもとにもあったということは歴史的事実であり、それは注目に値します。『ナトルプ報告』には、すでに時間論的な解釈に向かう姿勢は現われていますが、SZになると、「措定されるべきものが前提されている」という循環性が、明確に時間的に表現されるに至っています。
先駆することにあって現存在はみずからを、もっとも固
有な存在可能へと先んじて反復する。(62)
「措定」は時間的には「先んずる」ことですが、それが同時に「すでに」(前提されているもの)の「反復」であるとされているわけです。つまり、「措定されるべきものが前提されている」というテーゼがここでは時間化されているわけです。こうして解釈学的循環の構造は、時間概念に結びつけられることで、人間的生の存在構造になるわけです。逆にいえば、時間概念を外してみれば、解釈学的循環と人間的生の存在構造とは切り離されることになるわけです。
次回は段落2に移ります。
(注)
(54) GP.第1節,p.4f
(55) SZ.1-p.221,d.124
(56) SZ.3-p.60,d.684
(57) SZ.第2節,1-p.85,d.14
(58) SZ.第32節,2-p.232,d.432
(59) 『ハイデッガー カッセル講演』後藤嘉也訳,
平凡社 2006年 p.101
(60) 同上p.117
(61) 『アリストテレスの現象学的解釈』高田珠樹訳 平凡社
2008年 p.052f
(62) SZ.第68節a,4-p.77,d.1001