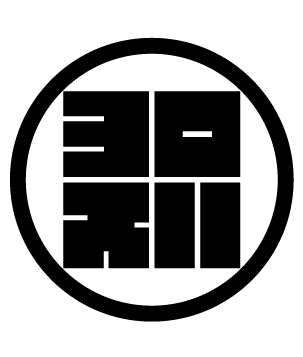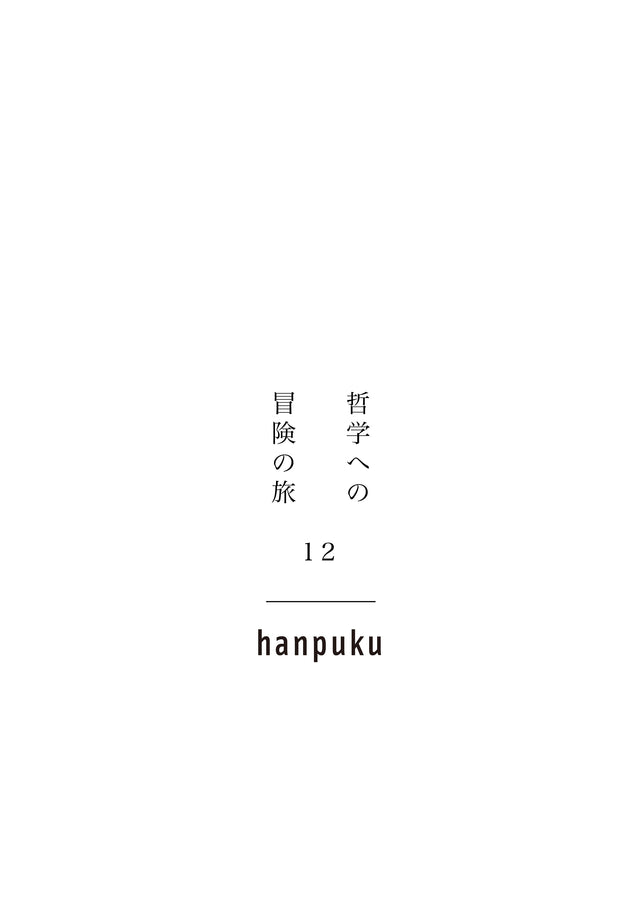
哲学への冒険の旅 12
哲学への冒険の旅 12
12 歴史の中の「時間的パラドクス」五――ハイデガー6
一 解釈学的方法
今回から、現存在の存在論を基礎的存在論にする、という点について見てゆきます。これについては、すでに冒険の旅10で、根源学の理念の観点から、根拠づけられるあり方に根拠づけるあり方を取り戻すこととして説明しておきましたが、実は驚いたことに、そうした説明に適合するような記述がハイデガーのテキストの中にもあったのです。一つの発見でした。興奮のあまり、しばらくは書けなくなったほどです。
1919年の緊急講義(1~4月)のあと、その年の夏学期では新カント派の価値哲学を扱った講義が行われ、冬学期に『現象学の根本問題』という講義が行われます(43)。その「予備考察」第1節のa「根源学の理念の意味」にその記述はありました。以前読んだときには、何を意味するのかまったくわかりませんでしたが、今回は、すでに根源学の複合存在の分析を行っていたことで、はじめてその意味を理解することができました。そこでは、認識論からの転換を行った後、根源学を取り戻す現象学――すなわち源学――がどういうものかが、根源学(Ursprungswissenschaft)(44)の観点から捉えられ、根源学の理念(Ⅰ、Ⅱ)として記されています。しかし、その前に第一節の冒頭部分にも重要なことが、やや不可解な形で呈示されているので、まずはそれから見てゆくことにします。
「現象学の根本問題」――もっとも火急で決して消し去ることのできない、最も根源的で最も究極的な現象学の根本問題は、現象学自身にとっての現象学自身である。
現象学こそ源学そのもの〈die Urwissenschaft〉、精神即かつ対自――「生即かつ対自」――の絶対的根源の学である。差し当たっては、空虚な言葉で、まったく特定の、真正に絶対的に証示しうる何かを意味すると自称するにすぎない。
――言葉自体は、「偶然ふりかかってくるもの」。そこで、現象学はそれ自身、生の表明として現象学の対象の中に、自己自身の中に、降りかかって還帰する。これは、現象学にまつわる欠陥でもなければ、現象学を煩わせる障害でもなく、現象学の問や解答の仕方の生き生きとした活性、「巡り合わせFügung」の特殊な性格であり、現象学の問題性の経過形式の長所である。(45)
一読ちんぷんかんぷんだと思いますが、実はこれ、解釈学の方法について言っているのです。細かく見てゆきます。まず冒頭では、現象学の根本問題は、現象学自身にとっての現象学だと言われています。つまり、自己理解する現象学、それが現象学の根本問題だということです。次に、そういう現象学、すなわち自己理解する現象学が源学だといわれています。そして、自己理解する現象学のあり方が、ヘーゲルの術語を借りて「即かつ対自」だといわれています。そのうえで、そう言う言葉は、空虚な言葉で、特定の何かを指しているわけではなく、そう自称しているにすぎない、と言われます。つまり、それは単なる形式を表す言葉で、内実はないということです。そういう内実のない形式を表す言葉は、何らかの特定の何かにとっては、「偶然降りかかってくるもの」でしかないと次にいわれます。それを受けて、次になんと、現象学の即かつ対自というあり方、単なる形式を表わす言葉が、現象学の対象に「降りかかって還帰する」といわれます。現象学の対象とは、むろん、何らかの特定のもの、すなわちこの場合、人間的生のことです。ですから、即かつ対自という形式を表わす言葉が、人間的生に降りかかるというわけですが、これは、人間的生を、即かつ対自的に存在するものとして解釈するという、解釈の方向づけをおこなうということです。まず形式が先にanzeigen(「告示」では強すぎますが、「暗示」では弱すぎて、「標示」ではよそよそしく感じられてしまうので、訳が難しいのですが)され、それに方向づけられて対象(人間的生)を解釈するということです。むろん、形式が偶然降りかかってくるのだとすれば、人間的生がそれに適合したあり方を自ら示すかどうかはわかりません。ですから、これは一つの賭けのようなものです。うまくいけば、問いと答えが「巡り合う」ことになるわけです。カントの術語を用いれば、これは「企投」です。ハイデガーの現象学は、形式(意味)をあらかじめ立て、それを対象に企投し、対象にそれを示させるという方法――これが解釈学的な方法といわれるものですが(46)――、この方法がここで呈示されているわけです。奇妙に思われるのは、形式がまず学のあり方において呈示され、それが、学の対象に降りかかって、対象の探究を方向づける、という形をとっていることです。学のあり方は、ここでは、ただ解釈の方向づけをするための形式のあらかじめの告知をしているにすぎません。ですが、もっと驚くべきことに、ここで言われていることがSZにおいて現実化されていることです。それを見てみましょう。
SZは存在の意味への問いを呈示していますが、その問いは、古代ギリシャにおいて提起された問いを反復するものとされています。外面的に見ても、巻頭、プラトンの『ソフィスト』からの引用が置かれていることがそのことを示していますが、それだけでなく、第一節の表題では「存在への問いを明示的に反復することの必要性」と言われておりますし、本文の中でもこう言われています。
私たちはそのつどすでに或る存在了解のなかで生き、しかも同時に、存在の意味は暗がりのうちに蔽われている。このことが証明するのは、「存在」の意味への問いを反復することの、原則的な必然性なのである。(47)
つまり、SZは、古代ギリシャの哲学との歴史的関係の中にあり、その歴史的関係の内容は「反復」だということです。つまり、これはSZと名付けられた著作の歴史的なあり方をあらわしているわけです。
ですが、第二篇第五章(時間性と歴史性」では、SZの主題対象である人間-現存在に関して、歴史性が問われ、しかもそれが「反復」として規定されます。
決意性が、それに向けてみずから投企する可能性の由来を明示的に知っていることはかならずしも必要ではない。
それでもなお現存在の時間性のうちに、しかもそのうちに含まれている可能性は、つぎのようなものなのである。
つまり、現存在がそれに向けてじぶんを投企する実存的な存在可能を、伝承された現存在了解から明示的に取り出してくる可能性である。
じぶんへと立ちかえり、みずからを伝承する決意性はそのとき、受けつがれてきた実存可能性を反復することであるはこびとなる。
反復とは明示的な伝承のこと、すなわち現にそこに既在していた現存在のさまざまな可能性への還帰にほかならない。(48)
こう見てみるとお分かりになると思いますが、学(SZ)の歴史的なあり方が形式的に先示しているものが、学の対象である現存在の歴史性において具体的に証示される、という形になっているわけです。
以上は、「降りかかって還帰する」を、解釈学の方法としてとらえた解釈です。このやり方の持つ意味は、ヘーゲルの場合と比べることで際立ちます。ヘーゲルの場合は、「即かつ対自」というあり方は、即自‐対自‐即かつ対自という弁証法的な生成の成果でありますが、ハイデガーの場合は、現存在の存在をいきなり「即かつ対自」というあり方として規定する、ということになるわけです(49)。これはあとで、歴史俯瞰的に見たとき、大変興味深い光景を現出させます。
二 根拠づけられる学の障害としての根拠づける学
では次に「根源学の理念Ⅰ、Ⅱ」を見てゆきます。まず「根源学の理念Ⅰ」から見てゆきます。Ⅰは一つの段落を成していますが、便宜上、前半・後半の二つに分けて引用します。前半は以下のとおりです。
根源学<Ursprungswissenschaft>(Ⅰ)の理念が自らに与える意味は、根源学が自らの課題を産出することによって、また、根源学の最も固有な動機が「課題」を研究しつつ解明し解決することにおいて真正に効果を発揮することによって、初めて根源学自身の根源的な理解にいたるということである。これによって一方で標示されている<angezeigt>のは、現象学がある逆(・)説(・)性(・)と絶え間なく戦(・)う(・)ということだが、この逆説性を我々は、生即かつ対自の源逆説性<Urparadoxie>として理解することになろう。(50)
要約するなら、根源学は、自らの課題を産出し、それを解明し、解決することで、はじめて根源学自身の理解にいたりうるものだが、これが告げ知らしめているのは、根源学としての現象学が、生即かつ対自の〈源逆説性〉と絶え間なく戦わねばならないことになる、というのです。
ここでは二つのことが言われています。ひとつは、根源学の自己理解は自らが産出した課題の解決によってはじめて達しうるということで、もうひとつはその解決は、即かつ対自の〈源逆説性〉との戦いであるということです。ここでヘーゲルの場合を想起しつつ、歴史俯瞰的な見方をするなら、ヘーゲルは、時間的パラドクスの解決を断念して、弁証法へと向かったわけですが、ハイデガーは、まさに弁証法的生成を廃棄しているために、逆にハイデガーがここで「源逆説性」と呼んでいる時間的パラドクスとの戦いのなかに引き戻されていると見えるわけです。むろん、それぞれパラドクスを構成する内容は異なっているので、単純に元に戻ったというわけではありません。ヘーゲルは、才能をあらかじめ把握しようとことでパラドクスに陥ったのですが、ハイデガーはおのれ自身を根拠づけようとしてパラドクスに陥ったのでした。ここに差異が現れていますが、そもそも「即かつ対自」というあり方そのもののうちにパラドクスが含まれています。即自と対自とは相反的な関係にあります。つまり、互いに対立的な二つのあり方を含んだ存在というものがそもそも逆説的なわけです。この逆説的な存在をどう説明することができるのか、それが問われているわけです。ヘーゲルは、弁証法的な生成として、一度否定した即自を取り戻すことという形で、この逆説を解決しているわけですが、ハイデガーは、ヘーゲル的な解決を採用しませんでした。まさにそのために、逆説そのものに陥ることになっているわけです。そして、解決は断念されました。この断念は、より詳しく見るなら、前にも言ったように、根拠づける学から始めることの断念でありました。そこで、根拠づけられる学へと移行し、根拠づけられる学から始めるという途を採ったのでした。
ここで段落の後半部分を読むことにします。
他方ではしかし、源学の理念から次のような根本指令が生ずる。すなわち、源学自身はその活性化の仕方を抽象的な概念的構築において案(・)‐出(・)し(・)た(・)り(・)、あるいは形式的な秩序概念において――結果を客観化しつつ――源学を停止させようとするいかなる試みも――つまり、根源の中に生き生きと還帰し、根源から生き生きと現れ出てゆくこと(比喩的な言い方だが)から抜け出そうとするいかなる試みも――容赦なく却下すべしという根本指令である。言い換えれば、源学自身の中で働いている「傾向」を真正に、具体的に実現し、遂行する(従う)ことによってのみ、源学自身やそのもっとも固有な問題領域へと導かれるのだが、この問題領域が語りかけてくるのは、それが現象学の根本傾向そのものの中にとりいれられているときのみである。源学は、自己を真正に表明することによって初めて、自己自身を表明として表明しつつ理解することができる。(51)
源学とは、すでに見てきたように、根源領域としての人間的生を主題対象とする存在論的な現象学のことで、認識論から転換した存在論であり、かつ根源づける学の断念から移動してきた根拠づけられる学のことでした。ですから、源学という術語は、この後半部分が、根拠づける学を論じている前半部分から根拠づけられる学へと移動していることを表しています。もっとも、その移動が源逆説性を解決できないために行われたとは書かれていません。前半部分では、源逆説性と「絶え間なく戦(・)う(・)」とあるだけで、解決を断念したとは書かれていませんでした。解決の断念のことはいわば潜在化され、その代わりに、ここでは、源学の立場から、源学がおこなうべきことを妨げるものとして根拠づける学が扱われています。実際、源逆説性の解決は、経験的な対象が不在なのですから、「抽象的な概念的構築」によってしか解決できませんし、源逆説性は根源づける学のもつ逆説性ですから、「秩序概念」からすれば、まずはじめに取り組むべき問題でありますが、そんなものと戦っているかぎり、源学には取り組めないわけです。源学がおこなうべきことは、「根源の中に生き生きと還帰し」、逆に「根源から生き生きと現れ出てゆく」ことなのですから、それを進めるためには、「抽象的な概念的構築」とか「秩序概念」といったことは「容赦なく却下」しなければならない、というのです。たしかに、源学を形成しようとする立場から見れば、源逆説性の問題は、源学の遂行を妨げる邪魔ものとなるものではあります。ですが、なんか腑に落ちない感じが残ります。『哲学の理念』講義の中では、「突破」できないと言っていたのですが、同時に「手段」がないからできないからだとも言っていました。つまり、手段が見つかれば解決できる可能性があるという余地が残されていたのです。ですが、ここでは、そんな余地は残されません。根源学の課題は解決不可能であることがと固定化され、課題そのものが閉ざています。しかし、じぶんが「突破」できないからといって、その課題そのものがなくなるわけではありません。しかしまた、その「課題」を持ち続けて、繰り返し挑戦しているかぎり、第二の途を進むことはできないことも明らかで、私自身体験していることです。ですから、課題そのものをなんだかんだといって閉ざしてしまうことも、実際問題としては理解できることです。源学を建設しようする行動が、こうした課題の閉鎖をもたらしているわけです。おそらくこの事情が呼び寄せたのだと思われるのですが、本文に先立ってベルクソンの『物質と記憶』(1896年)からの次のような引用がなされています。
我々ハ常ニ我々ノ前ニ空間ヲ開き、常ニ我々ノ後ニ持続ヲ閉ジテイル。(52)
源学に向かうということは、前に学の可能性を開いていることですし、源逆説性との戦いを断つことは、根源的な問題に従事するあり方を断つこと、つまりこれまでのあり方を切断することを意味します。その意味では、ベルクソンの言葉は、第一の途を断念し、第二の途に向かっているハイデガーのあり方を表してくれているようにも捉えられえます。そうであれば、ここでハイデガーは、ベルクソンの言葉を媒介にして、自分自身のあり方にかかわっていることになります(53)。むろん、ベルクソンの言葉は、彼の哲学の文脈のなかにあるもので、かならずしも、全面的にハイデガーの意に沿うであろうものではありません。ハイデガーが行っているのは、異なったあり方への移行であって、それによって、過去のあり方(根源学から始めるあり方)を閉ざしているのであって、時間(持続)を閉ざしているわけではありません。ですが、ここはベルクソン哲学と対決する場ではないので、これ以上深入りは避けて、ひとまずこの段落の全体について締めくくっておきます。
前半と後半の全体を通して、根源学の二つの途という観点から見るなら、そこでは、根拠づける学から根拠づけられる学へと移動していることが示されています。ですが、そのように見ることができるのは、あらかじめ根拠づける学と根拠づけられる学の区別、および前者から後者への移行という概念(関数)を得ていたからであります。そうした形式的、抽象的な概念(関数)が、ハイデガーのテキストのなかで具体的に具体的な形態をとって見いだされるわけです。これによって、ハイデガーのテキストの中のある事実(所与)が、あらかじめ与えられた関数の値として再把握されるわけです。これは、あらかじめ形式的な思考を遂行したものにとってみれば、自分が創出した形式的概念が、現実の中で見出されるという出来事です。ハイデガーのテキストが与えられていなければこの出来事は起こりえません。つまり、これは、自分のテキストと過去の他者のテキストとの関係の中で起こった出来事です。一般にこうしたことは、「解釈」と呼ばれています。ハイデガーの存在論的な現象学も解釈学として成り立っているので、これと類似した解釈形態を見ることができるのですが、この問題もまた次回、「根源学の理念Ⅱ」と関連するので、そこで触れることになるかもしれません。
いずれにせよ、「根源学の理念Ⅰ」では、根拠づける学から根拠づけられる学への移行が読み取れますが、根拠づけられる学が根拠づける学を取り戻す、という点には及んでいないわけです。そのことを念頭において、次回「根源学の理念Ⅱ」を読むことにします。(2025.6.26)
(注)
(43) 邦訳全集第58巻『現象学の根本問題』(GP)虫明茂、池田 喬、ゲオルク・シュティンガー訳
この講義は1919/20年冬学期に行われたもので、1927年の同名の講義(邦訳『現象学の根本諸問題』)とは別です。
(44) 『哲学の理念』講義では、源学(Urwissenshaft)が一貫して用いられており、おのれ自身を根拠づける学にも使われています。そのため、邦訳ではその部分は「根本学」という語があてられていました。
(45) GP.第1節,p.3f
(46) SZ.第7節
現存在の現象学とは、ことばの根源的な意義における解釈学であり、その語義にしたがえば、このことばは解釈という仕事をしるしづけている。(1-p.212,d.113)(dは段落番号)
(47) SZ.第1節,1-p.80,d.8
(48) SZ.第74節,4-p.264,d.1127
(49) GPでは、自己理解する人間的生そのものは、生即自として、いいかえれば「事実的生」として、扱われています。つまり、即かつ対自は、一方では人間的生の事実的なあり方であり、他方で、それを扱う現象学は、それに対して即かつ対自的であることになるわけです。
(50) GP.第1節p.4
(51) GP.第1節,p.4
(52) GP.第1節,p.3
(53) このあり方を私は「媒介的自己言及』と呼んでいます。自己言及については、「歴史の中の時間的パラドクス」が終わった後で扱います。