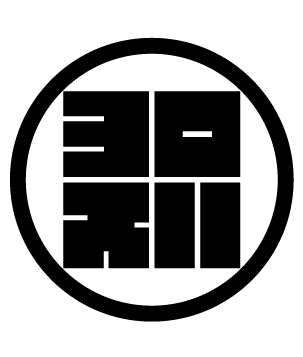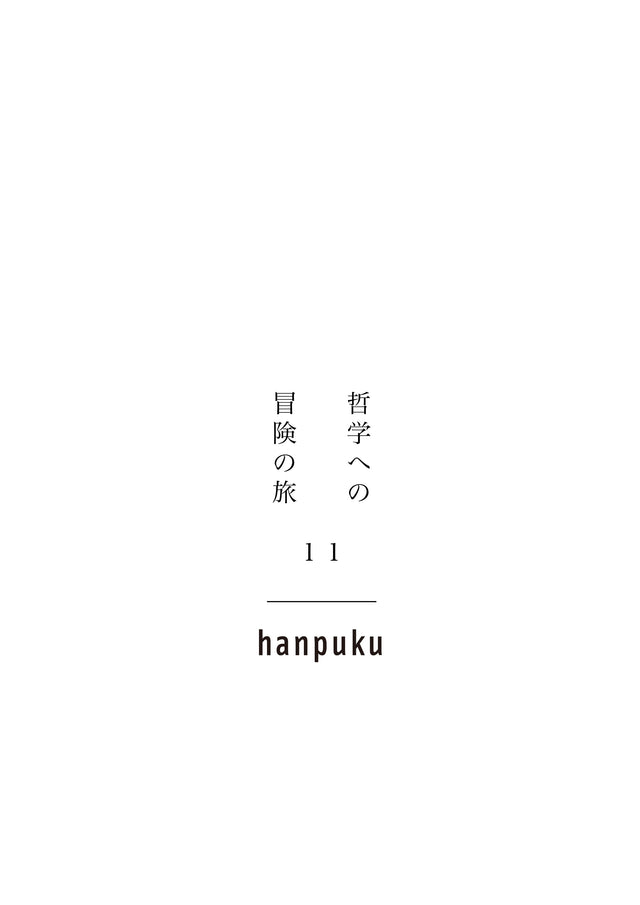
哲学への冒険の旅 11
哲学への冒険の旅 11
11 歴史の中の「時間的パラドクス」五――ハイデガー5
「源‐学」、根源学のとり戻し
では、テキストの文脈に戻ります。私たち解釈者はいま転換のまっただなかに身を置きながら、テキストに向かっています。前回、循環的なあり方が理論的な現象だといわれていることを取り上げましたが、それに続けてこういわれています。
ところで、循環的あり方の理論的性格を洞察することでなにか新しい成果があっただろうか。われわれは、先にすでに、このありかたを根本学〔根源学〕の基礎特質であるとしたが、どのような学もそのものとしては理論的である(実践的ではない)。しかし、われわれはこれまで、循環的なあり方を本質的に理論的現象と見ることはしなかった。つまり、特殊な隔生の過程によって環世界体験から肥大してきたものとして見ることはしなかった。だが今は、循環的あり方が存在する領域にもまた前提事項があり、根源的…な領域ではありえない……ことが解っている。なぜならそれが理論的な領域だからであり、理論的なものは、隔生化されたもの、それ自体跳出してきたものである。(39)
理論的難点とは、理論的現象(認識論)のなかにおける根源性の問題でしたが、ハイデガーは、そもそも、認識論としての理論的領域は根源的な領域ではなく、隔生化によって生の領域から跳出してきたものだとしています。
ここで「隔生化」という言葉に再び出会いますが、先に認識論における隔生化について言われたときと同様に、理論的現象は「環世界的な体験」から派生したものだと言われているわけです。ですから、あきらかにこの場合の「理論的現象」は認識論を指しますが、また、理論的現象(認識論)が生の領域から跳出してきたもので、根源的な領域ではないということは、逆に、そこから理論的現象(認識論)が生じてきたところの生の領域こそが根源的な領域だということでもあります。
ですから、「隔生化」という概念は、一方では理論的領域(認識論)の根源性を否定しつつ、他方で、それに代わって理論的領域がそこから出現する生の領域に根源性を与えるという二重の働きをしているわけです。そこから生まれてくるのは、広い意味での現象学です。というのも、そこから理論的現象(認識論)が生まれ出る生そのものが根源であるのであれば、根源を見いだすためには、生そのものを見つめればよい、ということにもなるからです。
ということで、フッサールは、「従って」と「から」(「則して」)の区別によって「循環」から回避しましたが、ハイデガーもまた、フッサールとは違った仕方で、すなわち「隔生化」という概念によって、理論的難点から離れて現象学的な探究へと移っているのです。
ですが、人間存在のうちに根源を見いだせばいい、というのだとすると、こういう疑問が湧きます。
-
なぜ隔生的なものが生み出されるのでしょうか。
-
なぜ生は隔生的なものを生み出すのでしょうか。
-
なぜ人間は哲学を生み出すのでしょうか。
-
なぜ私は哲学を生みだそうとしているのでしょうか。
その答えはこのシリーズの後の回で示しますが、ここで言えるのは、現象学では根源学のもつ理論的難点を解決することは不可能だとして、ハイデガーは現象学へと移動していますが、それとは逆に、私が体験したことは、現象学を断念してテキストとしての根源学に立ち向かうこと、つまりハイデガーとは逆向きの移動であったということです。
ともかく、ハイデガーはこれによって「根源的な領域」という新たな対象領域を見いだします。具体的にいえば、それは人間的生、つまり人間存在の領域です。
主題対象の移動ということでは、認識から存在への移動ですが、領域に関する移動という点で言うなら、もともと認識論も人間の認識能力の問題だったのですから、人間の領域という共通のベースの上での転換にすぎません。
ですが、根源学からの移動という場合は、領域も人間の領域からテキストの領域への移動ということになります。というのも、「学の現存は著作にある」というフッサールの言葉を踏まえるなら、根源学は領域的にはテキストの領域だからです。ですから、実在論的に見れば、上の移動はテキスト領域から人間領域への移動ということになります――ちなみに私の体験した移動は、逆に、人間領域からテキスト領域への移動ということになります。
ともあれこうして、理論的(認識論)領域の起源とされる領域である人間的生の領域を主題対象とする新たな学が構想されることになります。ハイデガーはその学を「源・‐学 Ur-wissenschaft」と呼んでいます。そして、源‐学へのこの移動を「止揚」と呼んでいます。
理論的な根本学〔根源学〕というのが存在するとすれば循環は止揚不可能である。……。
しかし、もし循環が止揚可能であるとすれば、理論‐以前の学、すなわち超理論的な学が存在しなくてはならないことになる。すくなくとも非理論的な学、つまり理論的なものそれ自体がそこから起源してくる真の源・‐学が存在しなければならないことになる。(40)
前に言ったように、「止揚」は「解決」を意味しません。それは一度否定したものを取り戻すことを意味するのでした。ですから、「止揚不可能」ということは、一度断念した根源学を取り戻せないということです。
むろん、それは認識論としての根源学では難点を解決することができないため、取り戻せないということです。反対に、「止揚可能」ということは、一度断念した根源学を別の形で取り戻せる、ということです。そして、それができる学は理論的な学ではなく、すでに紹介したように「非理論的な学」だと言うのです。
「非理論的な学」とは何を意味するのでしょうか。ここにも「理論的」の二つの意味があるので、二つの解釈が可能になります。
-
「理論」を「認識論」ととらえる場合
→ 「非理論的」は「非認識論的」という意味。 -
「理論一般」ととらえる場合
→ 認識論だけでなく、存在論も含む。
「理論一般」の基本的な特質は、前に言ったように論理的な区別です。論理的区別は、認識論にだけ固有な特質ではなく、存在論においても作動しているものです。そもそも論理的な区別は、言葉を使用することに内在するものだからです。
言葉が表現している意味(シニフィエ)は、たとえば猫、木、石、人、等々のように不特定の対象についての概念です。それを用いて特定の対象について表現するわけですから、このような言葉使用には、必然的に関数と代入項と両者の結合としての値の区別が内在しています。論理的な区別は、それを顕在化しているだけです。
ですから、存在論であろうと認識論であろうと、言語表現であるかぎり論理的区別からは、たとえ否定しても逃れることはできません。
ハイデガーは認識論を批判して存在論へと転換していますが、存在論はいうまでもなく非・認識論です。ですから、「理論」を認識論とみなすならば、存在論は「非理論」ということになります。
ですが、「理論一般」とみなすなら、存在論は言語表現に内在する論理的な区別が機能しているかぎり、「非理論」ではありえません。しかし、ハイデガーは論理的な区別を論理学的な仕方では表現していません。むしろ論理学には批判的です(41)。
ですが、実質的には上に述べたように、言語使用に内在する区別を拒否することはできないので、表現を変えて、たとえば関数に相当する概念を「形式」と言っています。ですが、「形式」という概念も「内容」と対をなす概念であり、それは実質的な論理的区別にほかなりません。
以上が、ハイデガーにおける認識論から存在論への移動の経緯です。ちなみに、私自身、まったく別の形で、認識論から存在論への移動が必要だと思っていました。
卒論のためにカントの『純粋理性批判』を読んでいるときに思ったのですが、カントは、認識の客観的妥当性を根拠づけることができていない、と。なぜできていないのかといえば、カントにおいては現象とは感性の形式に適合しているものでしかなく、対象そのもの(物自体)には達しえないとされていたからです。
そのため認識の客観的妥当性を根拠づけるために、カントは認識の普遍妥当性に依拠していました。それを表している文章が『プロレゴーメナ』§19にあります。
客観的妥当性と〔すべての人に対する〕必然的な普遍妥当性とは相関概念である。そして、われわれは客観自体を知らないにしても、ある判断を共通妥当的、したがって必然的と見なすとき、まさしくそれによって客観的妥当性を意味しているのである。(42)
これに私は疑問を感じました。普遍的妥当性といっても、それは人間にとっての妥当性でしかありません。それが客観的妥当性だというのであれば、そもそも客観的妥当性も、人間にとってのものにすぎないのではないか、と思ったのです。
そこから、客観的妥当性を根拠づけるにはどうすればいいのか? ということが課題として浮かび上がり、それに対して、感性の形式ではなくて存在の形式をア・プリオリとすることができればいいのではないか、というようなことを漠然と考えたのです。
この考えには、認識論から存在論への移行が含まれていたと、いまでは言えます。この視点から見ると、一方ではハイデガーがおこなった認識論から存在論への移行に賛同しつつも、彼が形成した存在論では、依然として客観的妥当性を根拠づけることはできていないと思わざるをえません。
たとえば、彼は世界を有意義性と規定していますが、それは人間にとってのことでしかなく、依然として人間内在的でしかなく、人間の外部には達しえていないからです。ですから、客観的妥当性を根拠づけることが、今度は存在論の課題として残されているということに、私の中ではなっているのです。
次回は、第三の問題、現存在の分析論を基礎的存在論とすることに関しての考察を行う予定です。
(注)
(39) ID.§18. 邦訳p.104
(40) ID.§18, 邦訳p.104
(41) 「『形而上学とはなんであるか』への後記」(1943) 邦訳全集第9巻『道標』所収参照
(42) 『プロレゴーメナ』土岐邦夫・観山雪陽訳 世界の名著 カント、中央公論社 p.133f