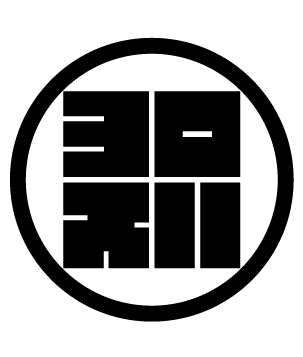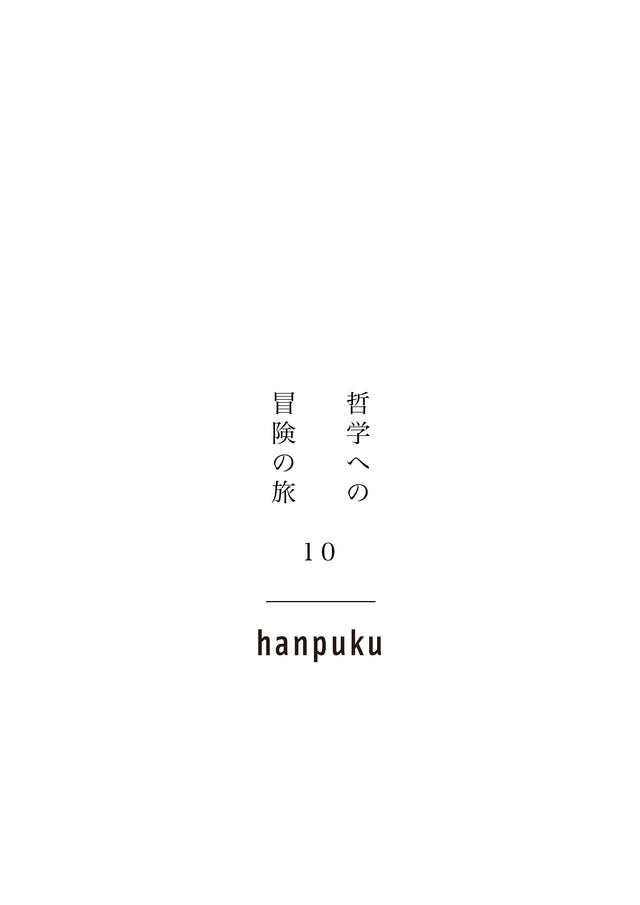
哲学への冒険の旅 10
哲学への冒険の旅 10
10 歴史の中の「時間的パラドクス」五――ハイデガー4
根源学における移動と認識論から存在論への移動
これから読むのは同じ1919年の『哲学の理念』講義の第二部第三章§18「認識論の循環的なありかた」です。ここでハイデガーはふたたび根源学における「循環的」なあり方に立ち戻っています。それを「哲学の本質的特性」として呼びつつも、「克服不可能」なものとして捉え、それを「止揚する」哲学の途を見いだそうとしています。「止揚」は対立の解決を意味しません。ヘーゲルにおいては、止揚は否定された端緒を回復することを意味しますが、ハイデガーもここで、否定されたもの(根源学)を変形したうえで回復しようとしています。それをあらかじめ告げ知らせるかのように、循環性についての或る解釈がまず示されます。
まず措定される……べきはずのまさにそのことが……、前提と…されており、前提とされなければならない。(33)
この解釈は、認識論から存在論への転換を前提しているもので、根源学の循環性が変形されて回復された姿を表わしています。ですから、まず転換の経緯を見たうえで、ふたたび戻るのでなければ、十分に理解することはできません。
そこで転換の経緯ですが、まず「循環的なあり方」が「理論的な現象」だといわれます。
循環的なあり方はすぐれて理論的な現象である。それはいわば、純粋に理論的な難点の最も昇華されたかたちである。これまでの一切の努力の方法上の意味とは、無前提の境界に、つまり根源(源‐出)に迫ることであった。前提に侵されているものをすべて取り除くことであった。その際に、われわれ自身が理論的なものに貼りついてしまったのであった。循環的なあり方は理論的難点であって、理論的につく……り出された……難点なのである。(34)
ここで「理論的な現象」と言われているのは、認識論のことです。ですが、「理論的なもの」一般として考えたとしても同じことは言えます。つまり、たしかに「循環的なあり方」は、或る意味理論的に作られた理論的難点です。ですが、単なる仮構ではありません。それは学にとっては必要不可欠なものです。
大事なことなので、これに関連した考察をしておきます。たとえば、ハイデガーは『存在と時間』の中でこう言っています。
学一般は、真なる諸命題の、基礎づけ〔根拠づけ〕連関の全体と規定されうる。(35)
根拠づけ連関の全体があるとすれば、その連関における第一のものとして、他によっては根拠づけられない根拠、すなわち自分自身を根拠づける根拠があるのでなければなりません。ですが、まさにそこで「循環的なあり方」が生ずるのですから、それが解決できなければ、根拠づけ連関の全体としての学は成立しえないことになります。
ですから、「循環的なあり方」を理論的に突破することができないとすれば、学をあきらめるか、何か別の形で学を存続させる途を見いだすほかありません。以前の引用で示していたように、ここで哲学は「生死をわかつ方法上の岐路」に立たされているわけです(36)。
ただ「別の途」は、形態はさまざまであれ、概念的にはすでに決まっていることが、根源学の理念そのものを分析することで明らかになります。
根源学とは、おのれ自身を根拠づける学です。ですから、仮にそうした学が成立するとすれば、その学は、二つのあり方、すなわち、根拠づけるあり方と根拠づけられるあり方とを含んでいることになります。これを形成する場合には、二つを同時に行うことはできませんから、どちらかを先に形成しなければなりません。
根拠づけるあり方を先行させるとすると、根拠づけられるものが先取されるのでなければなりません。何を根拠づけるのかわからなければ、根拠を形成することはできないからです。ですが、それはいまだ存在しないものであるだけでなく、後で経験的に実証されうるものとして現実化されるもの――言い換えれば、単なる想像的なものではないものを――、しかも論理的に必然的なものとしてあらかじめ捉えることができなければならないという難問(この稿で「時間的パラドクス」と呼んでいるもの)にぶつかることを意味します。
これを突破できないとすれば、もうひとつの途に向かうほかありませんが、その途とは、いうまでもなく、根拠づけられるあり方から始めるという途です。この途は、根拠づける学が存在しなくても、存在しえる途です。なぜなら、根拠づけられる学は、何らかの対象についての学として成立し得るからです。
実際、諸科学は、根源づける学が不在であってもそれぞれの領域内で成立しています。言い換えれば、根拠づけられる学は、何らかの実在するもの――すなわち経験可能なもの――を対象とする、実在するものについての学なのです。
けれども、実在するものについての学から始めるということは、それを根拠づける学(存在論)の不在、したがって、その学を根拠づける根拠の不在を前提としているということです。ハイデガーが採った「現存在の存在論」の途は、まさにこの途です。以前『現象学の根本諸問題』(1927年夏学期)の序論第5節から引用した文が表しているのはまさにそのことでした。
オントロギーは、基礎的部門として現存在の‐分析論をもつ。このことには同時に、オントロギーはそれ自身純粋にオントロ―ギッシュには基礎づけられえない、ということが含まれている。オントロギー自身を可能にすることは、或る一つの有るものすなわちオンティッシュなものへ、つまり現存在へと差し戻されるのである。(37)
言うまでもないことでしょうが、「オントロギーはそれ自身純粋にオントロ―ギッシュには基礎づけられえない」とは、根拠づける学が存在しえないということです。その結果、現存在の存在論へと移動するわけです。ですから、移動した先の現存在の存在論は、根拠づける学の不在を前提として「含んで」いるということになります。
上でいわれていることはそれだけでなく、移動した先の現存在の存在論を「存在論の基礎的部門」とするとも言っています。順序を変えてあらためて要約すると、上の引用文には次の三つのことが言われています。
① 自分自身を根拠づける存在論は不可能であること
② それゆえ、現存在の存在論に移行すること
③ 現存在の存在論を存在論の基礎的部門とすること
おのれ自身を根拠づける存在論は、学の秩序からいえば、第一の根拠づける学にあたります。それが不可能だからといって、現存在の存在論へと移動するわけですから、当然、現存在の存在論は、根拠づけられる学に当たります。つまり、この移動には、学的秩序における移動、すなわち根拠づける学から根拠づけられる学への移動という側面があるわけです。
そして第三に、現存在の存在論、つまり根拠づけられる学を「基礎的部門」にするとあります。『存在と時間』では、現存在の存在論は「基礎的存在論」とも言われていますが、それは実質的には、あらゆる存在論の根源としての存在論を意味しています(38)。ですから、ハイデガーは、根拠づけられる学を、また根拠づける学にしようと企てているわけですが、これについてはあとでまた立ち戻ります。
これから見ようとしているのは、「理論的なもの」一般の視点で言うなら、この移動、すなわち根拠づける学から始めることを断念して、根拠づけられる学から始めることへの移動で、それが、どのような仕方で行われたかということです。
ですが、他方で、「理論的なもの」を認識論として見る場合には、この移動は、認識論から存在論への移動という形になります。それというのも、おそらくフィヒテ以来、根源学は認識論の枠組みにおいて提示されていたからです。フッサールにおいても認識論の枠内で循環が見られていました。
ですから、この視点から見た場合には、「根源学の難点は理論的な現象である」という場合の「理論的」とは、実質的には認識論のことを指しています。上の引用文は、『存在と時間』が刊行された1927年の講義、すでに存在論へと転換した後の講義で言われているものですから、存在論が前提となっていますが、いま私たちが取り組んでいるテキストは、『存在と時間』への歩みが始まる時点のもので、これから存在論への転換を行おうとしているということを念頭においてください。その時点では、「理論的なもの」は「認識論」とみられていたわけです。
つまり、ハイデガーがこの講義で用いている「理論」には二つの意味が貼りついているのです。
-
一つは、「理論一般」で、最初に述べた根源学の分析はこの視点に立ったものです。
-
もう一つの意味は、特定の理論としての認識論です。
この二重性のために、理論一般に関しては、根拠づける学から始めることから、根拠づけられる学から始めることへの移動と捉えられるものが、認識論という特定理論から見れば、認識論から存在論への移動として捉えられることになります。
ですが、ハイデガーは、この二つの意味を明確には区別していません。そのためでしょうが、認識論からそこへと転換してゆく先の学を、「非理論的な学」とみなしていました。
「非理論的な学」というのはどういう学かというと、後で引用しますが、「理論的なものそれ自体がそこから起源してくる」学のことです。ですが、この言い方は、理論的なもの=認識論としているということでもあります。だからこそ、認識論ではない学は「非理論的な学」ということになるわけです。
認識論から移動する先が存在論だとするなら、認識論から存在論への移動は、学の主題対象の移動――認識から存在へ――であるだけでなく、「理論的」な学から「非理論的」な学への移動ということになり、しかも存在論は「非理論的」な学としてしか成立しないということになってしまいます。
ですが、そもそも「非理論的」とはどういうことでしょうか。前回見たことでもありますが、理論的な学の根本特徴は、一般的なものと特定のものとの区別にあります。これは、アリストテレスによる第一実体(例えば、特定の馬)と第二実体(例えば、馬一般)の区別以来のことです。
この視点から見ると、理論一般と特定の理論との二重性というのは、そもそも論理的におかしいということです。なぜなら、根本的な論理的区別を侵しているからです。理論一般は明らかに特定理論に対して抽象度がより上位にあるものです。記号論理学の表現でいえば、理論一般は関数にあたり、特定理論は値にあたるものだからです。
ここから生ずるあいまいさは、『存在と時間』における「存在」と「実在」のあいまいさとも共通しています。ここにハイデガー存在論の歪みが現われている、と私は考えています。
次回は、具体的に、移動の経緯を見ることにします。
(注)
(33) ID.§18, 邦訳p.103
(34) ID.§18, 邦訳p.103f
(35) SZ. 第4節, 邦訳1-p.111
(36) ID.§13, 邦訳p.69
われわれは、哲学の生死をわかつ方法上の岐路に立っている。この岐路は、無に至るか、つまり絶対的な即物性の無に至るか、それとも別の世界へ向かう跳出が、いや厳密にはおよそ世界そのものへ向かう跳出が成功するかどうかをわかす深淵である。
(37) 『現象学の根本諸問題』(GP). ハイデッガー全集第24巻, 邦訳p.26(「現有」を「現存在」に変更)
(38) SZ. 第4節
かくて基礎的存在論は、現存在の実存論的分析論のうちにもとめられなければなりません。他のすべての存在論は、その基礎的存在論からはじめて発出しうるのだ。(1-p.118)