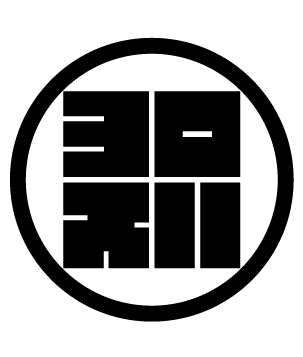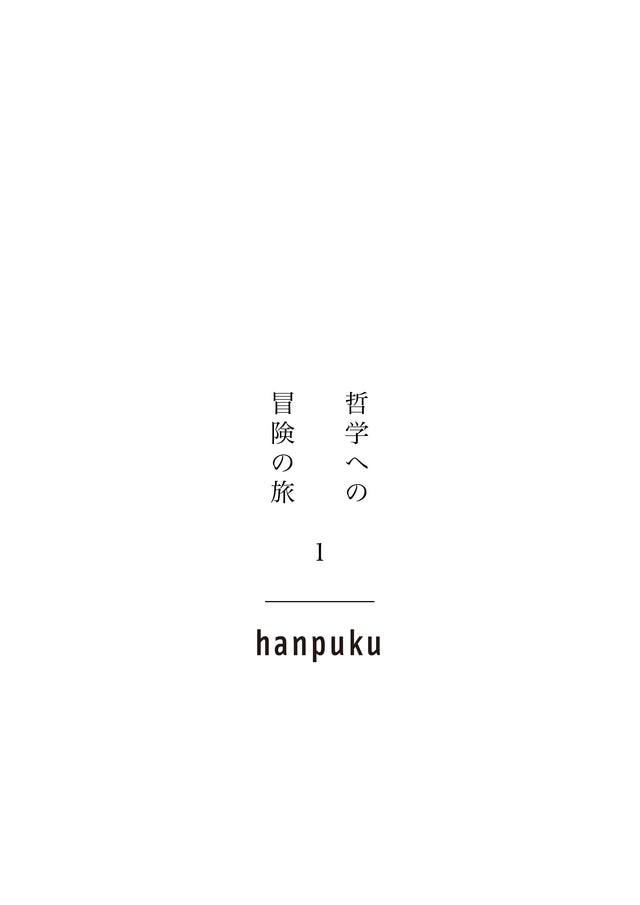
哲学への冒険の旅 1
前口上
学生時代後期、遅咲きで人文系全般、特に思想、哲学と呼ばれるジャンルにどっぷりハマった時期がありました。(ファッション系の話は別タイミングにて書きたいと思います。)やりたいことはこれだったと、熱心に将来はその道の研究者になりたいと思って没頭しましたが、時すでに遅し。二つの理由で挫折。ひとつは、真剣に取り組んだからこそ、能力が圧倒的に足りないことが身をもって分かりました。やはりスポーツのように越えられない壁はあるなと。二つめは、その業界は50代頃、ようやくスタート地点に立てるような世界であり、専門的であることが最重要。加えて横断的な研究は嘲笑という風潮がありました。総じてその場所が心地よく、それが得意な方々がやれることだなと。
当時、アルバイトでは迅速かつ綺麗な皿洗いから、高速かつ丁寧な仕込み、味も見た目もよい料理を作る。集中。定期的に反動のように、サケ、カオス。それ以外は読書、勉強、目が痛くなったら音楽をひたすら聴く、その繰り返し。とにかく反復の日々を過ごしていました。
そんな中で、とある著者が新刊を出すとのことで、おそらく新宿紀伊國屋だったような気がしますが、ひとりで発売トークイベントに出向。偶然隣の席で、知り合いになったのが堀渕さんでした。一言でいえば、日本からアメリカへ行き、そちらでサバイブを経験した後、ラブアンドピースの結論に至った方です。
そんなご縁から、彼らが定期的にやっている読書会というものに参加させていただく流れに。そこでは塚原さんという在野でひたすら哲学をしている方を先生とし、生徒は編集者、教師、自由人、新聞社、大学院生、等様々な方々が集い、あーだこーだと盛り上がる空間がありました。当時のわたしには非常に刺激的で今まで頭の中にぼんやりあったものが言語化され、輪郭が鮮明に認識できるようになったり、新しい世界が発見されました。yorozuはそれらの経験が基礎となり、影響を受け、時を経て予期せぬカタチで始まりました。直接的には表現できておりませんが。
列挙するのが、なんといいますか、とても薄っぺらく、恐縮な気分ではありますが、ソクラテス、プラトン、デカルト、カント、ヘーゲル、マルクス、ニーチェ、フロイト、フッサール、西田幾多郎、ブッダ、ナーガールジュナ、ヴィトゲンシュタイン、ハイデガー、レヴィナス、ドゥルーズ、フーコー、デリダ、小林秀雄、柄谷行人、東浩紀、等々、日本語ですが、著作を読みました。難解。でも分かりたいから粘り強く向き合ってみる。知の巨人の凄さに圧倒されては自身の未熟さに絶望していました。ちなみに、なんと残念なことに、現在それぞれの著作の具体的な詳細を思い出すことができません。悲しいですね。それは数年前の今日、昼食を誰かと楽しく会話しながら食べたはずですが、その詳細を思い出せない虚しさと同様です。しかしその経験が全くゼロになってしまったということではなく、久しぶりでも自転車に乗れるように、抽象的な話は、解像度は低くはなっているものの理解できるような気がする、ということです。そのような経験として残っています。
社会人になってからは、その場になかなか参加できなくなってしまいましたが、時折り思い出しては気になっていました。大学などで居場所と役割が確保され、所属がはっきりしている研究者ではなく、現代の日本社会において、ただひたすら哲学の道を歩いている、あの塚原先生はどんな感じなのかと。
そして最近、数十年といっても過言ではない、塚原さんの文章がある程度まとまったとのこと。その一部を、こちらのhanpukuに掲載してよいことになりました。急遽斬新な展開ですが、一部連載を掲載させていただきます。
A.Morikawa
・・・
哲学への冒険の旅
塚原誠司
1 二つの思い その1―マルクス
私が哲学への冒険に出たのは54年前の1970年のことでした。それ以来一貫して同じテーマを追い続けています。
開始したとき私の内には二つの思いがありました。ひとつは、哲学者自身を認識しなければならないという思いです。もともと自分自身を知りたいという内的衝迫のようなものがあったのですが、自分の哲学を始めようとするときに、哲学者自身を認識しなければならないという形になったのでした。
その後の探究遍歴の中で、これと同じ思いはニーチェのうちに否定的にではあれ見いだされたし、晩年のフッサールが、いわゆる『危機書』(1)のなかで、自分の思いとは異なる点はありましたが、認識者が自己自身を省察するという動機を「超越論的」と呼んでいることも知りました。また、ハイデガー『存在と時間』では、〈存在の意味を問う者の存在を問う」といいながら、存在論を形成する者の存在は問わずにいるということも知りました(より詳しくは後述します)。
もう一つの思いは、解決すべき課題として意識されたものです。私はこの課題をマルクス『資本論』の「価値形態」論と「交換過程」論の分析から掴みだしました。
細かいことは後にして結論を言うなら、当時、マルクスのテキストと格闘の末に私がたどり着いた結論は、マルクスは交換の可能性を明らかにすることに失敗している、というものでありました。それは、マルクス自身がある意味認めているもので、後で見てみますが、あまりにも明白な〈理論的事実〉と思われたのです。
ですが、当時は今日とは違ってマルクスの権威がまだかろうじて生き延びている時代であったせいか、私の知る限りでは、この事実を誰も指摘していませんでした。しかし、マルクスの権威を保持している人々のただなかに私はいたので、その権威を否定しさるような考えをもってしまった私は、自然に周囲の友人たちから離れてみずから孤独のなかに入り込んでしまいました。
私がその事実を見いだしたのは、感情的な判断によるのではなく、ましてやイデオロギー的な判断によるものでもなく、まったく論理的、合理的な判断によるものだったので、その後繰り返しおこなったマルクスとの対話を通じてもこの考えは揺るぐことなく、自分の中ではますます確信の度合いを強めるばかりでありました。
むろん、マルクス自身は「失敗した」とは書いていませんし、ちゃんと通りすぎる道を示していましたが、しかし、ある論証が挫折せざるをえないことは間違いなく告げていました。ですから、「交換過程」のなかの次のくだり――「わが商品所持者たちは、困りはてて、ファウストのように考える。初めに行いありき。したがって、彼らは、彼らが考える前にすでに行っていたのである」(2)――は、私にとっては、マルクスの理論的企ての挫折を示す墓標と見えていました。
価値形態論でマルクスが試みたのは、商品と商品との関係から貨幣が生成することを論理的にあきらかにすることでした。交換は商品と貨幣の間でおこなわれるということを前提としたうえで、まず貨幣がどのようにして生まれてくるのかを示すために、商品と商品との関係から貨幣が生成することを「論証」しようとしたのです。
そのために、マルクスは、ふたつの商品に二つの相反する在り方、すなわち、他の商品の価値を表現するもの――「等価形態」とよばれますが実質的には貨幣の役割を果たすもの――と他の商品によって自分の価値が表現されるもの――「相対的価値形態」と呼ばれるもので、文字通り商品であるもの――とにわりふったのです。つまり、商品という点では同じあり方をもつ二つのものに、表現するもの/表現されるものという対立的な役割を与えているわけです。
しかしここに解決不可能な問題がありました。それは役割決定の問題です。というのは、一方が「表現する」役割を引き受け、他方が「表現される」を引き受けなければ、この関係は成立しえないことになるわけですが、どの商品がどの役割を引き受けるかを決定することができないという事態が必然的に生じてしまうのです。たとえば、商品Aが「表現する」側とすると、他の商品、たとえば、商品Bが「表現される」側に立つと決定できなければならないわけですが、どちらも商品ですから、逆に、商品Bが「表現する」側になることもありうるわけです。そうなると、商品Aは「表現される」側に立たねばならないことになります。つまり、ある関係はかならず役割に関して逆の関係を可能性として含むことになり、かつ二つの関係は互いに相殺しあうので、結局、ある商品を「表現する側」に、他方の商品を「表現される側」に立たせるという決定はできないことになるわけです。
しかし、決定しなければそもそも生成の論証ははじまらないので、なんとか決定しなければなりません。マルクスはどうしているかというと、決定するのは、なんと論証を行う理論家マルクス自身なのです。「私がこれを逆にしてしまうやいなや」、商品Bが商品Aの「かわりに等価〔形態〕となる」(3)といっているのです。つまり、マルクスは、逆関係をみずからに禁ずることで、一つの関係を設立するわけです。しかも、それを一般的原則のように立てて言います。「同一商品は同一の価値表現において、同時に両形態に現われることはできない。この二つの形態は、むしろ対極的に排除しあうのである」(4)と。仰々しいですが、この原則は、自分が行っている理論的行為を一般的原則として表現したまでのことです。
こうして単純な価値関係を措定したうえで、価値形態論では、マルクスは貨幣の生成を「論証」してゆくのですが、交換過程論では、これが否定されてしまいます。なぜ、そういうことになるのか理解するためには、価値形態論と交換過程論の違いに目を向ける必要があります。
その違いは、簡単なことで、価値形態論では、商品だけが登場し、商品所持者は登場させないのに対して、交換過程論では商品と商品所持者の両方を登場させるのです。これによって、商品の価値関係の設立が破壊されることになります。どうしてか?
価値形態論では、決定者はマルクスで、商品所持者はいないので、商品はマルクスの決定通りに配置されることになります。ですが、マルクスは商品交換の場にいるわけではなく、それを理論的に分析するという場にいるわけです。実際に商品交換の場にいるのは、商品所持者です。そして、商品所持者の間では、マルクスの決定などなんの意味ももちません。
ある商品所持者が自分の商品を「表現する」側――貨幣の側――におこうとしても、他の商品所持者も「同一のことをする」(5)ことができるので、そうすると、逆関係が形成され、互いに争いになり、決定できない事態に陥ることになるわけです。つまり、商品所持者の同等性(平等性)が、そもそも差異関係である商品の価値関係の設立を不可能にするわけです。
そこで、マルクスは、先に引用した言葉――「わが商品所持者たちは、困りはてて、ファウストのように考える。初めに行いありき。したがって、彼らは、彼らが考える前にすでに行っていたのである」(2)――と宣うことになるわけです。ですが、「困りはてて、ファウストのように考えて」いるのは、実は、理論家マルクスに他なりません。理論家として介入するかぎりでは、二つの商品を「表現する」側と「表現される」側にそれぞれ決定することができるのに、現実の商品交換の場では決定されえないことが明らかだからです。ということで、商品と商品の関係から貨幣を生成させるというマルクスの試みは挫折するのです。その理由もはっきりしています。同等性(平等性)を前提としてそこから出発するかぎりでは、貨幣の生成も交換可能性も原理的に解明できない、というのがそれです。
だとすれば、差異性から出発するほかないということになりますが、この問題は経済学の領域で片が付く問題ではありません。「彼らは、彼らが考える前にすでに行っていたのである」という言葉も示唆しているように、それは存在論の領域に属する事柄です。そうであれば、上の言葉は、『資本論』における存在論の欠如という理論側の欠陥を示すものでしかないことになります。
しかし他方、存在論の側においても、交換可能性の問題は欠落しているのです。詳しくは後で見ますが、ハイデガー『存在と時間』では、道具はもっぱら使う側においてのみ考察され、生産する側に関しては考察の外に置かれています。当然、生産する側と使用する側の間で行われる交換についてもまったく無関心です。ということで、私の存在論の目的のひとつは、経済的交換だけでなく広い意味での交換現象の可能性を解明することとなりました。
『資本論』では、このあと、ある特定の商品を、他の商品を持つすべての商品所持者がみんなで一緒になって等価形態(貨幣)にするとしています。この論理は、ホッブス『リヴァイアサン』の論理と、扱っている内容は異なっていますが、論理の形式は同じです。
ホッブスも、個々人の平等からはじめます。要するに、誰もが同じことをしうるという点からはじめるわけです。これは、マルクスが商品同士および商品所持者同士の平等な関係から始めるのと論理的形式において同じです。
次に、その関係の中では、互いに同じことを行おうとするので、かならず争いになります。競争であればまだしも、ときには暴力的な争いにまで及び、ついには戦争にまでなるとしています。ホッブスは、これを「各人に対する各人の戦い」と呼んでいます。マルクスで言えば、各商品所持者が、自分の商品を等価形態(貨幣)にしようとして相争うことになり、結局、決定できないというのと論理的形式において同じです。
そして、最後に、ほかの誰もがこぞって、ひとりの人間に、自らのもつ権利を譲渡するのですが、これは、それ以外の他の商品を持つ商品所持者たちが、こぞって自分の商品に貨幣の役割を与える可能性を放棄し、特定の一つの商品に貨幣の役割を与えるというマルクスの論理と同じ形式です。
こう考えると、マルクスは、存在論的に解決すべき問題を、政治論的に、さらに言えば、社会契約論的に、解決しているということになるわけです。
むろん、今日、経済学的には、以上のようなマルクスの貨幣生成論はもはや問題にもなりません。それでも取り上げ直しているのは、ひとえに存在論的な問題のためです。マルクスの論証の挫折が示しているのは、存在論的には、平等性からは「表現する/表現される」という差異関係は生まれえないということにほかならないからです。そして、その不可能性の墓標の下から、存在論的にあきらかにすべき課題、すなわち、「表現される/表現される」関係はいかにして可能になるのかという問いが掘り起こされるのです。
といっても、はじめからこんなに明確に課題を意識していたわけではありません。はじめはただマルクスの論証への疑義を持ったにすぎませんでした。このような明示的な表現は、言うまでもないことですが、哲学の旅において今日到達した地点での所産です。
注──
(1) 『ヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学』第二十六節、細谷恒夫、木田元訳、中央公論社1974年p.137
(2) マルクス『資本論』第一部第一篇第二章「交換過程」向坂逸郎訳、岩波文庫p.156
(3) 同上第一章第三節「価値形態または交換価値」p.91
むろん、亜麻布20エレ=上衣1着、または亜麻布は一着の上衣に値するという表現は、上衣1着=亜麻布20エレ、または一着の上衣は20エレの亜麻布に値するという逆関係をも含んでいる。
(4) 同上p.92
(5) 同上第二章p.155
塚原誠司(つかはらせいじ)
1944年東京生まれ。1967年、早稲田大学文学部西洋哲学科卒業。労働運動系広報誌の編集者、塾講師、警備員などを経て、現在、自らの哲学を「自己言及的存在論」として展開している。
ポッドキャスト「自己言及的存在論講義」pod.link/1456031219