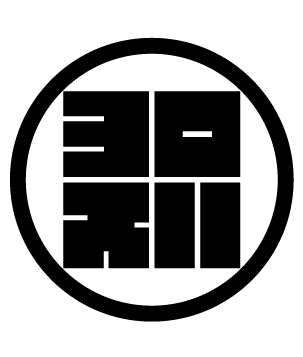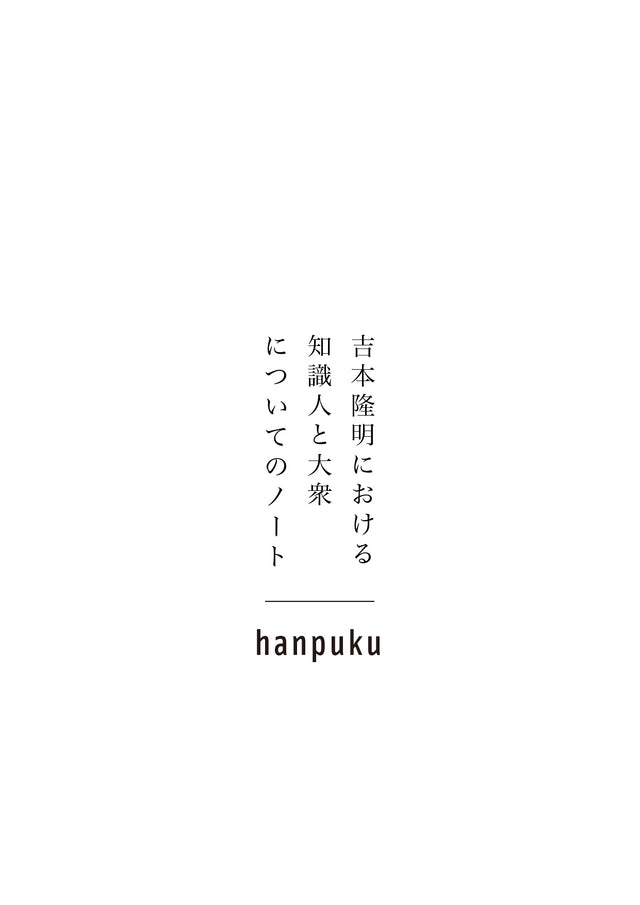
吉本隆明における知識人と大衆についてのノート
上下という空間認識に政治・社会的な状況をあてはめれば、上の内実は、国家・為政者・権力者、下の内実は個人・労働者・大衆、といったところになるだろう。この上下空間はあくまで仮定されたモデルであるため、上と下に本来的には意味はない。よって、上下の内実を入れ替えようとも差し障りはないわけだが、実際この状況に上下空間のモデルを設定した場合には、「上意下達」や「お上」といった用語群が内包する社会的・歴史的文脈を想起させざるをえない。ここでの文脈とは、共同体が歴史的に抱えてきた制度やコンセンサスの表象、またはその残滓のようなもだ。「民主」主義といえど民衆が下にある、カミシモの感覚を伴った認識は、言語表象や制度と社会成員の間に齟齬が残ったままであることを示している。
吉本隆明の着眼は、歴史的な変革は無名な大衆の行動の総和によって起こってきたという前提にある。その懐疑において「上」という言葉が抱えるような歴史的蓄積がどのように成立したかを社会的・歴史的文脈における、法や宗教の発生についての考察を通し問い直すことから、共同幻想における上の極点である国家とは別の、下=語義的な「民主」の共同体、ないしその自治形態が発生するための条件を考えていたといえよう。
吉本の思想の大まかな見取り図はマルクス主義に多くを負っている。このことは60年代彼自身がブントに随伴したことからも明らかである。しかし、安保闘争に関しても、法案の阻止以上に、民衆による社会変革の最後の契機だという考えで参加していた、という意味の発言もあることから、共産主義運動に対する吉本の立場は、純粋な権力闘争や法案への反対といった意味合いよりも、大衆運動による社会変革の可能性を見極めるための意味合いが強いものであった。それゆえ、その後の吉本の考えは原理主義的なマルクス理解からは離れ、そこから枝分かれした独特の思想を展開してゆくこととなる。国家や人間、歴史に対する根源的な問いを繰り返したことを鑑みれば、マルクス主義を相対化し、情況をいちから理解するための、普遍的な世界認識を自身の言葉で確立しなければならないと考えていたことが想像できる。左派の多くが革命の方法を問ういていた時代に、吉本が革命の条件を問ういていたとすれば、行き詰まった状況下で、彼の考えになんらかの希望を抱いたものがいたことも理解に難くない。
マルクス主義者たちと吉本が合致するのは、革命/根本的な政治社会変革の必要を前提として考えていた点であり、異なっていたのは、そこに至る条件への検討である。レーニン、トロッキーの理解では、資本主義発展の必然的な帰結として革命が発生し、共産主義へと移行するとし、その必然は知識人による大衆の啓蒙によって、大衆が知識人へと引き上げられることで起こると考えた。これに対し、吉本が知識人へ向ける視線はより厳しい。ただし、クリストフ・シャルルによれば知識人とは「国家理性にあえて立ち向かう文化的・政治的な前衛」と定義されていたが、吉本の指弾した知識人は、この定義に則れば、知識人のなり損ないのようなものといえるかもしれない。つまり、当時の日本の状況下において、知識人とされていた何者かに対する指弾であった。ここで目される日本的知識人とは、安保闘争期における左派インテリゲンチャであり、戦前におけるマルクス主主義者たちであり、ひいては明治期に近代化を推進した士族たち等、明治維新以降繰り返し現れる、西洋主体の知の在り方を受容することで知識人化した者たちのことである。
吉本は『転向論』において、日本的知識人の在り方を抽出するため、サンプルとして戦前の共産主義者たちの転向の問題をとりあげている。政府からの思想弾圧下において彼らが選ばされたのは、拷問を伴う投獄か、思想の敗北による社会的死の二択であった。日本的知識人たちは、西洋に由来する知識や論理的な思考法を学ぶにつれ、日本の社会機構や日常生活的を支える封建的な性質から遊離してゆく。しかし、思想的に日本を離脱したとしても、社会の成員として日本国内にある限り、遅かれ早かれその地の情況と向き合わざるを得なくなる。このような現実との対峙が、転向の問題では最も端的にあらわれるというわけである。
吉本は転向の問題が回避できない形で眼前に迫ったとき、日本的知識人のとる典型的な思考の経路はふたつあるという。ひとつは、理に合わず、つまらないなものとしてみくびり、正面から対決し損ねていた日本の封建制が、実際にはそれなりの秩序や構造をもった存在であることを認識させられることで、それらを意識から消すために学んだ西洋的=インターナショナルな知を貫徹できず、心の底に沈殿していた日本の封建的=ナショナルな知のあり方を呼び起こされてそれに屈するという転向の経路。ふたつめは、非転向の転向と呼ぶべき、日本の封建制にはおもねらないが、現実との対峙も拒むというものだ。この経路は、社会の現実の構造と歴史との対応から織り上げられる知のあり方を、それらのコンテクストから切り離し、自足し完結した論理として捉えることからおこる。対応する現実のない論理は、差し引きならない現実の変化に対しても、原理への固執という態度でそれをやりすごそうとする。このような態度は非転向として扱われる場合がほとんどであるが、これを転向の一種と考えることは、現実という基盤の変化とともに変化できない思想は死に体であり、論としての完結性だけでは社会の変革に至りえないという吉本の考えが透けて見える。そして、この考えの裏には、敗戦体験という個人の力ではどうにもできない社会変化に対応しなければならなかった戦中世代の感性が響いている。
これらふたつの典型に対する考えは、転向を行うことも行わないことも否定しているようでもあるが、ここでの批判の力点は、主体性の欠如によるの忘却と黙殺にある。吉本とも交流のあった戦中派の「荒地」派詩人たちは、文学者の戦争責任論というテーマにおいて、戦中に愛国詩を書いた/書かなかった、戦争肯定だった/戦争否定だった、という二分法での断罪ではなく、自身と戦争との関わりを総括せず、表現の血肉とさえしないままに、ただ「ブランク」の期間として忘却し、黙殺しようとする年嵩の詩人・文学者たちを信用の観点から批判した。戦中に自己形成期をくぐり抜けた吉本もまた、かれらと同様に「ブランク」に対する問題意識を抱えている。それゆえに、過去に信望したインターナショナルな論理を忘却し、あたかもはじめからそうであったかのように封建制に屈服することも、情況の変化から目を逸らしつづけることで現実の変化を黙殺することも、知識人のありうべき振る舞いとして充分なものとは考えなかった。
日本的知識人における、ふたつの袋小路を避けるための思想的隘路として、吉本は中野重治の小説、『村の家』における父子のやり取りをとりあげる。官憲に屈服し、転向して故郷に帰り、蔵で翻訳業をおこないながら暮らしていこうとする息子・勉次に対し、父・孫蔵が自身の考えを語る場面である。孫蔵は勉次に、
「おまえがつかまったと聞いたときにゃ、おとっつあんらは、死んでくるものとしていっさい処理してきた。小塚原で骨になってくるものと思て万事やってきたんじゃ……。」
という。吉本にいわせれば「孫蔵からみるとき、勉次は、他人の先頭にたって革命だ、権力闘争だ、と説きまわりながら、捕らえられると『小塚原』で死刑されても主義主張に殉ずることもせず、転向して出てきたインテリ振りの息子にしかすぎない。」(『転向論』)そのような息子に対し、孫蔵はこうつづける。
「おとっつぁんは、そういう文筆なんぞは捨てべきじゃと思うんじゃ。(…)おとっつぁんらア何も読んでやいんが、輪島なんかのこのごろ書くもな、どれもこれも転向の言いわけじゃってじゃないかいや。そんなもの書いて何しるんか。何しるったところでそんなら何を書くんか。いままで書いたものを生かしたけれや筆ア捨ててしまえ。それや何を書いたって駄目なんじゃ。いままで書いたものを殺すだけなんじゃ。(…)わが身を生かそうと思うたら、とにかく五年、八年と筆を断て。これやおとっつぁんの考えじゃ。おとっつぁんら学識アないが、これやおとっつぁんだけじゃない。だれしも反対はあろまいと思う。七十年の経験から割り出していうんじゃ」
これらは、なんら特別な語彙によるものではない、誰にでも発言可能な平易さであることにおいて、日本封建制の総体として知識人を糾問する言葉となりえている。庶民であることにおいて得られる倫理的な真っ当さを吉本は「日本封建制の優性遺伝」という。ひとつめの典型が屈服したのがそれである。それに対して勉次は、今筆を捨てることが知識人としての終わりを意味することを理解しつつも、知識人として居続けることと、封建制に屈することいずれかを選ぶことに迷う。そして、知識人であり続けるため語り得る説得的な論理も、庶民としての父の言葉に対しては、本質的に答えるものではないことを理解しながら、絞り出すように答える。
「よくわかりますが、やはり書いて行きたいと思います。」
吉本はこの言葉を、自身の論理がクリティカルな情況によって揺らがせられようとも、思考を放棄しないことによって、自らの意志で知識人であることを選び取ろうとするものとして高く評価する。忘却と黙殺によって「ブランク」を生み出すのではなく、ときには誤りも含む状況判断の積層を引責しつつも、思考の連続性と独立性を保ち、封建的な倫理と普遍としての知の論理を架橋しようとすることからしか「国家理性にあえて立ち向かう文化的・政治的な前衛」としての知識人は存在し得ない。その行為を絶え間なく続けることが知識人の役割であるとし、大衆と思想を突き合わせ続ける運動にこそ優位に置く。その終わりのない対峙を選び続ける姿勢の端緒が『村の家』にはあらわれており、これをふたつの典型から逃れる唯一の経路だとする。
対峙や対決という状況設定からわかるように、吉本は知識人と庶民=大衆を対等な関係として扱う。先に書いたようにレーニン、トロッキーにおいては知識人は大衆の上に措定され、かれらを引き上げる役割を担うが、吉本の考えでは、それらふたつの立場はどちらもそれだけでは有意義性をもたない。吉本は知識人化するということについてなんらの特権を認めておらず、ある環境条件が整った人間は自ずと知的に上昇し、それに伴い共同体を超えて社会、国家と視野を拡大してゆく。最終的には世界のもっとも高度な水準にまで必然的に到達する自然過程を持っているというが、高度は視野の広がりに対する比喩としての高さであり、ヒエラルキー的な上昇よりも疎外の概念に近い。知識人は主体的意志の結果により生み出されるのではなく、環境要因によって「自然に」生み出され、「自然に」西洋知≒普遍知の方へと引き寄せられる。上昇の結果知識人たちは、社会の構成を生活の水準によってとらえるための基盤を失うことになるが、そのような背離を抱える必然も含めて、それを「知識人の本質的な存在様式」であるとする。知識人は、ある種の知を得て上昇はすれども、大衆も大衆であることが自然状態であるのだから、そこに有意差は存在しない。ここで吉本が念頭においているのは『村の家』の孫蔵からでてきたような、知識人に拮抗する知が生活の中の言葉としてでてくるという点であろう。普遍知と拮抗する、体系として明瞭にあらわれない大衆の思想、または共有された意識の集合のようなもの。普遍知としての知だけが唯一の知ではなく、生活者としての知が存在するという観点においても、知識人と大衆は対等でありうる。このような意味でも、自然過程の内側にある知識人とは、封建制を無視しようとも、対立しようとも、封建制を補完する存在としてしか機能しえない。
「知識人の本質的な存在様式」に対して、大衆の存在様式は「もっとも強固な巨大な生活基盤と、もっとも微小な幻想のなかに存在するという矛盾が大衆のもっている本質的な存在様式である。」(『情況とはなにか』)と規定される。大衆とは、食べること、暮らすこと、蓄えることといった生活の繰り返しの中で日々直面する問題のみを重大事として考える存在であり、その生活範囲を超え出る社会領域における知識の問題などは考えない。彼らにあるのは現に生活し、明日も生活するということだけであり、それに対して情況が干渉していようといまいと、考えたとてどうなるものでもないという立場にある。大衆はこの限定された生活の範囲の中でしか考え方を動かさないことによって、孫蔵が勉次にしたように、態度を決めかねた知識人の韜晦を見抜き、生活者における知に基づいて、だらしのないものとして生き恥をさらすなと喝破することができるわけだが、その一方で、国家や政治といったものに対する包括的な視座をもたないため、それらからの支配に直通してしまうという矛盾を抱えている。その関係は、戦時中であれば、赤紙がくれば即座に応じて兵隊となり、敵を襲撃するにとどまらず、軍部上層の意図を超えた残忍さを発揮してしまう。大衆にとっての支配者とはまさにお上であって、そこから降り下ってきたものを、生活者の知によって解釈することで、このような過剰や狡猾さの発露がおこる。このような面を吉本は「日本封建制の劣性遺伝」と呼ぶ。大衆もまた、端的な善性として語ることのできない、裏表を抱えた存在といえる。
知識人と大衆の価値は等価に見積もられているが、存在する位相はそれぞれ異なっている。知識人は大衆から上昇的に疎外されていると同時に、国家からは下降的に疎外されている。そのため、世界というスケールを把握可能にする知的上昇によって情況と関わることはできるが、民主の主体である大衆からは離れる結果、運動を組織する母数を持たず、また国家のように直接に政治を動かす権力を持たない。一方の大衆は生活を基盤とし、そこから外に出ないため、国家や情況との直接の接点を持たないが、運動を動かすための母数をもつ。知識人と大衆の双方に対し抑圧的に機能する国家とは、労働生産などにまつわる経済機能により規定される社会的国家像と、宗教を起源として法に結実する政治的国家像が重なった存在である。前者はマルクスの言葉でいえば下部構造であり、後者は上部構造となる。マルクスは下部構造によって上部構造が規定されるといったが、吉本にとっては、上部構造としての「幻想」を介することよってしか人間は他者や社会と接触することができないと考える。そのため、マルクスに比べて上部構造の重みづけが大きく、下部構造の関与を最小限に見積っている。幻想とはフィクションやナラティブといった概念に近く、一対一、または個対多といった、人間が他者と関与するときに生み出される観念の共同性や、共通の語彙のようなものである。幻想の水準において、国際的な超国家という幻想が未だ生み出されていないことを鑑みれば、現状において国家は、最大のスケールをもつ共同体の幻想だと考えられる。それに対し、大衆のもつ幻想の水準は一対一の関係から生み出される対幻想をコアにしているという点で、最小スケールのものである。このことからは、幻想が一対一の関係から、協働関係、宗教、法と、それぞれの共同体の規模や関係性の変化に応じて、コンセンサスとしての幻想を生み出してきた結果、国家に到達するのであるが、それまでの間に支配層と大衆の分離がおき、大衆層はそのコンセンサスに浴することなく、最小の幻想に留まり続けた。この関係性は『自立の思想的拠立』においてこう示されている。「土俗的な言葉に着眼し、それをおしすすめて思想の原型を作ろうとしても、尖端的な課題にゆきつくことはできないし、また逆に世界の尖端的な言語から土俗的な言語をとらえかえすことができないという結節や屈性の構造があり、戦前から戦後にかけて、大衆的な課題を視界にいれようとした思想は、この不可視の結節をかんがえることができなかったために、虚構の大衆像をとらえざるをえなかった。」そのような意味で、最小の幻想による大衆の思想とは、国家とは別の方法で機能してきたと考えられる。吉本が大衆に対し可能性を見出すのはその点である。
自然過程の先に、主体的判断によって選び取ることのできる意識過程の領域がある。大衆にも知識人にもそこへ至る段階があり、それはそれぞれの立場での主体自我の確立過程ともいいかえられる。政治社会変革の可能性はその意志に賭けられているといっていい。先述の通り大衆は、国家からの支配を一方通行的に受容してしまう存在であるが、大衆から国家へのコミュニケーションの不在ゆえに、本質的には国家と接触しておらず、異なる位相に存在している。そのため、現状にある国家との支配・被支配関係を切り離す/自立することができれば、土俗的な一対一の関係からおこる幻想の地点から、本来的な「民主」の共同体が立ち上げることが可能だと考える。そのために大衆は、自身が生活する行為それ自体を意識化し、それ自体の思想的な意味を取り出さなければならない。これを「自立」と呼ぶ。注意しなければならないのは、近代性=国家と封建制=大衆の対立という形でなく、近代性と封建制とが矛盾のまま包括されている日本の社会構造=国家に対するオルタナティブを志向するという点である。近代化が伝統の偽造を促進するように、国家幻想において封建要素は近代性と必ずしも対立する条件となるわけではない。「封建的要素にたすけられて近代性が、過剰近代性となってあらわれたり、近代的条件にたすけられて封建制が「超」封建的な条件としてあらわれる」(『転向論』)わけだ。そして、大衆の自立による生活思想の確立はその外側におこる。念頭に置かれているのは、インターナショナルな知が、実際は西洋の土着性からあらわれたように、日本においてもそのような意味での知のありかたが必要であるという確信であった。そのような意味で、共同幻想論を書いて以降、吉本がアジア的段階、アフリカ的段階へと降りて行くのは必然であったといえよう。
では知識人の意識過程における課題とはなにか。『村の家』で勉次が選び取ったのは、自身の信じたインターナショナルな知を捨て封建制におもねることも、思想の中にすっぽり収まって情況をやり過ごすこともよしとせず、自然過程により上昇し拡大された視野を持ち続けながら大衆と向き合うということであった。これは知識人の意識過程の内に、自然過程における普遍的な知への探求の継続と、大衆との対峙の両面を含んでいることを意味している。意識過程にある知識人は、大衆と向き合うことで、大衆の存在様式とそれが情況の中でどのような位置と思想にあるかを読み取り、そのことを生活基盤から遊離した知識人自身の思想の中に、ある種の思想の重石として繰り入れる。吉本は知識人が把握すべき大衆の存在様式をひとつのモデルと考え「大衆の(存在様式の)原像」と呼ぶ。ここで像という言葉がもちいられるのは、大衆が言語化された思想体系をもたないため、書き残す言葉そのものを追いかけるだけではその実相を掴むことができず、外側にある知識人はかれらの振る舞いからその思想の輪郭をくみとらなければならないという理由による。知識人から大衆への視線の方向性を持つこの言葉の内には、吉本が自身の立場を徹頭徹尾知識人と認識していたということも含まれる。『情況とはなにか』に「わたしが大衆という名について語るとき、倫理的なあるいは政治的な拠りどころとして語っているのでもなければ、啓蒙的な思考法によって語っているのでもない。あるがままに現に存在する大衆を、あるがままとしてとらえるために、幻想としての大衆の名を語るのである。」とあることは、その証左だろう。知識人がとらえるべき「あるがままに現に存在する大衆」=大衆の原像は、「すべての時代をつうじて歴史をうごかす動因であったにもかかわらず、歴史そのもののなかに虚像として以外に登場しえ」(『日本のナショナリズム』)ず、「どんなに意味をつけようとしても、意味のつけようがない」(『情況とはなにか』)矛盾した存在である。情況との接点を持たないがゆえに、情況の変化によって位置づけを変えられてしまい、それにあわせて刻々と生活思想を転化させる大衆の動性を精確につかみ続けなければ、知識人の思想はアクチュアルなものにはなりえない。情況の中に布置された「大衆の原像」を絶えず自己の思想の中に繰り込むことを経て、知識人には自然過程の延長線上にある課題と、意識過程における本質的課題があらわれてくる。知識人の自然過程の延長戦にある課題とは、知識人が全政治情勢、全政治党派に対して単独で拮抗するだけの究極の理念を持つことにある。これは、大衆が自立によって国家のオルタナティブになりえるという考えと同じように、知識人が単独として国家のオルタナティブになりえるという考えである。しかしこの職業的知識人に対するビルドゥングス・ロマン的目標設定は些か、吉本自身もどこかで封建的な在りかたを内在していることを示しているようにも思える。一方、知識人の意識過程における本質的課題とは、自身の思想の中に繰り込み言語化した大衆の原像を、幻想の側に投げ返し常識化させてゆくことで、大衆が自身の生活を意識化する契機をつくることにある。最小の幻想の内に生きる大衆が、幻想の中に投げ返された思想的課題をどのようにつかむことができるのかという点は明示されていないが、知識人が大衆に知識を注入することが否定されている以上、投げ返された思想的課題は、受容されなければ空を通り過ぎて行ってしまうようなものだ。受容の可否は現象としてあらわれてくるものであっても、その判断の主体は常に大衆の幻想の側にある。思想と幻想が合致し受容されたさきに想定されていたのは、国民が戦争に向って一丸となり社会を動かした、戦前の運動エネルギーの大きさの体験とそれ自体へのフォーカスがあったのではないかと思う。国家における封建制と近代性の抱合と、大衆に内在するナショナリズムの相補性によって醸成された社会的ムードは、大衆の抱える最小の幻想とその情況の中にある位置と政策が偶然的/必然的に合致したものだった。戦後の吉本自身は戦争反対の立場であったが、そのような社会的な運動エネルギーとの協働がなければ、社会政治的変革は起こりえないという考えを持っていたのではなかろうか。
ともあれ、そのような課題に対する現状について、吉本は1966年の講演『国家・家・大衆・知識人』でこのようにいっている。「そういうことが具体化し、幻想として、観念の問題としてあらわれ、それがまた現実の問題として実現されるということが、情況として生まれたならば、それは僕が考えているひとつの希望というものの状態であるわけです。しかし現在僕はどんな希望をも持っていません。(…)しかし僕が希望というものを感ずることができるとすれば、そういうものが具体的なかたちであらわれてきたというときに僕は希望を感ずると思います。しかし現在はそういう兆候もない。それが僕の考え方です。」ここから60年弱を経た現在において吉本が希望とした情況はあらわれたかと考えれば、答えは否だろう。国家はキャンセルされておらず、人々が主体的自我を確立したかについては心許なく、そして膠着した国家-大衆-知識人の関係性は止揚されないままだ。しかし膠着状態であるがゆえに、ここで素描した吉本における知識人と大衆に対する見取り図は、現在も幾何かの有効さを保持しているともいえるだろう。(了)n.shukutani