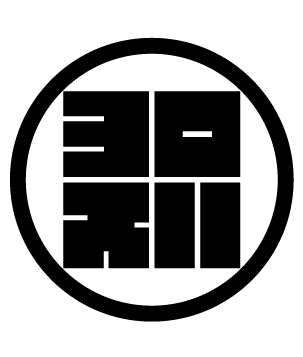思い出せないことを巡って
わたしはとても忘れっぽい人間だ。
生まれた時の記憶はもうないし、初めて食べた固形物の味も思い出せない。知り合いが友達に変わった最初の瞬間も忘れてしまった。それどころかもはや、15日前の15時に何をしていたのかも、3日前の夜に食べた牛丼を何回咀嚼して飲み込んだかすら覚えていられない。日々過ごすごとに、爆発的な量の情報が入ってくるけれど、ほとんどのものは通り抜け、動くたびに溢れてしまう。
あったことは覚えているのに忘れてしまった感覚がある。
スマートフォンがなかった頃があったことは分かるのに、上手く想像できなくなってきた。インターネットを使いだす前、円ドル相場が300円台だった頃、疎遠になった友人と仲が良かったときの感情。この調子でサブスクリプションが一般的になる前の世界ももうすぐ忘れるだろう。あったことは覚えているのにその感覚を取り戻せない。
自分が考えることぐらいは自分のものだと思いたい。しかし外側から入ってくる情報に絶えず晒されているせいで、気付かないうちに認識の枠組みがぐにゃぐにゃと変形してしまっているようだ。ほとんどの情報は流れ去っていくのに、いくつかの情報は川から突き出た岩に引っ掛かるようにして全体の流れに影響を与え、川のかたちを変えてしまう。元のかたちが思い出せなくなる。
自分が把握できる認識の枠組みの変化を考えていると、「いま、このことを考えている認識の枠組み」はなにによるものなのかを考えざるを得なくなる。世界から直接受け取っていると思っていたものごとが、実際は意識されない大きな枠組みによってフィルタリングされている。私達のコミュニケーションは、社会的な認識の枠組みの共通性を前提にしているので、その自明性を疑う機会はめったにない。しかし、規模の差こそあれ、個人の認識の枠組みの変化によって主体の一貫性がゆらぐように、何かのきっかけで変化がおこってしまえば、社会的な認識の枠組みといえど、同じように一貫性に対するゆらぎを抱えることになるのではないだろうか。
そのような大きな認識の枠組みの変化について考えた本に、柄谷行人の『日本近代文学の起源』がある。柄谷は、明治時代の文学=日本語表現の変化を通して、「西洋近代」における概念や制度を受容せざるを得なかった当時の日本で、どのような認識の枠組みの変化がおこったのかを詳らかにする。「西洋近代」とは文字通り西洋に由来するものなので、鎖国を経た日本と強い軋轢を起こしたことは想像に難くない。今あなたが読んでいる口語的な日本語の文章は、このような衝突のあとに生み出された新しい表現だったという。つまりわたしたちはそれ以前の日本語の在り方がどのようなものだったか忘れてしまっている。より正確に言うなら私達の社会は、それ以前の日本語の在り方を忘れてしまっている。
柄谷の考える認識の枠組み(柄谷は認識の布置という)の変化の仕方を私なりに整理してみるとこうなる。人間の認識の枠組みは、上から用意された制度を素直に受け入れて変化するようなものではない。認識の枠組みは、概念や制度が内面を満たすことで無意識のうちに変化してしまう。そして、私達はその変化がおこってからしかそのことに気づくことができない。たとえ自主的に概念や制度を選び取ったとしても、その変化がもたらすものによって、本質的に何を選び取ってしまっていたのかということと、その変化が不可逆であることを事後的に理解することになる。概念や制度のもたらすものの重大さを理解したとしても、濁流に飲み込まれるようにその変化に従わざるを得なくなる。歴史は過去から現在に流れるように記述されるが、実際は変化に気づいてから遡って見いだされた原因を、直線的な時系列に配置しなおしたにすぎない。単に利便性のために選んだ概念や制度が、認識の枠組までも変化させてしまうリアリティを、歴史が伝えることは困難である。そして、認識の枠組みが完全に入れ替わり、それが自明のものとなったあとでは、何によってこの変化がおこったかの起源を忘れてしまう。
西洋諸国と対等に渡り合うために「西洋近代」を受容した日本は、その概念や制度の根本に存在する「自我」や「内と外」といった、それまで存在しなかった懊悩を抱えることになった。柄谷はその出現を抽象的思考言語=言文一致的な言語の発明から広がるパースペクティブの中に見出すのだが、紙幅の関係でここでは触れない。ただ、自分探しをし、自分の実感が他人と共有できないもどかしさに悩む現代人は、間違いなく明治時代におこった認識の枠組みの変化の延長線上にある問題意識を抱えている。自己とは何かという問題設定が立ち上がること自体が西洋由来のものであって、それこそが概念や制度を選んだ時には気づけなかった、選び取ってしまった本質的なものであったというわけだ。
社会的な認識の枠組みとは、皮膚と一体化して外せない色付きゴーグルのようなものだ。生きている間に「ある時代と社会における知の枠組み」の入れ替わりが起こらなければずっと同じ色、同じ視野で世界を認識することになる。何かのトリガーで新しい枠組みが発生すると、それは感染症のように広がり、ゴーグルの色とレンズの範囲を変化させる。世代の入れ替わりによって過去に人々が付けていたゴーグルの色や視野は忘れられ、新しいゴーグルのフォルムを通してフィルタリングされた認知に適応される。このことを言葉として理解するのは簡単だ。しかし体感としてこの枠組みを把握することは一筋縄ではいかない。今このように文章を書いている間にも、視線をうごかし風景を見る間にも、その認知の枠組みは機能しているのに、それが働いている機序を分割して把握することができない。
認識の枠組みの変化に伴ってそれ以前の感覚を忘れてしまうと、新しい認識の枠組みの中の認識機序が透明化し、その外側にある異なった枠組みを想像できなくなる。自分が中にいる枠組みがどのようなものか認識できなければ、自分が何によって物事を認識しているのかにも気付けない。認識の枠組みの変化に気づき、その意味を理解したときに初めて歴史が現れるのならば、いまだに見出されていない変化の存在は、現在と過去の出来事のつながりに未だ渡されていない橋が存在することを暗に示している。しかし、残念ながら認識の世界に対して完全な地図は未だ用意されておらず、洞窟の暗がりを手探りで調査するしかない。幸い先人たちが残してくれた文献が、ところどころの岩肌を照らしているので、それを頼りに先に進むことはできる。社会的なものであれ、個人的なものであれ、私達は物事を忘れていくことを止めることはできない。けれど、忘却に抗い、認識の枠組みの変化に気づき続けるためには、自分なりの仕方でその輪郭をたどり、その意味のありようを繰り返し考えることから始めなくてはならない。
n.shukutani